食事を終えて店を出ると、港の空模様はすでに怪しく変わっていた。
遠雷が腹の底を震わせるように響き、ほどなくして稲妻が白く路地を照らす。
「うわッ……近ッ!?」
サタヌスがビクッと肩を跳ねさせ、その場にしゃがみ込んで耳を塞いだ。
ガイウスは思わず目を丸くする。
「お前、雷怖いのか? 意外だなー」
サタヌスは真顔のまま返す。
「屋根ねぇとこで鳴る雷の怖さ知らねぇだろ。一発で丸焦げなんだぞ」
そんな二人を見上げながら、ヴァレンは涼しい顔で空を仰いだ。
「まぁまぁ。雷は怖くないよ」
その瞳に一瞬だけ稲光が映り込み、薄い笑みを浮かべる。
「ラブコールさ――神様から人間へのメッセージ」
「……なんだそれ」
ガイウスは呆れ顔を向ける。
ヴィヌスは肩をすくめ、軽く笑った。
「クードス節よ。ここの住人、時々ポエマーになるの」
次の瞬間、稲光が走り、ヴァレンの横顔が鋭く光に切り取られた。
その一瞬だけ、笑顔の奥に何か底知れない影が潜んでいるように見えた。
やがて、雨の匂いを含んだ風が路地に流れ込む。
分かれ道の前でヴァレンが振り返り、口角を上げた。
「じゃ、夜はいいトコ連れてく。港の風、気持ちいいからさ」
「……雨ならパス」サタヌスがぼやき。
「“勇者ちゃん”言うな。俺は勇者ガイウス」ガイウスはまだ拗ね気味に釘を刺す。
ヴァレンは片目をつむり、ウィンクを返した。
「はいはい、勇者ちゃん」
再び遠雷が小さく転がり、クードスの夜が静かに、しかし確かに深まっていった。
雨上がりの石畳はまだ濡れていて。
街灯や提灯の光を映し込み、広場を淡く照らしていた。
風に吹かれて紙吹雪が舞い、生演奏が再び始まると、人々は自然に輪をつくって踊り出した。
その中心に、ひとりの金髪の青年がすっと入った。
動きは流れるように軽やかだが、どこか異質な鋭さを纏っている。
フードの影の下、頬に黒いマークがちらりと見え隠れする。
「お、舞踏だ」
「誰だあの兄ちゃん――キレがヤベぇ」
地元客が息を呑む。青年のステップは剣士の踏み込みを思わせるほど正確で。
回転は雷鳴のように速く、観客の目を奪った。
ガイウスは目を細め、吐き捨てるように呟いた。
「……ダンスって、あんな“斬れる”もんなのか」
隣でヴィヌスが低く囁く。
「所作が舞台じゃない、“道場”のそれね」
演奏が切れ、余韻の中で青年がふっと視線を上げる。
柔らかな笑みを浮かべながらも、その奥に冷たい光を宿していた。
「そこの色黒い坊主、カリヤから来たのかい?」
「は?……オレはスラムだが」
サタヌスが怪訝な顔をする。
青年は口元に笑みを残したまま続ける。
「そうかい。カリヤはいい所だよ。魂は巡るって考える。
“死ぬ”ってのは、向こうの季節に帰るだけだ。怖がる必要はねェ」
ガイウスは眉をひそめる。
「……妙な慰め方だな」
次の瞬間、雷光が夜空を裂き、金の髪が白く焼かれる。
青年はステップひとつで輪の中から消え、観客の視線だけが虚空を追った。
「クードス、人懐っこい狼ばっかだな?」
サタヌスが肩をすくめる。
ヴィヌスは目だけでその残影を追い、低くつぶやいた。
「狼っていうより……雷ね」
石畳の路地を抜け、宿へと戻る途中。
夜風が港から吹き抜け、ガイウスはふっと立ち止まって海を見やった。
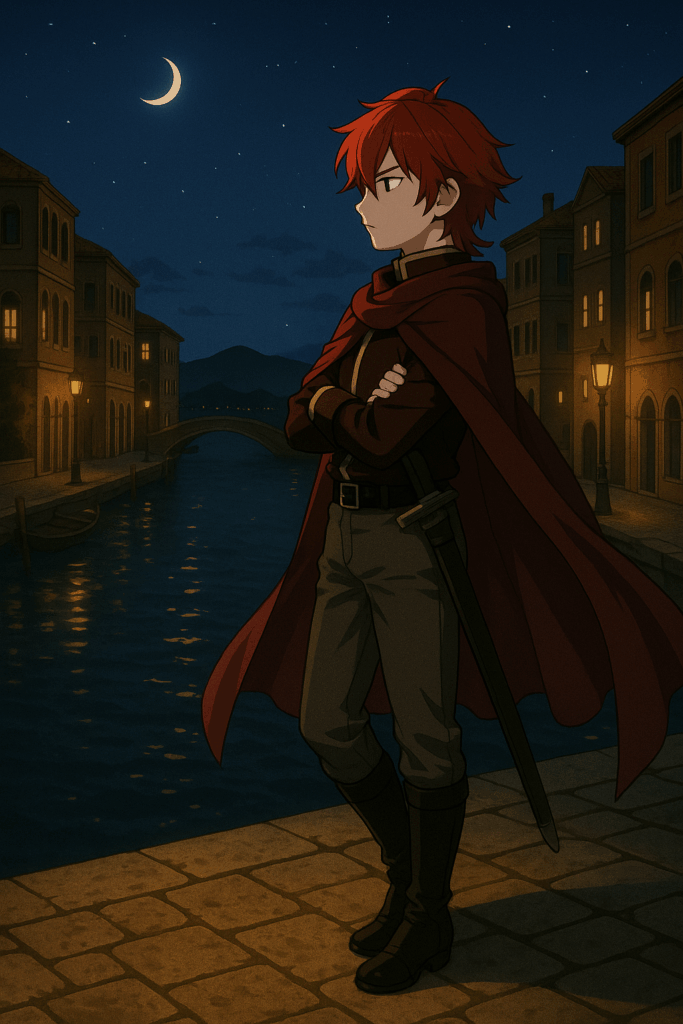
「アルビオン島……ここからじゃ見えないよな」
小さくこぼした声は、波音にさらわれていく。
ヴィヌスが振り返り、わざと艶めかしく笑う。
「残念ね♪ アルルカンやソルーナからなら、はっきり見えるのに」
サタヌスは肩をすくめ、にやつきながら茶化した。
「ブリテン、パスタ食えなくてホームシックか?」
ガイウスはむっとして返事もせず、赤いアホ毛を夜風に揺らしながら再び歩き出した。
宿に帰る途中、祭りの余韻がまだ残る石畳の通りを歩いていた。
運河沿いの街灯が水面に揺れ、夜風が赤いマントの裾をさらう。
三人の影が伸びて、石畳に重なっていた。
ヴィヌスがふと歩みを緩め、横を歩くガイウスをじろりと見る。
「ねぇ、あんた何気にアルキード訛りすごくない? 島国訛りってやつ?」
「……は?」
ガイウスは眉をひそめた。
「イントネーションが違うのよ、デリンやアルルカンの人たちと。
ほら、“ガイウス”の発音も、無意識に“ガイアス”寄りになってる」
ヴィヌスは楽しげに口元をゆがめ、わざと誇張して「ガイアス」と呼んでみせる。
サタヌスが後ろから追いつき、ニヤニヤしながら口を挟んだ。
「言われてみりゃそうだな。俺らが“ガイウス”って呼んでも。
返事するとき微妙にイントネーション違ぇんだよ」
ガイウスはむっとして視線を逸らす。
「……島の発音がそうなだけだ」
ヴィヌスはワイン色の瞳を細め、肩をすくめた。
「ま、別に悪いことじゃないわ。むしろ“あんたはアルビオンの人間だ”って証でしょ」
その言葉に、ガイウスの胸にわずかなざらつきが走った。
アルビオン島――ブリテン。今は遠く、夜の海の彼方に沈んで見えない故郷。
「……ガイアス、ね」
小声で呟くと、アホ毛が夜風に揺れて、港町の灯の中に溶けていった。
石畳の路地を抜け、宿へ向かう途中。
夜の海風が冷たく頬を撫で、遠い波音が港町の喧騒をさらっていった。
ガイウスはふと立ち止まり、暗い水平線を見つめる。
「……俺、あの腹黒王族とは当面顔も見たくないんだが」
吐き捨てるように言いながらも、瞳は海の彼方に釘付けだった。
「だけど……あの島が海に見えないってだけで、こんなに寂しいんだな」
ヴィヌスもまた、立ち止まって彼の横顔を見やった。
月明かりに照らされるその表情は、戦場で見せる強気な勇者のものではなく。
遠き故郷を思う、ひとりの青年のものだった。
「気持ちわかるわよ」
ヴィヌスは静かに口を開いた。
「オーゼを出た時は、こんな雪国出て行ってやるって思ったのに……」
彼女はほんの少しだけ、唇を噛んでから続ける。
「アルルカンに雪が積もらないことに、不満を抱いている私がいるのよ」
二人の吐息が夜風に混じり、交わる。
故郷を憎みながらも、離れて初めて募る恋しさ。
言葉にすれば矛盾だが、その矛盾こそが彼らの胸を占めていた。
サタヌスが後ろから追いつき、肩をすくめて笑う。
「やれやれ、ホームシック同盟かよ」
港の灯が揺れ、三人の影を長く伸ばしていた。
港の夜風に吹かれながら歩く三人の背を、暗がりから見つめる視線があった。
石造りの建物の影に佇むのは、先ほど広場で鋭いステップを見せた金髪の青年。
フードの奥に浮かぶ笑みは、月明かりの下で不気味に静まり返っている。
「勇者ってのは、昔から仲良しなもんだ」
独り言のように呟き、目を細める。
「その分、叩き潰してやる楽しみが増える」
唇の端が吊り上がり、頬の黒い紋様が一瞬だけ稲光に照らされる。
そして、声を転がすように低く笑った。
「……くわばらくわばら」
遠雷がごろりと夜空を揺らし、港町クードスの闇がいっそう深く沈んでいった。