陽が傾き始めた公園。
ベンチに座るマケルーダは、たい焼きを手にふにゃっと悩んでいた。
目の前でアヴィドがカップケーキをかじりながら。
まるでラジオの人生相談みたいなテンションで語り出す。
「マフィンちゃん、そんなんは勢いだよ」
アヴィドは相変わらずの脱力系スマイル。でも、言葉は妙に現実的だ。
「俺もマデリーと付き合ってた時、なんか…“ハイ”になった勢いでそのまま行っちゃったし」
マケルーダは一瞬、目をまんまるにした。
「それ、普通に後悔するやつじゃ…?」
アヴィドは肩をすくめて、ベンチの背もたれに体を預ける。
「いや~、愛って大体その場のノリで育まれるもんだからさ」
「理屈で考えてると永遠に進まないぜ?大事なのは“勢い”と“ハート”」
魔王少女、あまりに現実的な助言に一瞬フリーズ。
吸血鬼界のヤンデレ代表が、まさかの現実主義。しかも淡々と。
ふと思い出したように、アヴィドは優しい目で遠くを見た。
「マデリーとの愛は永遠だけど、披露宴は一生に一度だからな?」
家計簿をつけるヤンデレ。
しかもめっちゃ丁寧。
その背中、完全に「できる主夫」
「会場の広さ、料理のランク、ドレスは絶対マデリーの希望通り……」
「でもプランAとBの差額が……」
「あと引き出物ってこれ…吸血鬼向けのやつ選べるの?」
細かい。
ベンチの端でノランが吹き出す。「ヤンデレのくせに現実主義すぎw」
アヴィドは照れもせず、「愛と生活は別腹なんだよ」と返した。
その一言が、逆に説得力しかない。
マケルーダはたい焼きを見つめてつぶやく。
「うーん…たい焼きの勢いでやるものなのかな…?」
「たい焼きは勢いで食うのが一番美味いし、恋も同じだよ」
アヴィドの真顔に、思わず納得しかける魔王少女。
公園に風が吹く。
たい焼きの香りと、なんだかんだリアルな人生アドバイスが混ざった午後だった。
マケルーダはベンチの上で両手をぎゅっと握り、空を見上げていた。
「愛は勢い…よし、練習だ!」
誰に聞かせるでもなく、ひとりで気合を入れる。胸の奥まで空気を吸い込んで――
「えーと…えーと……ホテル行こう!!!!」
まさかの超大声。公園中に響くテンションMAXの絶叫。
次の瞬間、茂みの影からジャラ…と不吉な鎖の音がした。
「へぇ~?マケルーダちゃん、俺とホテル行きたいってこと~?」
物陰からクヴァルがヌルッと登場。片手で鎖をクルクル回しながら、悪い笑みを浮かべる。
「そりゃあ…お兄さん喜んじゃうなぁ~」
全身が一気に凍りついた。
「違うわ!!帰れ妖怪ィィ!!!」
マケルーダは全力でたい焼きをぶん投げた。
「おっと、危ない危ない。食べ物は大事にしなきゃねぇ」
クヴァルは涼しい顔でたい焼きをキャッチする。
天桜市の女子校生、いや全種族共通の鉄則が脳裏をよぎる。
――“あの男とだけは絶対にホテルチェックインしてはいけない!”――
クヴァルは悪びれもせず肩をすくめる。
「え、呼ばれたから来たのに~?ひど~い!」
鎖を指でクルクルしながら、目はぜんぜん笑っていない。
そこへアラネアが、慌てて駆け寄ってきた。
「お兄様がホテルとかありえませんわッ!!」
妹の全力阻止が入る。
ノランは大爆笑。
「社会的に危険すぎるからやめとけマジで!」
カティーヌは呆れ顔。
「そもそもなんで物陰にスタンバってるのよ…!」
マケルーダは頭を抱えた。
「よりによって一番アウトな奴呼び寄せるとか、私の引き運どーなってんの…」
クヴァルは最後までにこやかに「まぁまぁ、冗談冗談♪」
――ぜんっぜん冗談に見えないまま、鎖がまたジャラリと鳴った。
公園の夕焼けに、魔王少女の失敗練習だけが妙に鮮やかに響いていた。
日曜前夜、天桜市の公園は昼間とちがってどこかしら静かだった。
街の灯りがゆっくり滲む中、マケルーダはたい焼きを片手に、スマホで友達とやりとりしていた。
「まこちゃん、明日は日曜だから今日は夜更かしタイムだね」
「うん。ダンピールだから」
マケルーダは嬉しそうに返事する。「だから明日は昼まで寝てる、ごめんね~」
「いいのいいの、楽しんでね夜更かし!」
――魔族と人間のハーフ、ダンピール特有の“メンテナンス日”。
吸血鬼の夜行性と人間の昼行性のあいだで、どちらにも振り切れない彼女たち。
体内リズムを保つために、週一だけは徹夜OK。
それがこの世界の「夜ふかし組」の日常だった。
たい焼きを頬張りながらベンチに座るマケルーダ。
横にはカップケーキを持ったアヴィドがのんびり座っている。
「…今日は日曜だし、一応ダンピールだから夜も元気!」
「クェーサーいるよ、マフィンちゃん」
アヴィドはさりげなく耳打ちしてきた。
「……ホテル行く?」
ニヤリと笑う顔は、相変わらず吸血鬼特有のイタズラっぽさが混じっている。
マケルーダは両手で顔を覆い、そのままベンチからずり落ちそうになった。
「ムリ…自主練いっぱいしたけど、本番は無理…」
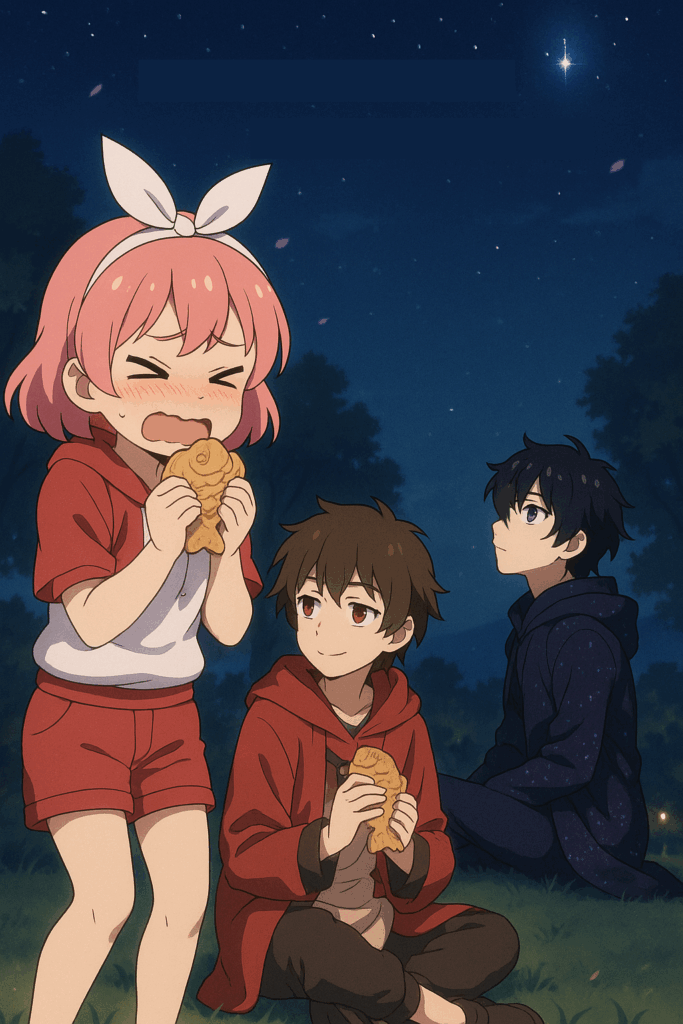
夜風が少しだけひんやりして、
でも、たい焼きの温かさが手のひらから逃げていくことはなかった。
公園の夜。
クェーサーの横顔が、街灯の明かりからも月光からも切り離されて、ただ星空に溶けていく。
その横顔を見ているだけで、
マケルーダは思わず「やっぱオベロン……」と心の中で呟いた。
人間の常識も都合も一切通じない、神秘的で異質な何か。
夜の静けさに包まれると、クェーサーの“人間味ゼロの美しさ”が、逆に怖いくらい浮き上がって見えた。
自分もそばに座ってみる。
けど、どうしても顔を見ると声が出なくなってしまう。
「やっぱ顔見ると声でない…!」
たい焼きをぎゅっと握りしめて、ドキドキだけが胸の中で暴れている。
そんな様子をアヴィドは遠くから見ていた。
「すぐに言えなくていいよ」
「むしろ“うぶな子”って好かれるよ、統計学的に」
無駄に優しい吸血鬼は、カップル長続き率データとかまで知っているらしい。
「統計学やめろ!」
マケルーダは顔を真っ赤にしながら、ツッコミにもならないツッコミを返す。
それでも、アヴィドの中にある“無理しない恋愛”への静かな肯定は、
どこか温かくて安心できるものだった。
クェーサーは星を見上げたまま、誰にともなくつぶやく。
「…夜の天桜市は好きだよ」
その声は、どこまでも遠くて、優しかった。
マケルーダは何も言えずに、その背中を見つめながら
たい焼きを小さくかじる。
甘さと温かさと、少しだけ切なさが夜風にまじっていった。