—-フーロン国境「麒麟砦」
「止まれ!この先はフーロン、通行許可証がないものは通さん」
「ガイ君、あの許可証出して」
「おう」
ガイウスが懐から皇帝に貰ったあのカードを見せると門兵は頷き敬礼をした。
どうやら皇帝の威光は大陸中に轟いているらしく、入国手続きは非常にスムーズに進む。
目の前の門には馬のような獣が描かれている。あれはなんだ?と首を傾げる。
ガイウスにバルトロメオが耳打ちする。
「麒麟だよ。簡単に言えば神の使いだね」
「ふーん、神の使いてことは……炎とか吐くのか?」
「はははは!それは荒ぶる神獣さ。麒麟は違うよ」
バルトロメオはにっこりと頷き、ガイウスも頷き返すと。
兵士に促されるまま砦の中へと進んでいく。だがしばらく進んだところで異変が起きた。
ネプトゥヌスから「虹の瞳」について聞いていた門兵がガイウスの顔を覗き込んだのである。
「……待て。その目。色が……不安定なんだが……!?」
「……へ?」
ガイウスは思わず目をそらした。
しまった――。
緊張のせいで、“虹の瞳”が僅かに揺れている。
青と金、紫の光が瞳孔の奥でグラデーションを描いていた。
「おい、透鏡(カラコン)か?それとも魔術か?術式干渉か?」
「えーとそれは……」
「はいッ!!」
ルッツが飛び出した。
「レンズ表面が構造色になってましてね!
タマムシ見たことあるでしょ!?同じです同じッ!!」
「構造色……?」
「そう、光の干渉で色が変わって見えるやつです!!
あの目、帝都で大人気なんですよ!“勇者の瞳”モデルって言って!」
バルトロメオも負けじと横から口を挟む。
「ねぇ、知ってた?帝都の女子の間じゃ“七色の瞳で見つめられたい”が告白テンプレなんだよ?」
「な、なにィ!?」
門番が押され気味になり、冷や汗を浮かべる。
一方ガイウスは黙ったまま、無表情でそのやり取りを見ていた。
(俺、タマムシ扱いされてる……?)
苦い思いを噛みしめながら、手元の剣の柄を握りしめる。
だが今は口を出すべきではない。
この場面、空気を読んだ方が勝つ。
それを、彼は旅の中で学んでいた。
「……わかった。とにかく目立つ色だ。フーロンでは目をつけられるぞ、外出時は外せ」
「お気遣い感謝します!」
3人は一礼し、門を通過した。
関門を抜けた直後、3人は同時に深いため息を吐いた。
「……切り抜けた……」
「帝都でも売ってないのに、あんな堂々と“カラコン”とか言っちゃってさ……」
「……俺、マジで一人旅じゃなくてよかったわ」
彼らの旅は続く。
虹の瞳は“勇者ごっこ用カラコン”として世を駆けていくのだった。
「おいバル!キズ野郎見て! スゲェいい景色だよ!」
ルッツが目を輝かせて指差す。
ガイウスとバルトロメオが並んで丘の縁に立つと――眼下に広がる光景に息を呑んだ。
赤い瓦屋根が幾重にも重なる街並み。
水路が碁盤目のように走り、石橋が優雅な弧を描いて架かっている。
街の中心には、何層にもそびえる塔――楼閣が空を突くようにそびえていた。
遠くには霞む山々が連なり、緑濃い稲田と川の流れが、その合間を縫うように光を反射している。
まさしく、帝国ともアルキードとも違う。
異国情緒に溢れた光景だった。
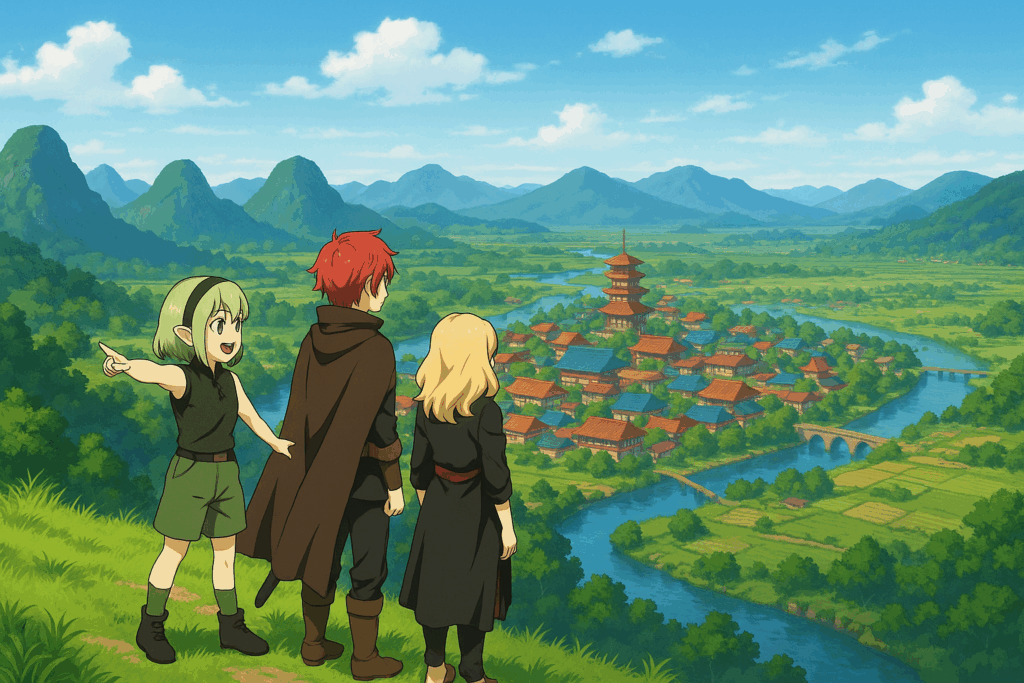
「……なんか異国に来たって感じだね」
「だな。ひとまず峠降りるぞ、ネプトゥヌスがいるはずだ……そして」
あいつがいる、ガイウスは宿敵の存在を感じ取って鼻の古傷を無意識になぞった。
そして一行は峠を降りていく、その足取りは重かった。
「――聞いたか?最近帝都じゃ、“虹の瞳”がまた流行ってるらしいぞ」
丘を下るすれ違いに、歩いていた商人風の男が話しかけてきた。
旅の道中で聞く噂話――だがその内容に、ガイウスの足が止まる。
「なんでも、あのユピテルを討った勇者……」
「シャボン玉のような、玉虫のような、不思議な瞳をしていたとか」
「それでな、デリン・ガルの職人たちが躍起になって。
“再現できねえか”と、虹色カラコンの開発に取り組んでるらしいんだよ」
「……そ、そうですか」
ガイウスは、引きつった笑みで答えた。
商人が立ち去った後、沈黙が訪れる。
誰も、最初に口を開こうとしない。
やがて、バルトロメオがポツリと呟いた。
「……ガイ君、たぶん近いうちに」
「本当に、“カラコンで通る”ようになるよ」
ガイウスは視線をそらし空を見上げた。
燃えるような髪が風に揺れ、瞳が静かに光る。
「……俺はカラコンじゃない」
「うん、わかってるよ」
ガイウスは何も言わなかった。
だが、心の中では叫んでいた。
(俺はなァ……“カラコンの勇者”じゃねぇ……!)
(最初からこの目で、地獄を見てきたんだ……!!)
それでも彼は黙って歩き出す。
淡く揺れる“虹の瞳”で。
丘を下り、ホアリンへと続く街道を歩いていると、すれ違う商隊の列が見えた。
荷台を引いているのは鉄の車輪でも、魔導エンジンでもない。
――巨大なトカゲだった。
「なっ……ランドリザード!?」
ガイウスが無意識に剣の柄へと手を伸ばす。
帝国で襲いかかってきた盗賊団の、あの獰猛な魔物。
だが商人たちは驚く様子もなく、長い手綱を操って荷台を進ませていた。
「あぁ、驚いたかい?」
先頭の商人がにこやかに声をかけてくる。
「フーロンはとにかく道が険しくてねぇ。魔導エンジンじゃ振動に耐えられず壊れちまうんだ。
その点こいつは馬と違って、干し肉さえありゃどんな悪路でも耐える。
産業革命の時代でも、まだまだ需要は尽きないのさ」
商人が慣れた手つきで、袋から乾いた肉片を放る。
ランドリザードが嬉々として咥え込む――それは、干からびたゴブリン肉だった。
「……おい、畑荒らしの常習犯を餌にしてるのか?」
「ありふれたもんだよ。手に入りやすいし、こいつらも好物だからな」
何気ないやり取り。だがガイウスたちにとっては衝撃だった。
帝国の蒸気と魔術で彩られた文明とは全く違う。
フーロンの民は、魔物を“敵”ではなく“生活の一部”として組み込み。
それを当然のように受け入れている――。
「……あ、ほんとだ。煙突が一本もないよ!」
ルッツが見下ろせば、街並みに赤瓦は連なっているが。
帝国の町では当たり前に見えた黒煙の柱がどこにもない。
隣を歩いていた商人が、肩越しに振り返って苦笑する。
「俺達が拒んでるわけじゃねぇんだ。むしろ自動化してもらいたいくらいさ」
「けどな――雨と山で機械がすぐ音を上げちまうんだよ」
「高温多湿でサビる、坂で車輪が外れる、冬は氷で管が割れる……」
男はそうぼやきながら、荷台を引くランドリザードの背をぽんと叩いた。
「俺達が機械にあやかれるのは、もう少し先になりそうだなァ」
石畳のはずの街道は、登るほどに傾斜が増していた。
荷を背負って歩く旅人たちは皆、肩で息をしている。
「……言われたらほんとだ……舗装されてるはずだよね?」
ルッツが額の汗を拭いながら、愚痴とも驚きともつかぬ声をあげる。
「山登りかってくらいきついんだけど……」
「あぁ」
バルトロメオが頷いた。
「だからフーロンから来る冒険者って、タフな奴らが多いんだな」
フーロンから来る冒険者は総じて“タフだ”と言われる。
それは単なる噂話でなく、実際の冒険の場で幾度となく証明されてきた。
かつてデリン帝国の依頼で険しい山岳に登ったことがあった。
帝都育ちの貴族出身の戦士や、アルルカンの剣士たちは。
急な坂に足を取られ、息を切らし「歩けない!」と音を上げた。
だが、その中に混じっていたフーロンの踊り子は。
額に汗ひとつ浮かべぬまま笑顔を絶やさず、こう言い放ったのだ。
「街道より歩きやすいじゃない」
その言葉に一同は凍りつき、同じ人間かと訝しんだほどだった。
また、帝国の討伐隊に随行した際、夜営の最中に爆竹の音が山間に響いた。
兵たちは「賊の奇襲か!?」と色めき立ち、武器を構えた。
しかしフーロンの傭兵だけは泰然と茶を啜りながら言った。
「心配いらない。あれは子供が祝祭で鳴らす音だ」
そう言いながら茶を口に含む姿に、逆に帝国兵たちが腰を抜かしたという。
山も祭も、異国では試練や恐怖に変わる。
だがフーロンの民にとっては、日常そのものなのだ。
ガイウスは商人たちと話しながら、2人を見やる。
勇者は超人、しかし今同伴する2人は違う。
「……俺はまだ平気だが、二人がきつそうだ。休憩所はどっちだ?」
すると、ちょうど荷台を引いた商人が通りかかり、彼らの会話に耳を傾けて笑った。
「おや、初めてかい?なら無理もない。
フーロンの街道は帝国やアルキードと違って、平坦じゃないんだ」
彼は荷を曳くランドリザードの首筋を軽く叩きながら続ける。
「休憩所を探すなら、この道を真っ直ぐ降りて谷を抜けるといい。
半日も行けば“ホアリン”に着く。宿場町だから、茶屋も風呂も揃ってるさ」
ルッツの顔がぱっと明るくなる。
「マジで!? やったぁ!」
ガイウスは小さく頷き、視線を先の谷へと向けた。
異国の道は厳しい。だが、その先に確かな休息と新しい出会いが待っているのだ。