大龍祭を前に、ガイウスは剣を腰から外し、勇者服を脱ぎ捨てた。
身にまとうのは、フーロンの武闘家が着る黒と朱を基調とした装束。
布帯で腰を固く締め、袖は軽やかに風を受けるよう仕立てられている。
肩から垂れていたマントはなく、動きやすさを優先した純粋な「戦舞」の衣。
町の広場でその姿を現すと、すれ違う者たちの視線が一斉に彼へ注がれる。
妖狐の娘が囁く。
「え?かっこよくない? 昨日のマントより三倍はイケてるじゃん」
鬼族の青年が腕を組み、惜しげに首を振る。
「惜しい……髪が黒いなら完璧だったのに」
ざわめきが広がる。いつも「異国の勇者」として浮いていたはずの赤髪。
今日は逆に祭りの華のように町に馴染んで見えた。
布を翻し構えを取るその姿は、剣士ではなく、拳で世界を切り開く武闘家。
仲間たちも目を丸くする。
「え? イメチェンし過ぎじゃない?」
ルッツが思わず声を上げる。
ガイウスは得意げに口の端を上げ、軽く扇を翻す。
「惚れるなよ?」
「だ、誰が惚れるかっ!!」
ルッツは顔を赤らめて即座に反発した。
宿場町のざわめきの中、勇者は新たな姿を披露した。
赤髪に虹の瞳、そしてフーロン衣をまとった武闘家。
その立ち姿は「転職」という一言では片づけられない、確かな変化を告げていた。
「いや~まさか。あんさんにサイズ合う服があったとは驚きダワ」
ハオが手を叩いて笑う。
ガイウスは道着の裾を少し引っ張り、肩をすくめて苦笑した。
「ああ……店員に“鬼向けですが”って言われたのはちょっと引っ掛かったがな」
これから鬼――マルスを倒すための稽古をつけるというのに。
鬼用の道着を着る羽目になるとは皮肉な話だ。
「でもま。おかげで武闘が始められるヨ」
「……なぁ、いつもの服じゃダメなのか? 武闘家ってのは」
「ダメネ。服も型のうちヨ」
着慣れない装束に身を包みながら、ガイウスは落ち着かず周囲を見回す。
視線の先、宿場町の広場には見物人が集まっていた。
モブ妖狐が扇を手に目を輝かせ、鬼族の若者が腕を組んでうなずいている。
「……注目される……」
思わず頬が赤くなる。
ハオはそんなガイウスの肩を軽く叩いた。
「よろしい。じゃ、シャオヘイ」
すぐ傍らに控えていた黒衣の少年へ、にやりと笑いかける。
「ハオが準備してる間に、陰陽の授業をしてあげなサイ」
シャオヘイ・シャオヘイは一歩前へ進み出た。
黒ずくめの衣装が太陽に照らされ、影の中に輪郭を浮かび上がらせる。
「勇者どの。――では、始めましょう」
「勇者どの、まず向こうの旗に描かれたマークを見て下さい」
シャオヘイが顎で示した先には、宿場町の稽古場に掲げられた旗が風に揺れていた。
そこに描かれているのは、黒と白の勾玉が寄り添うように組み合わさった円。
旅の途中、フーロンの至る所で目にした模様だ。
「あぁ、あれか……」
ガイウスは息を整え、旗を見つめる。
シャオヘイは一歩前に進み、まるで師を真似るような落ち着いた口調で言葉を紡いだ。
「勇者どの、フーロンでは“絶対の善”は存在しないとされます」
その声は、広場を取り囲む妖狐や鬼族たちのざわめきを静めていく。
「この国はあらゆる種が混ざり合ってできている。人も妖も魔も、皆が隣にいるのです」
「だからこそ我らは陰と陽、光と影、正と邪……それを切り離さず受け入れてきました」
ガイウスは息を呑む。自分の虹の瞳が光によって色を変えるように・
彼の言葉は真理を映していた。
「この考えを、陰陽(インヤン)と呼びます」
広場に緊張が走る。
師ハオは静かに扇を閉じ、弟子の言葉を誇らしげに見守っていた。
そして群衆の中の誰もが、黒衣の少年が勇者に授けようとしているものが。
単なる拳法ではなく、生き方そのものであることを悟っていた。
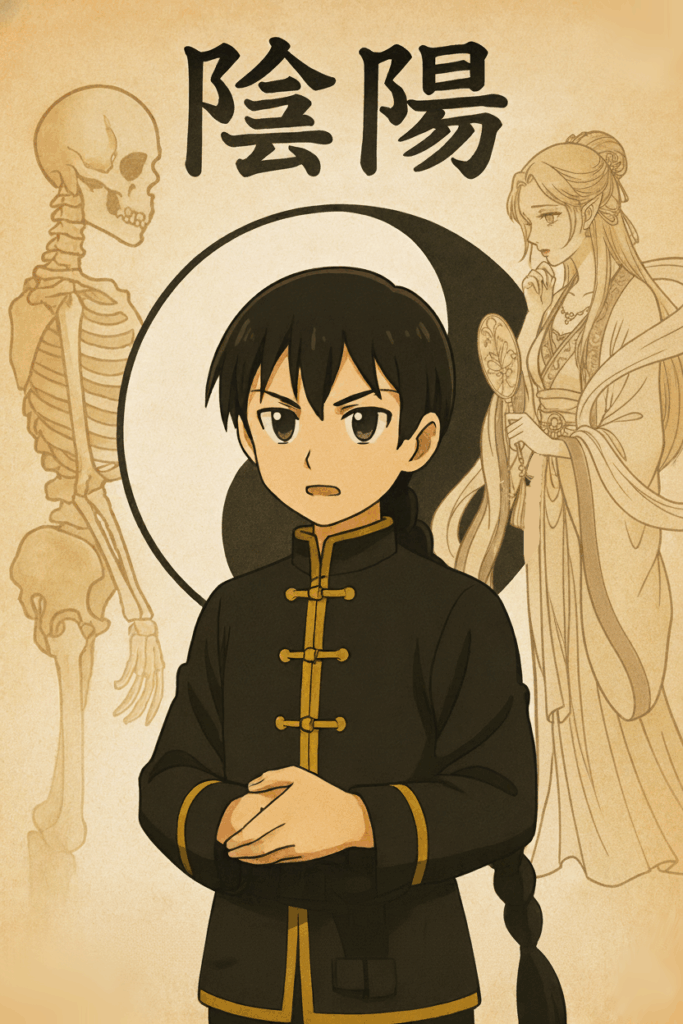
シャオヘイは指先で円を描きながら、静かに言葉を重ねた。
「例えば──天と地」
その手が空を指し、次に足元を指す。
「生と死。どちらか片方なくては、もう片方も存在できぬもの」
その声は決して高ぶらず、まるで山の風が通るように穏やかだった。
「それが、陰陽(イン・ヤン)です」
すっと両足を開き、両の掌を前に差し出す。太極拳の基本姿勢。
「勇者どの、見よう見まねで構えて下さい」
ガイウスは黙って頷き、少年の動きを真似る。
ぎこちない腕の動きに広場から笑いが漏れるが、本人は真剣だ。
シャオヘイは続ける。
「マルス……俺からすれば大師匠にあたる方。その人が何者か詳しくは知りませんが」
声が少しだけ震えていた。それでも言葉を選ぶように続ける。
「あの方はハオ師匠の師であり、シェンタオ大火までは
とても温和で善良な方だったと記録に残されています」
ガイウスの目が細められる。
「しかし今は、歴史に名を刻むため、貴方の国――アルキード王国を戦火で包もうとしている」
静かにうなずくガイウス。
その手のひらが、シャオヘイの姿をなぞるように流れる。
「善も悪も、絶対のものではありません」
シャオヘイは両の手を交差させ、次に円を描くように動かす。
「たがいに存在することで成り立つのです」
拳を握り、呼吸に合わせて言葉を紡ぐ。
「陽虚すれば陰虚、陰虚すれば陽虚し――陽実すれば陰実、陰実すれば陽実する」
難解な言葉に、遠巻きで見守る仲間たちが顔を見合わせた。
ルッツが小声でぼやく。
「……何言ってるかわかんないんだけど!?訳して!」
バルトロメオは首をかしげつつ、口元に笑みを浮かべる。
「う~ん……つまり、バランスが大事ってことかな!?」
広場にざわめきが戻る。
だが、ガイウスだけは静かに目を閉じ、その言葉の奥にあるものを噛み締めていた。
「はい、始めよっか」
ハオが軽く扇を畳み、息を吐く。
「マルスは……見ての通りパワータイプだネ」
その名が口にされた瞬間、ガイウスの眉がわずかに動いた。
かつて「寛寧様(かんねいさま)」と呼んでいたはずの人。
今、師をただ「マルス」とだけ告げた。
――もうあの方は師匠ではない。
たった三文字の中に、ハオの覚悟が詰まっている。
ガイウスはその事実を悟り、ゆっくりと拳を握った。
「あぁ。パワーは六将最強。代わりに搦め手に弱い」
低く答える声に熱がこもる。
「一年前も、搦め手でどうにか勝てたようなもんだったよ」
「そうネ」
ハオは軽く頷いた。
「あんさんはもうフィジカル面は充分に成熟してる。
なら攻めるでなく、受け流す拳法を教えるワ」
そう言って、足を開き、腕を滑らかに回す。
「太極拳って言われる拳法。朝おじいちゃんがやってるやつ、なんて言われるけど……」
微笑みながら続ける。
「奥深い拳ヨ。力に逆らわず、受けて流し、相手の力をそのまま返す。
――あのマルスにこそ通じる道ネ」
ガイウスは黙って構えを取り、目を閉じる。
拳はただ殴るためのものではない。
陰と陽が巡り、力を受けて流し、再び返す。
虹瞳の奥に映るのは、討つべき敵――マルスの姿だった。
ガイウスは深呼吸し、足を開いた。
(フーロン拳法か……ユピテルと戦ったとき。
ちょっと真似してみたが……本格的に学ぶのは初めてだ)
両腕をゆっくりと持ち上げ、円を描くように回す。
力強く振り抜くのではなく、流れるように、波紋を描くように。
その動きは勇者の戦いの型というより。
広場で中年以上の魔族が朝にやっている「健康体操」にしか見えなかった。
ざわ……と周囲の妖狐や鬼族たちが首をかしげる。
ルッツが耐えきれずに突っ込んだ。
「拳法っていうか……健康体操じゃない?」
バルトロメオが腕を組み、真面目な顔で首を振る。
「いやいやルッツ。ゆっくり正確に動くのって、実はすごい技巧いるんだよ?」
「えぇ……?」
勇者ガイウスの虹の瞳は、動きに合わせて静かに揺れていた。
赤の怒りも、青の哀しみも、この瞬間は水面に沈む。
ただ、陰と陽が巡るように――拳は静かに流れを描き始めていた。
ガイウスがようやく太極拳の構えを整えた瞬間、ハオがにやりと笑った。
「それじゃ、稽古行くヨ。ハオが攻撃するネ」
「え!? おい、太極拳ってこっちから攻めるんじゃないのか!」
困惑するガイウスに、横でシャオヘイが真顔で補足する。
「いえ、太極拳は“受け流す拳”。つまり攻撃を敢えて受け止め、流す形式となります」
「なっ……聞いてねぇぞそれ!」
次の瞬間、ハオの掌打が真っ直ぐに飛んできた。
「うわわ!ハオ、俺まだ準備――いてええええ!!」
ガイウスの体が見事に吹っ飛び、石畳に尻餅をつく。
遠巻きで見ていたバルトロメオが眉をひそめる。
「あれで習得できるかな……」
ルッツは腕を組み、冷ややかに言い放った。
「大龍祭まであと数週間よ、キズ野郎……しっかりして」
「うるさい!! カウンター戦法なんか初めてなんだ俺は!」
悶絶しながら立ち上がるガイウスの姿に。
広場の妖狐や鬼族の観客から笑いと拍手が起こった。
稽古はまだ始まったばかり――だが勇者の汗は、確かに陰陽の理へと染み込んでいった。
掌を受け流す――その動きを何度も試みるが。
ガイウスの体はぎこちなく、ただ打撃を食らうばかりだった。
「……くそ、やっぱ難しいな……」
額から汗を伝わせながら、彼はふっと過去を思い出す。
(カウンターといえば――あいつだ)
1年前の死闘。
闇に溶けるように立つ、マスターアサシンの影。
腰を落とし、掌をこちらへ見せるように構える――あの鉄壁のポーズ。
ガイウスは息を呑む。
「あのマスターアサシン(プルト)の鉄壁モードみてぇなもんか……」
皮肉混じりに笑いながらも、視線は真剣だ。
「……あれを真似しろとか、無茶ぶりすぎんだろ」
彼の脳裏に蘇るのは、プルトが攻撃を跳ね返した瞬間。
刃を受け、力を流し、そして倍返しにしたあの冷徹な動き。
ゆっくりと構え直し、ガイウスは掌を前に掲げる。
「えーと……あいつは、跳ね返す時どうしてたっけ……」
答えはまだ曖昧だ。
だが確かに、自分の体は陰と陽の間で揺れ始めていた。
ガイウスは額の汗を拭い、改めて深く腰を落とした。
掌をこちらに向け、半身を切る――プルトが見せたあの鉄壁のポーズ。
「……なんで、あいつがこの構えになるのか……」
息を整えながら姿勢を維持する。
両手は常に攻防に転じられる位置にあり、どこから打ち込まれても反応できる。
実際に取ってみて初めて、体にその理屈が落ちてくる。
「なるほど……この構え、強い」
自分でも驚くほど、攻防一体の安定感があった。
「どんな攻撃に対しても反応できる……」
一瞬の感嘆の後、顔が引きつる。
「……いや、だがムカつく……!」
結局“プルトのやり方”に納得させられたこと自体が癪に障る。
観客の妖狐や鬼族が「おお、形になってきたぞ」とざわめく中。
勇者は複雑な顔のまま構えを解かなかった。
ハオの掌打が正面から迫る。
ガイウスは腰を落とし、掌を前に掲げた――例の、プルトの鉄壁ポーズ。
次の瞬間、打撃は彼の腕を伝って横へと流れ、地面に抜けていった。
「……っ!」
重圧が抜け、空気が震える。
「おぉ!受け流したぞ!」
鬼族の野次馬が声を張り上げる。
「赤毛のにーちゃん、かっこいい~!」
妖狐の娘たちが手を叩き、黄色い歓声を上げた。
ガイウスは驚愕と興奮を抑えきれず、思わず拳を握りしめる。
ハオがにっこりと頷いた。
「お見事! あんさんの構えのベースは決まったネ」
「ああ……」
ガイウスは息を吐き、笑うでもなく苦い顔をする。
「……あのアサシンがベースってのが気に入らんが、この構えが一番安定するわ」
広場に笑いと喝采が響く。
勇者はようやく、太極拳という新たな道の第一歩を踏み出したのだった。
「よろしい。じゃ、次は実戦形式でいくヨ」
ハオが軽やかに身を翻す。
その笑みは穏やかだが、放たれる気配は鋭い刃のようだった。
広場に緊張が走る。
バルトロメオが肩をすくめ、ぽつりと呟く。
「こりゃ……夕方まで続きそうだね」
そんな中、シャオヘイが一歩前に出る。
「では、お二方は俺が稽古をつけます。こちらへ」
黒ずくめの少年がまっすぐに手招きする。
ルッツは大げさにため息をつきながらも近づいた。
「はいは~い。あんま痛くしないでよね、シャオ」
軽口に混じるほんのりした緊張感。
ガイウスとハオの構え、ルッツとバルトロメオの歩み。
広場は二つの修行場へと変わり、それぞれの汗と声が交錯していった。