砂嵐の音も届かない、静かな水辺。
サタヌスは、一人、岩陰にうずくまっていた。
呼吸が浅い。胸の奥がまだ焼けるように痛む。
脳裏に焼き付いたあの映像が、勝手に繰り返されていた。
ぐちゃぐちゃのままサタヌスは顔を上げ、無言で水の中に頭を突っ込む。
冷たい水が全身に弾け、服が重く貼りつく。
大嫌いな感覚だった。
いつもは水が跳ねるだけで、オールバックが崩れるだけで。
「クソッ、台無しじゃねぇか!」と怒鳴っていた。
けど今は—。
髪が崩れたまま、水を浴び続ける。
額の真ん中に髪が張りついた。
濡れた前髪が、だらしなく下りる。
鏡があれば、自分の顔が“子ども”に戻っていることがわかるだろう。
自信家で、口が悪くて、喧嘩っ早くて。
そんな“勇者サタヌス”じゃなく—ただの、何も知らなかったガキの顔。
「……何も、知らなかったのに」
レアがどんな気持ちで娼婦をやっていたかも。
自分がどうやって生まれたのかも。
父親が、どんな奴だったのかも。
「知らねぇままで、よかったのによ……」
声が震えた。
水面に落ちた雫は、水か、涙か、誰にもわからなかった。
水の音だけが、静かに耳に残っていた。
地面に膝をつき、サタヌスはただ、泣いていた。
誰もいない。
見ているのは、星と、咲きすぎた花と、冷えた空気だけだった。
「……そうだよな」
かすれた声が、喉からこぼれる。
「捨てちまうよな、レア……」
笑い声のような、泣き声のような。
わからない何かが喉を揺らす。
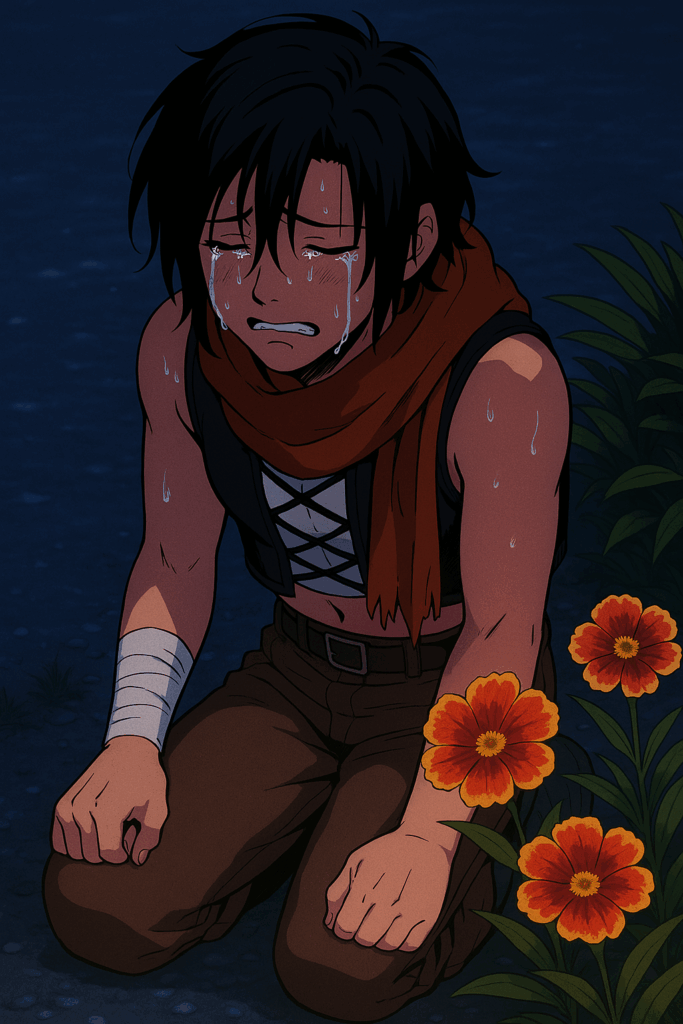
「……俺が、あいつに似すぎてるからさ……。……気持ち悪いよな。だって……俺、笑うと……」
そこまで言って、また息が詰まる。
何度も手で顔を拭っても、水は止まらなかった。
それが涙なのか、水なのか、もうどうでもよかった。
ただ、花が綺麗だった。
それだけが、やけにくっきりと視界に映っていた。
気配に気づいたのは、すぐ隣に体温を感じたときだった。
サタヌスが顔を上げると、ヴィヌスが無言で隣に座っていた。
いつものように「なに泣いてんのよ」なんて言わなかった。
その目は、ただ夜を見つめていた。
「……レア、俺が嫌いだったのかな」
誤魔化しも、照れもなかった。
それを口に出すだけで、ひどく苦しかった。
ヴィヌスは一度だけ瞬きをしてから。
やわらかく、でも確かに首を横に振った。
「……わからないわ」
それは、突き放しでも、曖昧でもなかった。
彼女にできる“誠実な答え”だった。
「でも、あんたのことをちゃんと見ようとしなかったのは……確かよ」
サタヌスは何も返さなかった。
ただまた視線を落として、静かに息を吐いた。
花はまだ、綺麗に咲いていた。
しばらくの間、ふたりとも何も言わずに月を見ていた。
空に浮かぶのは、細く鋭い三日月。
どこか自分たちと似たように、不完全で、だけど綺麗だった。
不意に、サタヌスが口を開いた。
「なぁ……俺、ティータって言われても、いまいちピンとこねぇんだよ」
声は掠れていたけれど、もう涙は落ちていなかった。
ただ月を見ながら、独り言みたいに続ける。
「俺にとっちゃ、父親って……“ボス”だからさ」
ヴィヌスは横目で彼を見た。
サタヌスは口元だけで笑う。
「スリ失敗すると頭どつかれるし、メシ代は自分で稼げって言うしさ。
でも─ティータなんかより、ずっと……」
そこで言葉が切れた。
何をどう言っても、本当の父親じゃないってことが付きまとってきた。
でも、少なくともその人は“怖くても、ちゃんと隣にいた”。
風がまたひと吹き、砂の匂いを運んできた。
その気配と一緒に、もうひとつの足音が近づいてきた。
「……よ」
サタヌスが顔を上げると、ガイウスがすぐ隣に座っていた。
何も言わずに、自分のマントを半分ほどサタヌスにかぶせる。
「……勝手に乱入してんじゃねぇよ」
サタヌスが鼻をすすって小さく文句を言うと。
ガイウスはそれには応えず、ぽつりと呟いた。
「確かに……女に乱暴して、ヤリ逃げかますようなやつが父親なんて、嫌だよな」
言葉は荒かった。
でもそれは、サタヌスが口に出せなかった代わりの怒りだった。
「……っ」
サタヌスの喉が、きゅっと鳴った。
でももう、泣いてはいなかった。
マントに包まれて、両隣に誰かがいるこの場所だけが、いまの自分を支えてくれていた。
マントの中で、サタヌスの呼吸は少しずつ整っていった。
誰も急かさなかったし、余計なことも言わなかった。
─と、その沈黙を破ったのは、ヴィヌスだった。
「……そういえばさ、賢者に“魔王軍の駐屯地探してもらう”って話、どうなったの?」
「──あ」
ガイウスの目が開かれる。
「……あ゛ッ!!」
サタヌスがガバッと立ち上がる。
そして三人そろって、同時に叫んだ。
「そうだ!!!」
ひゅっと風が吹き抜ける。
誰もいない砂漠の夜に、やたら勢いのいい声だけが響いた。
「いやおまえら、こんだけ時間あってなんで忘れてんだよ!!!」
「だって空気が空気だったじゃない!!」
「ちげーねぇけど!!」
三人がオアシスの小道を走って戻ってくると。
その先にある石造りの家の壁にもたれかかる影が見えた。
オリオンだった。
すでに屋外に出ていたらしく、月明かりの下で、静かに腕を組んで立っている。
「……なんで外にいんだよ」
サタヌスが息を切らせながら問いかけると、オリオンはふっと笑った。
「昔から、星の子は忙しないからな」
「……星の子?」
ヴィヌスが眉をひそめる。
「勇者というやつは、どの時代も落ち着きがないのだよ。
思い立ったら走る。何か忘れてたら叫ぶ。急に泣いて、急に笑う」
「うっ……反論できねぇ……」
サタヌスが思わず目を逸らす。
「“ああ、またか”と思って、外に出て待っていたわけだ」
「……やっぱあんた、怖いくらいに千年生きてんな」
ガイウスが肩で息をしながら、苦笑交じりに呟いた。
「で、魔王軍の駐屯地って結局どこなのよ?」
ヴィヌスがずいと一歩前に出ると、オリオンは何も言わず、懐から古い地図を取り出した。
「ここだ」
彼が指さしたのは、何も描かれていない、ただの砂のエリア。
「……おい、ここ、見張り台からも見えなかっただろ」
サタヌスが眉をひそめる。
「何もなかった」
ガイウスも地図を覗き込んで、静かに言った。
「─では、こうしてはどうかな」
オリオンが、指を地図にかざし、ぽつりと呟いた。
「……アブラカタブラ」
音も、光もなかった。
ヴィヌスがジト目で地図とオリオンを交互に見つめる。
「アブラカタブラって……手品師がいうやつじゃないの?本当に“呪文”なの?」
オリオンは静かに頷く。
「それだけ由緒ある呪文ということだ」
「魔法というものは、長く使われた呪文ほど効力が増す」
「人の言葉と想念が積み重なれば、幻惑くらい打ち消すのは造作もない」
魔法の性質である。
魔法は「古いもの」ほど効力が増す、と言われている。
人々に繰り返し使われ、信じられてきた呪文ほど。
世界のマナに馴染み、誰でも使いやすくなっていくのだ。
火炎魔法“メギ”が冒険者の友として親しまれているのも、この性質に起因している。
ヴィヌスが「つまり“ベタ”な呪文ほど強いってことね……」と。
小声でぼやいた直後、地図が─変わった。
そこには、さっきまで何もなかった場所にだけ、黒い印が浮かんでいた。
地図の上に浮かび上がったその模様─。
それは、逆さまの五芒星の中央に、鋭い1つ目が描かれていた。
「……なにこのマーク、禍々しすぎない?」
ヴィヌスが思わず声を漏らす。
「─あ」
サタヌスが顔をしかめた。
「これ……見たぞ。あの眼帯野郎……ティータのベレーに、同じ模様があった」
「……ってことは、あいつ」
ガイウスが静かに言葉を続ける。
「魔王軍の幹部で間違いないってわけか」
「ていうか軍服じゃなくて“制服”だったんかい……」
サタヌスがツッコむも、冗談にならない空気があった。
地図の上で、魔王軍の印はうっすらと脈動するように揺れていた。
まるで、こちらの視線を感じているかのように─。
「視えなかったんじゃない。“視えないようにされていた”ってことかよ」
サタヌスが呟く。
「それを……どうしてお前にだけ視えるんだ」
ガイウスの目が鋭く細められる。
オリオンはゆっくりと、何百年も生きてきた目で三人を見返した。
“私のことを知恵袋と思っていただろう”そう言わんばかりに。
「奴らは数が多い。正面から挑むのは得策でない、これを使え」
オリオンの手によって魔王軍制服のレプリカが用意され。
一行はすぐさま装備チェックと着替えに入った。
「……うわ、なにこの帽子、絶対似合わない」
ヴィヌスがベレー帽を手に取り、ため息混じりに被ってみる。
「……やっぱり似合わない」
「いやそこ2回言う!?」
ガイウスはジャケットを着込みながら、胸元を押さえて小声で唸った。
「なぁ……2XLサイズってないのか。胸、ちょっとキツい」
「えっ……そこ? いや、てか2XLの概念あんのこの世界」
サタヌスが引き気味に突っ込む。
そして彼自身はというと、袖を通した瞬間─。
「……なぜか、肌になじむぜ」
「こっわ!?」
ヴィヌスとガイウスが同時に引いた。