桜花の町並みを抜けた先に、小さな暖簾が揺れていた。
「手打ちそば」と墨で書かれた木の札。
古民家風の小さな店――かつて参拝客で賑わった頃の名残だけを、静かに残している。
「いらっしゃい」
店に入ると、囲炉裏の煙と一緒に、年老いた女の柔らかな声が迎えてくれた。
皺だらけの手で湯呑みを置きながら、彼女は微笑む。
「私は雫宮ぼっちゃまの世話人みたいなものさね。
ぼっちゃまから話は聞いているよ。さ、ゆっくりしてきなさい」
店内には木の匂いが満ちていた。
壁に貼られたメニューは、かすれた墨字で漢字とひらがなが並んでいる。
ハオが身を乗り出して、指先で追いながら解説してくれた。
「フーロン語とヒノエ語、似てるけど微妙に違うのヨ」
「でも大体、おんなじ意味。文脈で掴めるネ」
ルッツは唇を尖らせながらメニューを覗き込む。
「“天ぷら”と“かき揚げ”ってどう違うの? え、揚げ具合?」
「そんなもんかもネ」
ハオが笑い、店の中に小さな笑い声が広がった。
注文を終えると、ほどなくして湯気が立ち上る。
出汁の香りがふわりと漂い、冷えた体にじんわりと沁みていく。
バルトがやや困り顔で首をかしげた。
「ねぇガイ君、勇者って蕎麦食うの?」
ガイウスは真剣な顔で箸を持ったまま固まる。
「……そういえば食べたことねぇな」
ハオがぱあっと笑顔を浮かべる。
「いいネ! 初めての蕎麦、縁起が良いヨ!」
「うまいよこれ」
ルッツは口をもぐもぐさせながら笑った。
「この揚げてあるやつ、好き。サクサクしてる」
かき揚げを箸で摘み上げるその仕草は。
この亡霊の国の中で、あまりに“生きている”動作だった。
老婆は嬉しそうに頷き、湯飲みに新しいお茶を注ぎながら言う。
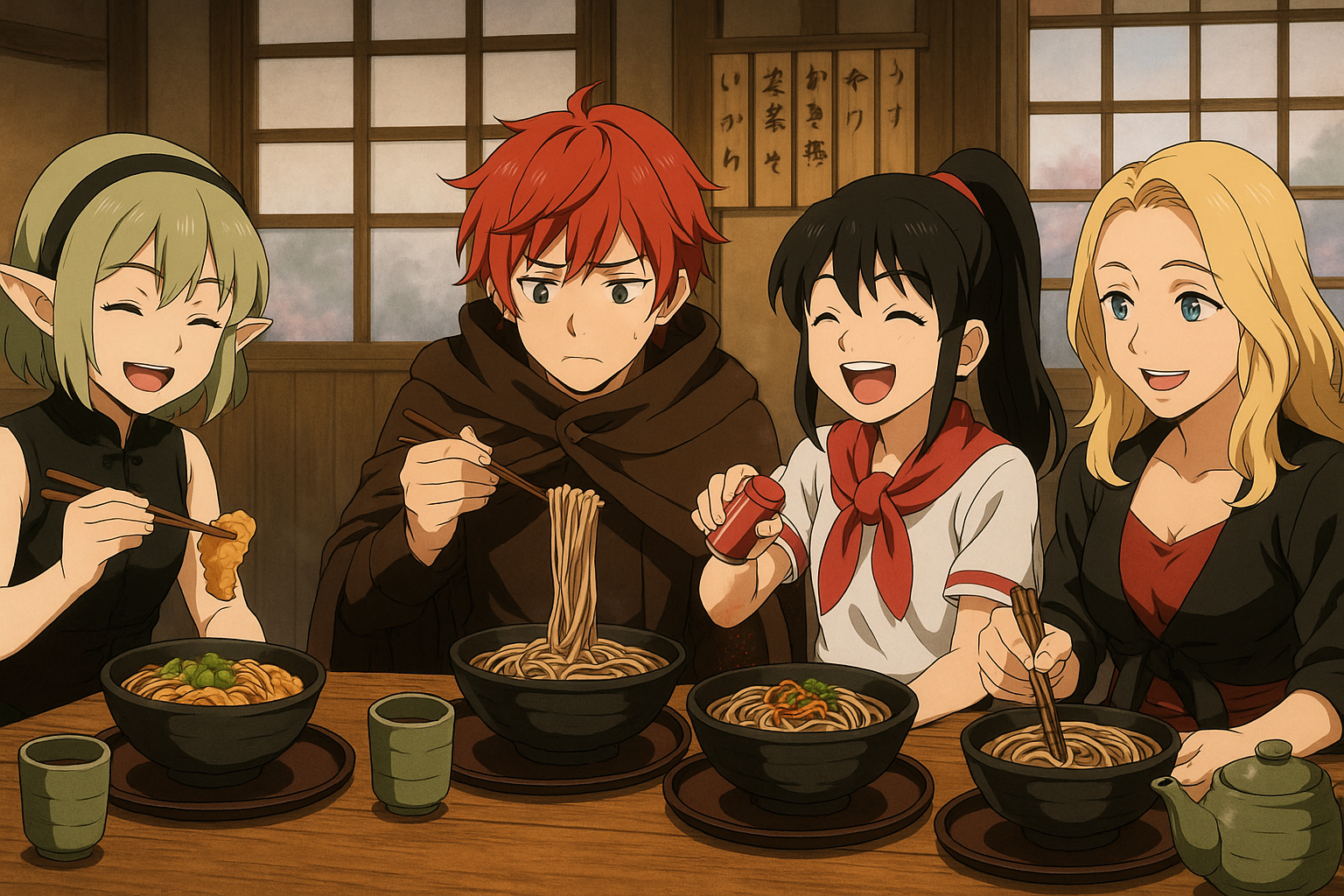
「おや、通だねぇ。それは清さんの大好物だよ」
「清さん?」
ルッツが首を傾げる。
「十五代目神楽王、清宮様だよ」
「大政奉還してからは、政を帝に譲ったのさ。
あの方はねぇ……こんな山菜や、揚げ玉のひとつを“うまい”って本気で言える人だったのよ」
湯気の向こうで、老婆の目が懐かしそうに細められる。
その語りは、春の夢のように柔らかく、どこか哀しかった。
ガイウスは湯呑みを手に取りながら、小さく呟いた。
「……いいな。そういうの」
雨の国の片隅で、束の間だけ“生者の匂い”が戻ってきたようだった。
湯気が少し落ち着いた頃、ふと、バルトロメオが口を開いた。
「おばあさんは聞いてる? ……丙は、地図から消えるって」
その声は、さっきまでの柔らかい笑い声とは違って、どこか遠い響きをしていた。
老婆は手を止めて、しばらく黙っていた。
やがて、しわくちゃの手で湯呑みを持ち上げながら、静かに微笑む。
「あぁ、聞いてるよ。……だからみんな、この味を残そうって努力してるんだよ」
言葉には、かすかな揺れがあった。
「幸いねぇ、“丙ふぁん”ってのはソラル大陸にたくさんいてねぇ。
ありがたいことだよ、まったく」
その“ふぁん”という発音が、妙にあたたかく響いた。
ルッツは箸を止め、ゆっくりと顔を上げる。
「国が消えても、文化を語り継ごうって人がたくさんいる……」
ぽつりと呟いたその声には、幼いけれど確かな敬意があった。
「……うん、いいね。なんか、救われる気がする」
ガイウスは何も言わず、ただ湯気の向こうを見ていた。
器の中の蕎麦が、ゆらりと揺れる。
滅びゆく国の味――それを噛みしめるように、静かに箸を動かした。
外では、霧とともに桜の花びらが散っていた。
それはまるで、滅びを受け入れる国の祈りのように。
蕎麦屋を出て、代金を払うと、街には再び霧が降りていた。
それでも、先ほどまでとは違っている。
雫宮に“お祓い”されたおかげか、浮遊霊たちは一行に気づくことなく、
ただふよふよと、夢の中のように漂っているだけだった。
「……いいネ、今のうちに見て回ろ」
ハオが言うと、バルトロメオが手を叩いた。
「あ、そうだガイ君。せっかくだからさ、刀見ていこうよ。
僕、一度生で見たかったんだ」
「刀?」
ガイウスが首を傾げる。
「あのユピテルが持ってた剣の名前だよ」
「あぁ! あれか!」
ガイウスが目を丸くする。
「なんか冒険者が言うもんな……“刀が欲しい”って。よし、見に行こう!」
霧の合間を縫うように、四人はオウカの市街を歩いた。
瓦屋根の家々は傾き、道端の露店は半ば崩れたまま放置されている。
それでもどこか、美しかった。
時が止まったままの街に、桜の花びらが淡く舞う。
やがて、古道具屋のような小さな店に辿り着いた。
木の看板には、掠れた文字で「打刃物」と刻まれている。
「……ここ、まだやってるんだ」
ルッツが小声で言う。
中に入ると、鉄と油の匂いが鼻をついた。
壁には刀が数本、無造作に掛けられている。
そのうちの一本に、ガイウスが目を止めた。
「……この細くて反った刃。丙にしかないタイプか?」
興味深げに指先で鞘をなぞる。
店主は苦笑いを浮かべた。
「昔は良いもんもあったんだがね。今は二級品ばかりさ。流し斬りなんて夢のまた夢だよ」
ガイウスが刀を持ち上げ、光にかざしたその時、
店の隅から低い声がした。
「……見たって無駄だ」
振り向くと、薄く白髪の混じったベテラン冒険者風の男が座っていた。
酒焼けした声が、鉄の響きを帯びていた。
「どれも鈍らだ。“流水”ひとつ切れやしねぇ」
ガイウスが眉をひそめると、男はくぐもった笑いを漏らした。
「だがな……粗悪品でも、刀を見たがる奴は多いんだ」
「ソラルじゃ、刀を持ってるだけで誇れる代物だからなぁ」
火のついていない煙草を唇にくわえ、ぼんやりと天井を見上げる。
「勇者さまには心証よくねぇかもしれないが――」
男はちらりとガイウスを見た。
「ユピテルって悪魔、人気あったんだぜ」
ガイウスの手が止まる。
「……なんでだ?」
「なにせ、“刀”を間近で見せてくれる存在だったんだからな」
笑っているのか泣いているのか分からない声。
「魔王軍の筆頭が、俺たちの“憧れ”を背負ってたんだよ。皮肉な話だろ?」
ハオが腕を組み、静かに頷いた。
「わかるヨ。誰も知らない“文化の化身”だったんダネ」
「それが、“滅びの象徴”として残るの、悲しいな」ルッツが小さく呟く。
ガイウスは黙って刀を鞘に戻した。
刃が擦れる金属音が、やけに澄んで聞こえた。
「俺ぁ冒険者やって五十年になるがな、
このソラル大陸で“最も斬れる剣”といやぁ――厳龍の刀しかねぇぜ」
「ゲンリュウ……?」
「オゥ、“厳しい龍”と書いてゲンリュウ。渋い名前ネ」
ハオが感心したように頷く。
ベテランは懐かしげに天井を見上げ、
「流れる水から、竜の鱗まで切り裂くってな。
あれを手にした瞬間、どんな戦場でも主役になれる。
……大陸中の憧れだったんだよ」
ルッツが小さく息を飲んだ。
「……その、厳龍って人、どうなったの?」
男は苦く笑い、煙草に火をつけた。
「さあな。だが噂じゃ――何がトチ狂ったのか、魔王軍の大幹部に刀を打ったって話だ」
店の空気が、一瞬で張り詰める。
「で、そのせいで帝に睨まれて……打ち首。
遺された刀は、“雷神を刀にしたような代物だった”そうだよ。知らねぇけどな」
「雷様みたいな刀ねぇ……」
バルトロメオが感心したように呟く。
「ガイウス君、僕たち、それ倒してきたね?」
ガイウスが腕を組み、少しだけ目を細めた。
「……ああ。ユピテルだ」
ハオは指先で刀をくるりと回して見せ、
「ねぇ、店主さん。日本刀って――2セットで1つなのヨネ?」
店主が感心して頷く。
「鋭いね。そう、“打刀”と“脇差し”を組み合わせるのが基本。
両方揃って“大小”ってわけさ。昔はそれが武士の証だったんだ」
「……じゃあ、厳龍はもう一つ作っていた?」
ガイウスが低く呟く。
バルトロメオは楽しげに笑った。
「雷様の弟刀(おとうとがたな)か。浪漫だねぇ」
笑い声が店の中に響く。
けれど、その笑いの裏で――ガイウスの胸の奥に、何かがざわめいた。
刀屋を出たあと、ガイウスはしばらく言葉を失っていた。
霧の街を歩く音だけが、やけに響く。
さっきの老冒険者の言葉が、何度も頭の中で反芻されていた。
「ユピテルって悪魔……人気あったんだぜ」
「なにせ“刀”を間近で見せてくれる存在だったんだからな」
信じられなかった。
だが、妙に納得もしていた。
彼の放つ一閃。
雷光を纏い、空を裂くその姿を、今でもまぶたの裏に焼きついている。
あれを見た者は、恐怖を通り越して――“美しい”と思ってしまう。
「……恐怖であり、カリスマか」
つぶやいた声は、桜の霧に溶けていく。
ユピテルは確かに外道だった。
血と狂気を愛し、あらゆる倫理を踏み越えて笑っていた。
それでも――彼には“力”があった。
誰もが惹かれずにはいられない、壊れた光のような輝き。
もし、あれが“神”を気取った悪魔だったとしても。
人々は、その神を讃えずにはいられなかったのかもしれない。
「俺は神に等しき存在」
「神を讃えるのは当然のことだろぉ?」
――あの声が、耳の奥でよみがえる。
傲慢という罪が、確かにそこに生きていた。
だが今なら、ほんの少しだけ理解できる気がした。
あれは“恐怖”だけではなく、“祈り”だったのだ。
滅びゆく文化を抱えたまま、戦場に立つ誰かの。
ガイウスは足を止め、空を見上げた。
曇天の向こうで、桜の花弁が風に舞う。
まるでユピテルの雷光が、今もこの国のどこかに残っているように。
厳龍。
雷神刀「舞雷」を打ったという伝説の刀鍛冶。
その名を脳裏に刻みつつ、一行は導かれるようにして辿り着いた。
――夢幻桜。
樹齢千年を超えるという大樹。
その花は一年を通して散ることがない。
霧の中に霞む花びらが、まるで夜空の星のように静かに輝いていた。

「“むげん”って、“無限”と同じ読みだネ」
ハオが呟く。
「だから、ここで告白すると縁が切れないって言われてるヨ」
バルトロメオが笑いながら頷いた。
「ロマンチックな都市伝説じゃん。幽霊都市にしては粋な話だね」
けれど、その足元には無数の墓石が並んでいた。
夢幻桜は、国を見守るように墓地の中心に立っている。
その根元、ひとつだけ手入れの行き届いた墓があった。
「十五代神楽王・清宮」
神楽の国を静かに閉じ、政を譲り、剣を捨てた男の眠る場所。
風が吹くたび、墓前の花が静かに揺れる。
ルッツが膝をつき、手を合わせた。
「この人が……この国を守って、終わらせたんだ」
バルトロメオは腕を組み、少し考えてから口を開いた。
「“強い王”じゃなくて、“譲れる王”ってのがすげーよな……」
その言葉に、誰もすぐには続けなかった。
ただ、ガイウスが一歩引いて、静かに頭を下げた。
風がざわめき、夢幻桜の花びらが逆巻く。
その中に、一瞬だけ“気配”があった。
姿は見えない。
だが確かに――誰かが、そこにいる。
「……ありがとな」
ガイウスが誰にともなく呟いた。
風がそれに応えるように吹き抜け、花びらが一枚、ゆっくりと彼の肩に落ちた。
それはまるで、亡き王が“旅路の行く末を見守っている”かのようだった。