夜霧の中、静かな水面に舟が一艘浮かんでいた。
木造の小舟。灯りはなく、ただ灰色の水を押し分けるようにゆっくりと揺れている。
その舳先に、古びた笠をかぶった男がいた。
目は見えず、顔も半ば影に沈んでいる。
低い声が霧を裂いた。
「……神楽に渡るのか」
「ああ。あんたが最後の船か?」
ガイウスが言う。
男は少しだけ笑ったように肩を揺らした。
「……最後ではない。向こうから、まだ帰ってきておらんだけだ」
「や、やめて!? 帰ってきてないって何!?どっから帰ってきてないの!? 現世から!?」
ルッツが即座に叫ぶ。
「……行こうぜ。話してる間に引き返したくなる」
ガイウスが小さく息を吐くと、船頭が櫂を押した。
霧が動き、船が音もなく進み出す。
水の音が、鼓動のように規則正しく響いた。
「泳いでいくのはやめておけ」
船頭の声が、ぼそりと響く。
「このお堀は泳げないよ」
「え?」
ガイウスが眉をひそめる。
ハオが欄干に身を乗り出して、覗き込んだ。
「あ、見えたヨ〜白い手、水の中でパタパタしてる」
「鯉みたいなノリで話すな!!!」
ガイウスが一喝する。
船頭は笑ったのか、わずかに肩が揺れた。
舟は霧の海を滑るように進む。
空も水も灰色で、世界に境目がない。
「丙って、この大陸で一番美しい国だったんだよな」
ガイウスが呟く。
その声はどこか遠く、記憶をたどるようだった。
「ヴィヌスが見たら泣くぜ。こんな怨霊だらけの国なんてよ」
バルトロメオが笑って肩をすくめる。
「まぁまぁ、僕は好きだよ? 詫び寂び♪ ってやつでしょ?」
ハオは目を細めて、霧の奥を見つめた。
「うむ〜,美醜也是一念間ネ〜」
(美しいか醜いかは、心次第ヨ)
ルッツが黙って船の端に寄り、霧の向こうを見つめた。
どこまで行っても、音も光も、帰り道もない。
それでも、彼らは笑いながら進んでいた。
まるで死の国すら、“旅の途中”の風景に見えていた。
石畳の坂道を上る四人の背中。
霧に沈む巨大な城郭は、江戸城の直線的な大手門でも、華美な金装飾でもなかった。
彼らの眼前にそびえていたのは、
白壁に重なる何層もの屋根、遠く東北の地で“難攻不落”と謳われた城――
苔むした石垣は曲線を描き、戦いの痕跡を残すかのように、剣がいくつも突き立てられている。
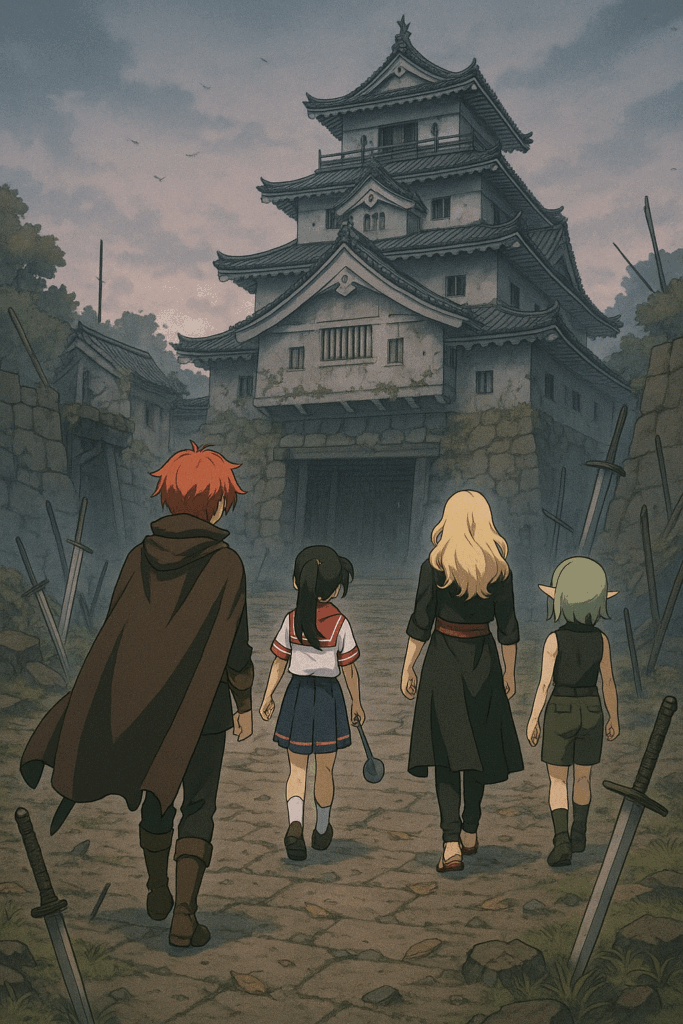
“観光名所”ではなく、滅びと記憶が層をなした“亡国の城”そのものだった。
桜と石垣、鋼鉄の門――どこを見ても、ただの観光地には収まらない重みがあった。
この城は、かつて「難攻不落」と讃えられた。
何度も外敵を退け、百の軍勢すら寄せ付けなかった鉄壁の砦。
その堅牢さも、城主たちの誇りだった。
バルトロメオが静かに呟く。
「難攻不落のお城でも、魔王軍には勝てなかったんだね……」
城壁を見上げる目が、どこか複雑そうだった。
ガイウスが肩を竦めて答える。
「改めて思うわ。……その魔王軍に匙投げさせるとか、フーロン、改めてヤバイな……」
苦笑しながらも、あの“混沌”に正面から挑む蛮勇に戦慄すら覚える。
ハオはさらりとお茶をすすり、
「魔王軍は混沌。秩序で対抗しようとすればするほど負けるヨ」
「逆に言えば、それ以上の混沌には勝てないネ」
柔らかい声で告げるその言葉は、妙に現実味があった。
石垣の冷たさが、滅びた国の記憶を今も残している。
“難攻不落”という誇りさえ、一瞬で塗り替えた混沌。
この場にいる全員が、改めて――“魔王軍”という存在の規格外さを痛感していた。
「ねぇやめてほんとやめて帰ろう??絶対なんかいるよ!?これ絶対いるでしょ!?ねぇ!?」
ルッツが超早口でまくしたてる、その声が霧に吸い込まれていく。
ガイウスは眉をしかめ、半歩前に出た。
「歓迎されてんの……? 俺たちほんとに。
“ようこそ”の雰囲気が、生首サイズで襲ってきそうだぞ」
「鍵は開いてるね……おじゃまします」
バルトロメオが静かに十字を切る。
この人だけ異様に冷静、むしろテンションが上がってる。
ハオが扉に掌を当てて、首を傾げる。
「門が“向こうから開けたい”って言ってるネ」
バキィ、と金具の音が鳴った。
門が、内側から少しだけ開いた。
「きゃああああああああああ!!!」
ルッツがさらに一段階上の悲鳴を上げる。
その直後、霧の中から声がした。
低くも明るい、妙に人懐っこい声。
「おや? なぜ南蛮人がいるで御座る?」
「ありゃ?オバケじゃな……」
ガイウスが振り返る間もなく――
「よくぞ参られた」
目の前に現れた忍者の姿が、まるで舞台のトリックのように鮮烈だった。
笑顔のまま、胸から腰にかけて袈裟斬りの痕。
「ぴゃあああああああああ!!」
ルッツの悲鳴が門前に響く。
バルトロメオは微笑んで呟いた。
「こういう演出、舞台じゃ難しいんだよね〜……」
覆面はしておらず、表情がよく見える。
くたびれた黒装束は胸元から裂け、袈裟斬りの痕が大きく走っている。
手首には、誰かにもらったらしい紐のお守りが揺れた。
それでも、彼は笑っていた。
人懐っこく、どこか照れくさそうに。
「この城に用のあるお方とお見受けするが……まぁ、気を楽に」
「……気を楽に、ってあんた、胸開いてるけど!?」
ルッツの叫びが即座に飛ぶ。
「ははっ、これくらいの傷では死ねませぬゆえ!」
「いや死んでるだろ!!」
ガイウスが叫んだ。
門の向こう、霧の奥に“歓迎の間”の光がぼんやりと灯っている。
その光の色は――暖かいようで、どこか悲しいほど白かった。
門を抜け、薄暗い回廊を歩く。
霧の白が壁を染め、遠くから太鼓のような音がかすかに響いていた。
ガイウスが歩きながら振り返る。
「で、あんたさ……名前は?」
黒装束の忍者は立ち止まり、にこりと笑った。
「忍びは名乗らぬものでござる」
「えー、でも呼びにくいよ~」
ルッツが眉をしかめる。
「じゃあ“袈裟さん”でいいよね?」
「見た目通りって感じでいいかも~」
バルトロメオが軽く笑う。
「胸のあたり、インパクト強いしね」
「バルト!!」
ルッツが肘で小突く。
忍者は一瞬きょとんとしたが、すぐに柔らかく笑った。
「ふふ、それで構わぬ。……呼ばれるのも、少し懐かしいでござるな」
彼の視線が、一瞬だけ遠くを見た。
霧の向こうに、滅びた城の影が浮かんでいる。
その目は、もう生きた者のそれではなかった。
けれど確かに、“名前を呼ばれる”ことを喜ぶ、人間の温度があった。
ハオが微笑む。
「“袈裟さん”、ヨロシク~」
「うむ、任せておくでござるよ」
忍者――袈裟さんは、胸の裂け目を気にも留めずに、軽やかに先を歩いた。
その背中を見ながら、ルッツが小声で言った。
「……ねぇ、いい人だね」
ガイウスが頷く。
「“いい人”なのに、死んでるってのがこの国らしいけどな」
薄明かりの中、袈裟は先頭を歩く。
姿勢は正しく、声は穏やか。
その佇まいだけで、かつて仕えていた主への敬意が伝わる。
「正嗣殿は──日向正嗣さまは、まこと武門の誉れ。
誰もが認める、気骨と礼節を備えたお方でござった」
淡々と語る口調に、誇りが滲む。
だが、次の言葉の前で、わずかに目を伏せた。
「……されど、同時に、ちと……厳しすぎる方であってな」
静かな間。
霧の向こうから、遠い鼓の音がかすかに響く。
「何度も怒鳴っておられたよ。
“それでも武士の子か”“涙を見せるな”“我が跡を継ぐ者の面をせぬ”……と」
袈裟の声は、どこか哀しげだった。
「拙者はそれを遠くから見ておった。
あの御仁の背中には、常に“血の筋”が走っておったのだ。
怒りではなく、……悲しみに似たものでな」
誰も言葉を挟まない。
霧の外で花びらが散る音だけが、僅かに響いた。
その空気を破ったのは、袈裟本人だった。
いつもの調子に戻り、穏やかな笑顔で立ち上がる。
「さて、この部屋は元は侍女の控えの間で──おっと、段差にご注意。
拙者はもう足がありませんので、つい見落としましてな」
「ハッハハハ! それおもしろいネ~! “足がない”~!」
ハオが腹を抱えて笑う。
「笑うとこか!?」
ガイウスが即座に突っ込む。
バルトロメオは苦笑しながら言った。
「おばけって思えないくらい親しみ出てきたね……」
「ははっ、それは光栄にござる」
袈裟は軽やかに扉の前へ向かう。
「──あ、そこ開けますと拙者の死に様その2が見えます」
「死にざまってカウントできんの!?」
ガイウスが思わず叫んだ。
ルッツが絶句し、ハオはまだ笑い続けている。
その横で袈裟は、なんでもないことのように微笑んだ。
「忍びは何度でも死ぬものにて。……生き返る方が、よほど難儀でござるよ」