「なぁ。神楽城って……軍人は来るか?」
ガイウスが尋ねた。
「真っ白の、軍服を着たやつだ」
袈裟はしばらく沈黙した。
風が吹き抜け、霧の中で花びらが舞う。
ようやく口を開いたその声は、どこか懐かしさを含んでいた。
「ふぅむ……外から軍人は来ませぬな」
一瞬、安堵が走る。
だがその後に続いた言葉が、空気を変えた。
「黒い軍人の方なら多くいらっしゃります。皆、神楽が落ちた日に囚われておりますが」
「……は?」
ルッツが固まる。
「待て待て待て、それ地縛霊じゃん!!」
バルトロメオが吹き出しかけて、慌てて口を塞ぐ。
「いや笑うなよ!? “黒い軍人が多くいらっしゃります”って、言い方が優しすぎるだろ!!」
ガイウスは眉をひそめ、袈裟の顔を見つめる。
「囚われてるって……自分で出られねぇのか?」
「はい。神楽が落ちたその夜、帝の命で自らを封じた者たちです。
“ここを抜ければ、国が滅ぶ”と信じて……そのまま。」
袈裟の声は、静かだった。
まるで今も彼らがそこにいるかのように、敬意を込めて語っていた。
ルッツが青ざめて呟く。
「……いや、なんでそんな人たちがまだ“いらっしゃる”テンションなの……?」
ハオが横で、ぽつりと笑った。
「死んでも職務を続ける兵士ヨ。忠義は骨まで、ネ」
ガイウスは腕を組み、霧の奥――神楽城の影を見た。
「……つまり、“黒い軍人”は出られねぇ」
「ええ。皆、“陛下の命をまだ待っておられる”」
その言葉に、空気が止まった。
霧の奥から、微かな声がした。
甲冑が擦れるような音と共に、かすれた言葉が夜気に混ざる。
最初はただの風のうなりかと思った。
だがそれは、確かに“言葉”だった。
しかも何度も――同じ会話を繰り返している。
「……大尉は……どこだ?」
声が途切れる。
次の瞬間、まったく別の方向から同じ声が重なった。
「大和はどこだ!?あいつの刀の腕はホンモノだ、あいつさえいれば魔物どもも食い止められる!!」
叫びが、霧に飲まれて遠ざかる。
代わりに別の声が応える。
「ダメです! 大尉が……どこにもいません!」
そのやりとりは、何度も、何度も。
音程も間も微妙にずれたまま、延々と反響している。
まるで同じ夜を、百年分繰り返しているかのように。
ガイウスが耳を澄ませた。
声は確かに近くにある――だが、話している者たちの姿はどこにも見えない。
霧の向こうには、黒い軍服だけが空中に浮かんでいた。
風もないのに、布地だけが揺れている。
「……“黒い軍人”か」
ガイウスが低く呟く。
ルッツは息を詰め、バルトロメオがわずかに肩をすくめる。
「百年経っても、まだ報告してるんだね……」
ハオが目を伏せた。
「忠義って、怖いネ。死んでも上司を探してる」
ガイウスの瞳に霧が映る。
「……“大和”ってのが、カリストのことか」
誰も答えなかった。
ただ、霧の中で――また同じ会話が始まった。
「大和はどこだ!? あいつの刀の腕は――」
「――大尉が、どこにもいません!」
それはまるで、神楽城そのものが記憶を壊したレコードのようだった。
そして“あの夜”を、永遠に再生し続けている。
霧が深く、声も音もすぐに吸い込まれていく。
門前の石畳を進むと、袈裟が振り返り、静かに頭を下げた。
「……日向大和(ひゅうが・やまと)大尉は」
その名を口にするとき、袈裟の声音がわずかに沈んだ。
「気づいたときには、消えておられました。
最早どこへ消えたか……忍びでもわかりませぬ」
「大和さんって人、きっと逃げたノネ」
ハオの言葉には非難ではなく、どこか柔らかな響きがあった。
生き延びるための逃走――それを責める気など、誰にもなかった。
ルッツが眉を寄せる。
「でも、その“逃げた人”を今も探してるってことは……
あの“黒い軍人”たち、まだ諦めてないんだよね」
袈裟は小さく頷いた。
「はい。彼らにとっては、あの夜が終わっておりませぬ。
“まだ戦の途中”なのです」
ガイウスが腕を組む。
「……気になるな、その大尉」
霧が再び濃くなる。
遠くで、鎧の擦れる音がした。
“まだ戦の途中”の兵たちが、今日も同じ報告を繰り返しているのだろう。
──朽ちた広間。
天井は崩れかけ、壁の裂け目から霧がゆっくり流れ込んでいる。
それでも、ランタンに火を灯せば、
わずかな暖かさだけは戻ってきた。
ルッツがマッチを擦り、火を点ける。
「これ灯すと魔除けになるんだって。……ちょっと休も、ね?」
怨霊が出ない、唯一の中継点。
畳の間で、五人はしばし腰を下ろした。
戦いの熱もようやく落ち着き、霧の外で虫の声のような風音だけが鳴っている。
ハオが小さく微笑み、懐から包みを取り出した。
「フーロンの嗜みとして茶器も持ってるヨ」
手際よく湯を沸かし、茶を注ぐ。
「はい、どうぞ。熱いヨ」
湯気が広がり、焦げた木の匂いに代わって緑茶の香りが漂う。
温かい湯呑を手にした瞬間、
ようやく「人間に戻った」ような感覚が訪れた。
自然と、話題は“軍”へと流れていく。
「なァ……袈裟さんさ。あんたが“この国で最もすげぇ”と思う人って、誰だい?」と尋ねた。
ガイウスの問いかけに、袈裟は即答した。
「……須藤晴輝(すどうせいき)元帥でござるな」
ルッツが目を丸くする。
「漢字多っ。名前の時点で強キャラ感あるわ」
「元帥にあられては、地位に溺れず、見返りを求めず、驕りを知らず──
……忍者の理想に候」
袈裟の口調は柔らかかったが、その声には誇りが宿っていた。
バルトロメオが笑みを浮かべる。
「元帥は忍者じゃないと思うけど……うん、尊敬は伝わるよ」
「ははっ、確かに。ですが、忍びというのは“己の影を誰かのために差し出す者”。
元帥様は、己の光ごと差し出された」
その言葉に、一同は静かになった。
茶の香りの中、沈黙だけが穏やかに広がる。
ハオが湯を注ぎ直しながら、ぽつりと呟いた。
「……その人、きっと、優しすぎたのネ」
袈裟は微笑んだ。
「そうかもしれませぬ。“優しすぎる”がゆえに、この国は百年、ここに留まっておるのやも」
ランタンの火がゆらりと揺れた。
その光が照らしたのは、五人の顔と、誰も座っていない座布団だった。
ランタンの灯がゆらめき、茶の湯気が静かに立ち上る。
外の霧のざわめきが遠くに消えていく中。
バルトロメオが、湯呑を指でくるくる回しながら言った。
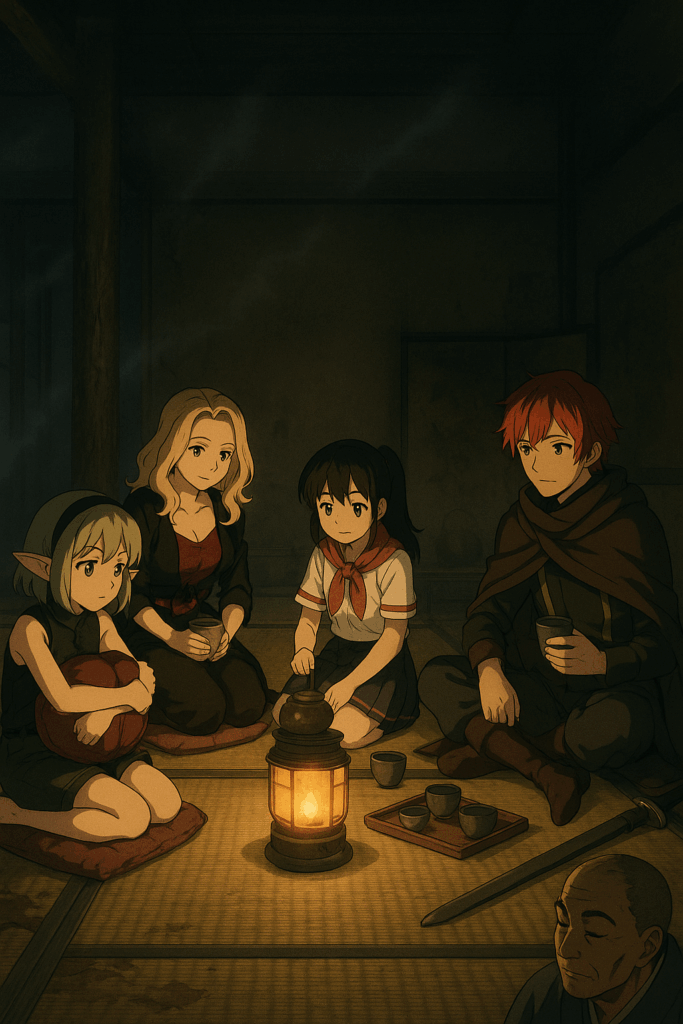
「じゃあ次は……神楽王のこと、聞かせてよ」
「袈裟さんなりの答えでいいよ。清宮様はなんで……幼い帝に御城を譲って、王様やめちゃったのかな」
袈裟は目を細め、少し間を置いた。
「えぇ……忍びや老中の間でも、清宮様の心意が読めぬと多く聞かれるのです」
静かに湯呑を置き、言葉を選ぶように続ける。
「これは飽くまで拙者の解釈でござるが……
清宮様は“国を残す”より、“人を残す”方を選ばれたのやもしれませぬ」
一同が顔を上げる。
「……どういう意味?」とルッツが尋ねる。
「神楽は、すでに戦の渦中にございました。
血で塗れたまま王が座に居座れば、国は王の亡霊と共に滅びる。
……ならば、自ら退くことで“怒りと憎しみの連鎖”を断とうとされたのです」
袈裟の声は穏やかだが、どこか遠くの出来事を見ているような響きだった。
「城を譲り、王をやめる。
それは敗北ではなく、“魂の切腹”にござる。
名を残さず、血を絶やすことで、次の時代に穢れを渡さぬ――
それが、清宮様の“奉還”の真意でござったのやも」
ハオが湯を口に含み、ゆっくりと飲み下す。
「……まるで、王が“自分ごと祓った”みたいネ」
「左様。ゆえにこの城は、今も“祓いきれぬ穢れ”のまま残っておる」
袈裟はランタンの灯を見つめた。
「清宮様は己を消すことで国を清めようとされた。
だが……残された者は、ただ“消えた主”を探し続けているのです」
沈黙。
霧の向こうから、どこかで太鼓の音が小さく響いた。
まるで百年前の神楽の残響のように。
ガイウスが小さく呟く。
「……死んでも、まだ忠義が続いてる国か」
袈裟が微笑む。
「だからこそ、誰かが“幕”を下ろさねばならぬのです。
神楽は、いまだ終幕を知らぬ舞台ゆえに」
ランタンの灯が一瞬揺れ、広間の影がまるで“観客”のように五人を取り囲んだ。
茶の香りがまだ広間に漂っていた。
袈裟は湯を注ぎながら、穏やかな声で言った。
「須藤元帥は、神楽が落ちてから、生前にも増して寡黙となられました」
その一言で、場の空気が変わる。
ハオが眉をひそめ、バルトロメオが動きを止めた。
袈裟はしかし、何事もないように湯呑を回す。
「しかし貴方がたなら、口を開いてくれるかもしれまする」
しばし沈黙。
霧の音さえ止まったように感じた。
ルッツが、ぽつりと口を開く。
「……へ? 元帥様……死んだって思ってたんだけど」
「今もいるの!!?」
「えぇ」
袈裟は微笑んだ。
「神楽城で数少ない“会話が成立する”相手でございまする」
湯呑を両手で包み、茶碗を回しながら、まるで茶会の続きのように。
ガイウスが即座に叫ぶ。
「ノリ軽いのに言うこと怖いよ!!!」
「ふむ……結構なお点前で」
袈裟は涼しい顔で茶をすすった。
ルッツが思わずバルトロメオの袖を掴む。
「ねぇ……“会話が成立する”って、つまり……?」
「つまり、他の奴らは……成立しないってことだろ」
ガイウスの声が低くなる。
「話しかけても、返ってこない。
あるいは、“同じ言葉しか返さない”──」
霧の奥、廊下の方から誰かの声がした。
『報告します、大尉が……見つかりません!』
古い声。
どこかで何度も聞いた残響。
袈裟が静かに立ち上がる。
「……さぁ、“元帥様の間”へ。この神楽城の、最後の主がお待ちです」
灯が揺れる。
誰もが無言のまま、立ち上がった。
茶の香りがまだ残る広間に、最後の湯気がゆっくりと消えていった。