少しの間、語りの熱が落ち着く。
静けさの中、茶の香りがゆっくりと広がる。
ガイウスが現実逃避のように、何気ない声を出した。
「はあ……ハオ、そういやさ──晴輝って、どういう意味なんだ?」
ハオはすぐ笑顔で返す。
「とても目出度い名前ネ。“晴れて輝く”、つまり──太陽ヨ。お日様みたいナ」
「……“はるき”だ。」
ルッツ(晴輝)が淡々と訂正する。
その声には、どこか遠い記憶の響きがあった。
「はる……?」と首を傾げるバルトロメオに、晴輝は少しだけ目を伏せる。
「我が諱だ。呼べるのは──家族と、許嫁の桜のみだ。」
その一言に、部屋の空気が止まった。
霧の音も、茶の湯気も、時間ごと静止したように。
ガイウスの胸に電撃のような感覚が走る。
(……!俺と同じだ)
“呼べる人間が限られてる名前”。
“絶対に他人に知られちゃいけない、真の名”。
胸の奥がズキンと鳴る。
(ルシウス・テルース・アルキード──)
誰にも言えぬ名が、脳裏で囁いた。
空気を切るように、バルトロメオが口を開く。
「……いいなずけ?」
「ハオちゃん、解説頼む。丙文化は難しくてね。」
ハオが小さく頷き、答える。
「結婚することを約束されたヒトのことダヨ。」
柔らかく説明してから、表情を引き締める。
「えーと……じゃあ、そろそろハオたちのターンね。」
「ヒュウガヤマト、て軍人さん……知ってる?」
ルッツ(晴輝)は迷わず答える。
「ああ。」
「あの青年大尉の顔は、今も覚えている。」
畳の上に、かすかな風の音が走った。
「ある日、日向正嗣殿は年にすれば十八歳ほどの青年を連れて来た。」
「“長男を丙最後の侍にしてくれ”と、そう言われていた。」
「だが重ねて言うが、私は侍ではない。私はただ一人の上司として、大和と向き合った。」
ルッツの声が少しだけ震える。
「大和が成人を迎えたあたりから、その目が少しずつ変わり出したのに気づいた。
目が合えば逸らす、何か後ろめたいことがあるように。」
そして、間を置いてから淡々と続ける。
「任務外でも、“お時間がありますか”と会いたがるようになった。」
ハオが、静かに息を吸い込む。
「もしかして……」
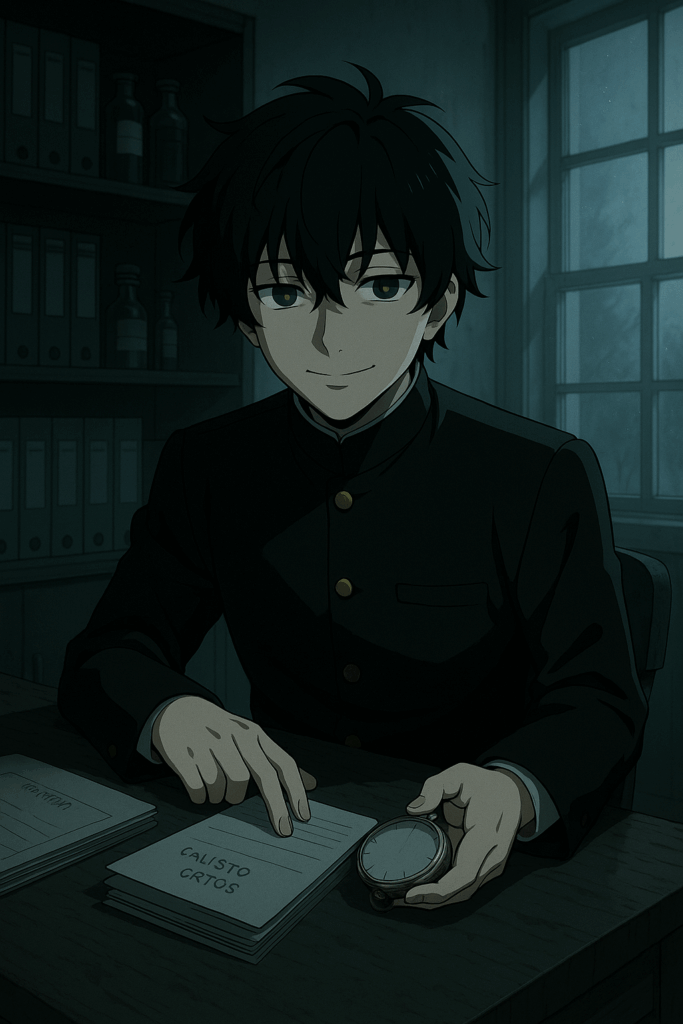
バルトロメオが低く呟く。
「同性愛は、禁じられていた……」
「……繋がったね。」
障子の外で、桜の花びらが一枚、ひらりと落ちた。
それは、許されぬ恋の余韻のように静かに舞っていた。
ルッツ(晴輝)の声が、ふと低くなる。
「そして──あの日。神楽城が落ちた日だ。」
空は鉛色で、雪が静かに舞っていた。
地に伏す兵たちの影が、白と赤に散る。
目の前に立つ“それ”は、男とも女ともつかぬ存在。
月光を喰らったような、形のない悪意。
日向大尉は震える手で剣を構えた。
示現流。
師の教えを最後まで貫くために。
だが、その刹那――背後から怒号が飛ぶ。
「日向ァ!! 何をしている、それでも剣鬼か!!」
「大尉なら先陣を切れ!! 死ぬのが怖いのか!?」
日向の肩がわずかに揺れる。
唇が震え、小声が漏れた。
「……何が“大尉なら”だ。」
そして、抑えきれぬ叫びへと変わる。
「死にたくない……死にたくないッ……死にたくない!!!」
剣が閃く。
斬撃音が雪を切り裂く。
上官の体が、音もなく崩れ落ちた。
血が雪に吸い込まれ、瞬く間に黒い花を咲かせる。
“それ”――月の悪意は、確かにその光景を見ていた。
ほんの一瞬、驚いたように。
次の瞬間、日向はその視線から逃げるように走り出した。
雪原を、闇を、己の恐怖を裂きながら。
静寂。
折れた軍刀のそばで、ルッツ(晴輝)は静かに目を閉じた。
ガイウスが、低く呟く。
「……逃げた、のか。」
その声には、怒りよりも悲しみが混じっていた。
バルトロメオが少しだけ微笑んで言う。
「残念だけど。9割の人間は“できない”ことだよ。」
「“恐怖に背を向けない”って、それだけで英雄扱いされるくらいには……普通は逃げるんだ。」
少しの沈黙の後、バルトはそっと続ける。
「僕も、日向さんと同じ立場にいたら……逃げるな。」
「死んだら、もう踊れないでしょ?」
晴輝の目が細くなり、口元にわずかな微笑が浮かぶ。
「……大和は、あの日──“逃げた”。」
「群雷と共に、“丙”を後にした。」
「否──見限ったのだ、この国を。」
ひと呼吸置いて、静かに言葉を落とす。
「……私は、咎めぬ。」
その声音には、怒りも嘆きもなく、ただ温かな赦しだけがあった。
まるで滅びゆく国そのものが、ひとりの若者を許したようだった。
「群雷(ぐんらい)? ぐんらい……?」
ルッツ(晴輝)の言葉の中に、ふと出た一語にガイウスが反応する。
バルトロメオがすぐに目を細めた。
「舞雷(ぶらい)と響きがそっくりだね。」
ハオは湯呑をそっと置き、表情を引き締める。
「もしかして……舞雷ちゃんの弟って……」
その瞬間、ルッツ──晴輝の口元がゆっくりと動く。
「日向の刀の腕は有名でな。帝や老中が、“丙いち”の刀工に刀を打たせたのだ。」
ガイウスの背筋に冷たいものが走る。
「……それが、“群雷”か。」
「然り。だが──その刀工は大和に刀を授けて、暫くして首を刎ねられた。」
室内の空気がひやりと凍る、誰も茶に手を伸ばさない。
「理由は聞かなかった。」
「やんごとなきものの真意など、知らぬほうがよい。」
ルッツの声は淡々としていたが、その瞳の奥には確かな憐憫があった。
“国の病”を知りすぎた人間の、達観した諦観。
障子の向こうで、雷鳴がひとつ鳴った。
まるで、“群雷”が遠くで応えるかのように。
「私はここに留まり、最後まで戦った。」
「だが見ての通りだ。こうして今も、留まっている。」
ルッツ(晴輝)の声は、すでに薄い霧のようだった。
語りの終わりとともに、茶の湯気がふっと途切れる。
ガイウスは正座を崩し、肩を軽く回した。
緊張の糸が切れたように、恐る恐る尋ねる。
「なあ元帥さま……あんた、何歳だったんだ?」
ルッツ(晴輝)は迷いもなく答えた。
「三十一だ。」
ただそれだけ。
それだけなのに、部屋の空気がずしりと沈む。
ガイウス(21)はぽつりと呟く。
「……たった10個しか違わねえのに……なんだこの威厳……」
その隣で、バルトロメオがやさしく笑った。
「いいんだよ。君、愛嬌あるじゃん? ほら、それで生きてこ?」
ふっと、ルッツの表情が和らぐ。
その笑みは、百年の霧を溶かすような静けさを帯びていた。
「……貴様らと過ごす時間は──少しだけ、悪くなかった。」
「──では、“名を呼ばれぬ男”の幕は、これにて。」
淡い光が広がり、軍刀の欠片が静かに浮かび上がる。
その光がルッツを包み、霊は静かに離れていった。
そして――。
「……んぁ!? え、えっ!? なんでみんな泣いてんの!? あたしなにしたの!?」
ガイウスが叫ぶ。
「うるせええええええ!!! 感動返せええええええ!!」
「はあ? 私に元帥が憑依して……嘘つけー!!」
「ホントだって!! あの威圧感! 俺、自然に“様付け”してたぞ!? 震えてたんだぞ!?」
バルトロメオが苦笑しながら立ち上がる。
「逃げた“大和くん”と、消えた“群雷”……」
「──きっと、それを見つけるまで、この橋の霧は晴れないね。」
ルッツはぽかんとしたまま、
「なにそれ、私そんな重要キャラだったの……?」
ガイウスは泣き笑いで肩を叩いた。
「おう、泣かせた責任とれや元帥!」
ランタンの灯が静かに揺れ、帝の間に積もっていた霧が晴れていく。
誰もが笑っていた。
悲しいのに、確かに“終わった”と感じられるような光の中で。
帝の間の奥。
古びた壁の裏に、袈裟が指で印を結ぶと石壁がゆっくりと音を立てて開いた。
袈裟が壁の印を結ぶと、重い音とともに石壁が左右に割れた。
そこには狭い通路が続いており、薄く冷たい風が吹き抜ける。
壁面には苔が張りつき、長い年月の眠りを物語っていた。
「ここから直通で、渡しまで通れまする。」
ルッツが目を丸くする。
「……“帝の間”から直通でお堀に通じる道があるなんて。
一番偉い人の道が、逃げ道だなんてさ。」
バルトロメオが肩をすくめる。
「見栄えがいい城ほど、裏側はこういうの多いよね。豪華さと裏口はセットっていうか。」
ガイウスが何気なく言った。
「珍しい事じゃない。アルキード城だって、玉座の後ろに地下通路があるんだ。
前、暇なときにあのオッサン(アルキード王)に見せてもらって知ってる。」
「ほぉ~、そんなのあるんだ?」とルッツ。
ハオは頷きながら、どこか達観したように言う。
「うむ~。主人を命に代えても守るってのは、どこの国も同じヨ。忠義の最後の形ネ。」
短い会話のあと、誰も口を開かなくなる。
壁の隙間から吹き込む夜風が、霧を少しだけ動かした。
この道が、かつて帝を救うために造られ。
今は勇者たちを次の物語へ送り出す――そんな奇妙な連続性を、誰もが感じていた。
袈裟は振り返り、静かに微笑んだ。
「そうそう……ハオ殿、黄泉送りをしていただけないだろうか?」
ハオが目を細める。
「……もう、行くんだネ?」
「はい。晴輝元帥が旅立たれた今、話し相手がいなくなってしまったのでござる。」
その言葉には未練よりも、穏やかな悟りがあった。
彼はまだ正気を保っている――だからこそ、旅立てるのだ。
袈裟は膝を折り、深く頭を下げた。
「未練が残らぬよう、揃いのポーズで見送ってくだされ。」
両手を組み、人差し指を立てる――あの“印”。
ハオが頷き、全員が静かに構える。
「これにて──御免。」
声が重なり、淡い光が弾けた。
残ったのは畳の上に落ちた一本の黒い手甲だけだった。
静寂。
ルッツがぽつりと呟く。
「……あぁいう幽霊なら、怖くないかもね。」
「いや幽霊より、元帥憑依したお前のほうが100倍怖かったからな!?」
ガイウスが即ツッコミを入れる。
「俺、正座して“はいっ”て言っちゃったんだからな!」
ルッツはふふっと小さく笑い、
「マジ? うける。」
バルトロメオが、少し離れた場所からやわらかく言う。
「“怖くない幽霊”って、理想かもね。……今の僕らみたいに。」
誰も言葉を継がない。
ただ、静かに微笑み合った。
静かな水面。
霧が少し晴れ、遠くに神楽城の影が霞んでいる。
あの日と同じ小舟が、岸で揺れていた。
船頭が櫂を支えながら、穏やかに問いかける。
「……探し物は見つかったかい?」
ガイウスが短く頷く。
「……ああ。また頼むぜ。」
船頭は口元だけで笑った。
「……あいよ。」
霧の向こうで、水面がひとすじ光を返す。
誰も多くは語らなかった。
だが、その“間”にすべてが詰まっていた。