香水や雑貨、絵葉書の並ぶショーウィンドウ。
その一角に、赤い蝋で包まれた丸いチーズが網袋ごと吊るされていた。
ガス灯の光を反射して、まるで小さなルビーのようにきらめく。
「見て!この網に入ってんの可愛い!」
ルッツが両手でぶら下がった袋をガチャガチャ揺らす。
店員がにこやかに声をかけてくる。
「それはベビーベルだよ。アルルカンじゃ定番のおやつでね」
「一口サイズだから手も汚れないし、栄養もある。冒険者に人気なんだ。
旅立つ人はだいたい一袋持ってくよ」
「ほほぅ……保存もきくネ?」
ハオが興味津々にのぞき込み、さっそく購入して皮をむこうとする。
が、やたら時間がかかる。
「……固いナ、これ」
「いや、それ普通は一瞬で剥けるやつだから」
ルッツが笑いをこらえながら突っ込む。
バルトロメオは赤いチーズを手に取り、目を細める。
「へえ……見た目はお菓子みたいだけど、ちゃんと腹にたまるんだな」
ひと口で食べ、踊り子らしい仕草でうなずいた。
「ふむ、美味。こういう素朴なの、案外クセになるんだよね」
ルッツは目を輝かせる。
「チーズってもっとくさいやつ想像してたけど……これ食べやすい!
やばい、これおやつにしようよ!!」
その喧騒の中で、ガイウスだけは黙っていた。
吊るされた赤い網袋を見つめ、ふと息を止める。
赤い蝋の光が、かつてノワール区の路地でチーズを剥いて笑っていた。
あのガキの姿を脳裏に重ねる。
――サタヌス。
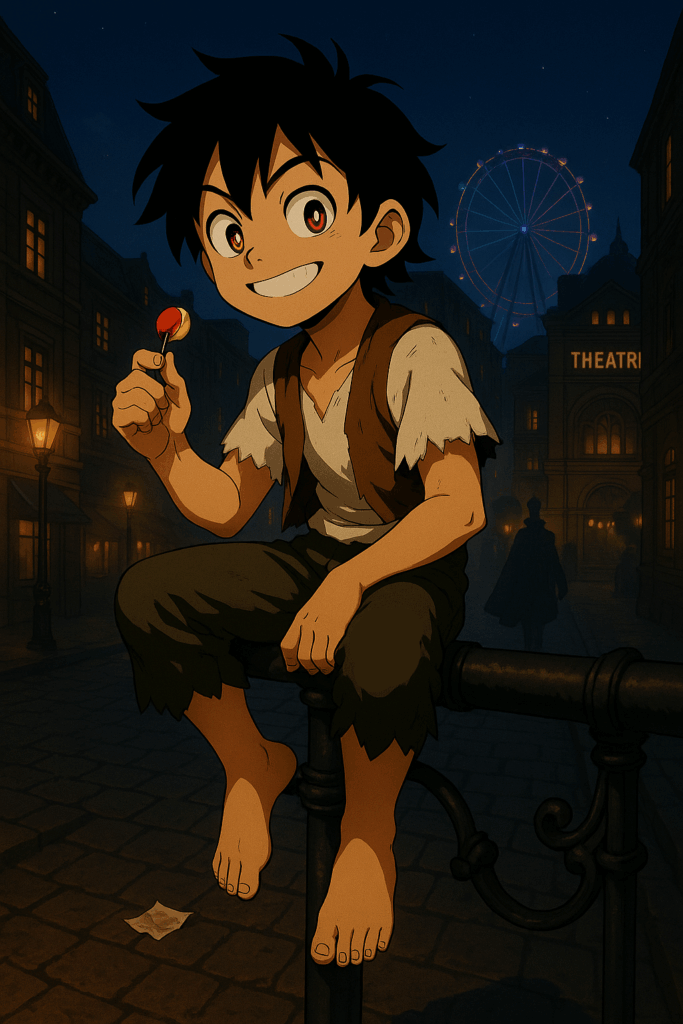
店員が続けるように言った。
「ちょうど仕入れて良かったよ。
こないだギルドの団体さんが来てね、みんなベビーベル買って在庫なくなっちゃったんだ」
ルッツが笑う。
「いや、これはわかる。ポストカードとかピンバッジより断然テンション上がる!」
バルトロメオも頷く。
「赤い蝋の丸が並んでるだけで可愛いって、反則だよな」
ハオが肩をすくめて微笑む。
「映えるし美味いし実用的──最強の三拍子、ネ」
ガイウスは、また無言でその袋を見上げた。
網の赤が、視界の奥に焼きつく。
……サタヌス。お前のことだから、今もどっかでチーズ齧って笑ってんだろ。
店主が懐かしむように言った。
「チーズを剝くねずみ──なんて呼ばれてた子が、勇者になるなんてねぇ。
みんな驚いてるよ。あの子、ベビーベルをあげるといつも喜んでたから」
「エトワール区の商人がね、こっそり破棄されたパンやチーズをあげてたんだ」
アルルカンの下層では、かつて廃棄された食材が“闇の流通”として生きていた。
彼はその中で、“ネズミ”と呼ばれるほどに早く、正確に、チーズを剥いた。
誰も名前を知らなかった、けれど剥く速さだけは街中で有名だった。
夜の灯りに照らされて、路地の鉄柵の上に少年が腰掛けていた。
裸足の足をぶらぶらさせながら、手に持つのは赤い蝋で包まれた小さなチーズ。
ベビーベル。
彼の名を知る者はいなかった。
誰もが彼を、ただ「ねずみ」と呼んだ。
薄汚れた服、煤けた頬。
それでも彼の目だけは、奇妙に澄んでいた。
――あの“同心円”。
少年の瞳には、まるで渦のような光の輪が宿っていた。
それが、彼が“異端”である証だった。
貴族たちはその目を嫌った。
「気味が悪い」「焦点が合わない」「魂を覗かれるようだ」と。
彼が通るたびに、上層の人々は遠巻きに視線を逸らした。
けれどノワールの者たちは違った。
店主は煙草をくわえながら、笑って言った。
「目が渦巻いてるくらい、かわいいもんだよ」
「荒らしはしねぇし、ノワールのガキなんざうるさくて汚いのが普通だ」
だから、あの子は不思議と好かれていた。
静かで、誰にも迷惑をかけず、ただ廃材の上でチーズを剥いて笑っていた。
剥く速さは誰よりも鮮やかだった。
赤い蝋を指で器用にくるりと外し、ぱくりと食べる。
そのたびに、口の端がわずかに上がる。
“剥き終わると同時に笑う”――それが、ねずみの癖だった。
店主はふと、ガイウスに目を向けて言った。
「……あの子、今どこにいるのかねぇ」
ガイウスは何も言わなかった。
ただ、吊るされた網袋を見上げる。
赤い蝋の光が、まるで彼の瞳の“同心円”のように揺れていた。
ノワール区の夜風が吹き抜ける。
どこかで誰かが笑う声がして、ガイウスの胸の奥がかすかに熱くなる。
――チーズを剥くねずみ。
あの頃、舞台の音を聞きながら「いつか俺も」とつぶやいた小さな夢。
それが、異端の勇者サタヌス・ルプスの原点だった。
夜の帳がゆっくりと落ち、ルミエール区のネオンが灯り始めた。
紫と金の光が混ざり合い、街全体がまるで舞台装置のように輝く。
その喧騒の中、ひとりの少年がいた。
サタヌスだ。ルミエール通りの看板に、ふてぶてしく腰を下ろしている。
下を行く貴族たちが足を止め、顔をしかめた。

「まあ、はしたない!降りなさい、あなた!」
だが、少年は口の端を吊り上げ、
赤いスカーフを風に遊ばせながら笑った。
「文句言うなら登ってみろよ、おばさん!」
どっと周囲がざわめき、誰かが息を呑む。
少年の眼には、まるで夜空を模したような同心円が輝いていた。
貴族たちはそれを直視できず、何も言えずに通り過ぎるしかなかった。
その少し先――階段の上では、別の“異端”が立っていた。
黒いスーツに身を包んだ女、ヴィヌス。
彼女はシアターの灯りを背に、ひとり静かに階段を上がっていく。
その姿はまるで、舞台へ向かう前の女優そのものだった。
「悪役で存在が霞むような主役は二流よ。私は舞台を引き締める役なの」
誰に向けた言葉でもない。
ただ、自分の中の“舞台”を律するための呟き。
遠く、街の明かりが滲む。看板の上の少年と、階段を上る女。
二人の間には、ほんの数十メートルしかないのに――その距離は、決して埋まらない。
けれど確かに、同じ夜の空気を吸っていた。
そしてその夜風の中、ガイウスは“いない子”の気配を感じて立ち止まった。
「……今、誰か……」
ルッツが振り返る。
「どうしたの?」
ガイウスは首を振る。
「いや……気のせいだ」
けれど彼の耳には、確かに聞こえた気がした。
「チーズ剥くか?」と笑う、あの声が。
アルルカンの夜風が吹く。
紫の街は、まるで舞台の幕が下りるようにゆっくりと暗くなっていった。