馬車の車輪が、湿った石畳を軋ませながら進んでいく。
森を抜けた瞬間、霧の向こうにその町は現れた。
まるで世界の端にぽつりと取り残されたような、静かな町。
赤い屋根、古びた木骨造りの家々。
その窓には小さなランプが灯り、橙の光が霧の中でぼんやりと滲んでいる。
遠くの丘には、古い鐘楼がひとつ――時間を忘れたまま、森と一緒に息をしていた。
「……見えてきた」
ルッツがぽつりと呟いた。
彼女の声はかすれていたが、その目には確かに光があった。
霧に濡れた金髪が頬に張り付き、風が小さく吹き抜ける。
バルトロメオは窓から身を乗り出し、口笛を鳴らした。
「こりゃまた、絵本の中みたいな町だな」
「エルフの住処ってもっとキラキラしてると思ってたヨ」
ハオが首を傾げ、くるりと尻尾を揺らす。
「実はソルーナ、行きたかったんダヨネ」
「えっ?珍しい。大体の食材はフーロンで揃うんだろ?」とバルトロメオ。
「そうだけど、燻製に関してはソルーナに勝てないヨ。あとジャガイモのレパートリーもネ」
「ジャガイモ……?」
ガイウスがぼそりと呟いた。
彼の目には懐かしさよりも、戦場の前に立つ兵士のような覚悟が宿っている。
故郷でも、帰る場所でもない。ただ“仲間の故郷”を守るために、ここまで来た。
霧が濃くなり、道が二つに分かれる。
ルッツは躊躇なく右の道を指さした。
「こっち。森の奥、湖のほとり。そこが――聖域への入り口」
森の奥から風が吹き抜ける。
針葉樹の葉がざわめき、霧の中の家々がかすかに揺れる。
世界そのものが、彼らを試しているようだった。
ガイウスは窓の外を見つめ、低く呟く。
「……行くか。勇者の“原点”まで」
馬車はゆっくりと、霧の中へと消えていった。
その先に待つのは、光か、闇か。
誰もまだ、知らなかった。
霧の中から、ひとりの女が現れた。
籠を抱え、頭には白いスカーフ。目尻には皺が刻まれているが、その笑顔は若木のように柔らかい。
「あら〜ルッちゃん。帰ってきたの?」
懐かしい声に、ルッツの肩がびくりと跳ねる。
「ルッちゃん!?」
すかさずガイウスが聞き返す。
ルッツは振り返りもせず、顔を真っ赤にして早口で言った。
「ちょ、ちょっと!その呼び方すんな!」
おばさんは笑って首をすくめた。
「そうさね、ソルーナはよく森から若いエルフがやって来る街でもあるんだよ」
霧の中に、少しずつ人の影が増えていく。
木造の家の扉が開き、パンを抱えた青年、ハーブを束ねた娘、みんながルッツを見て微笑んでいる。
彼らの胸元や軒先には、どれも“淡紫の蝶”の紋章が飾られていた。
蝶が輪の中で羽ばたく、細やかな意匠。朝の霧に溶けるように淡く光っている。
「フェイの紋章か」
ガイウスが呟くと、近くの老婦人が頷いた。
「臭み消しのハーブもエルフから教えてもらったんだよ。森の恵みは、みんなで分け合うもんさ」
エルフは森から出ないと言われている。
だがこの街だけは、その“掟”に風穴を開けていた。
霧が人と森の境をぼかし、蝶がその証となっている。
ルッツは足元の石畳を見つめ、少しだけ笑った。
「……みんな、変わってないな」
「ルッちゃんの方が変わったよ」と誰かがからかい、彼女は小石を蹴って誤魔化した。
そんな空気を割るように、ハオが手を挙げた。
「それより時間ある?ソーセージ見たいんダケド」
「始まったよ、料理人魂……」とバルトロメオが溜息をつく。
ハオは気にも留めず、屋台の方へくるくる歩いていく。
「まぁいいさ」
ガイウスは笑って肩をすくめた。
「森はどんだけ歩くかわからないよ、見ていこう」
霧が晴れ始める。
淡紫の蝶が一羽、静かにルッツの肩へ降りた。
それはまるで――森そのものが、“おかえり”と囁いているようだった。
霧の町を抜けると、香ばしい匂いが鼻を突いた。
それは森の湿気に混ざって漂う、燻製とハーブの香り。
通りに並ぶ屋台のほとんどが、なぜかソーセージ関連専門店だ。
通りすがりの冒険者が、半泣きで叫んでいた。
「毎晩ゆでソーセージとじゃがいもでノイローゼになりそうなんだよォ!!」
だが隣の女冒険者は、串を片手にニコニコしている。
「毎日違うソーセージ食えるとか最高♪」
二人の温度差が、ソルーナの“現実”を物語っていた。
ルッツは肩をすくめる。
「誇張じゃないわよ、あれ。マジでソルーナの食事あんな感じだから」
「え、ほんとに?」バルトロメオが半笑いで尋ねる。
「朝は焼き、昼は煮て、夜は燻して終わり。たまにパンとスープつくけど……結局ソーセージよ」
「……食の楽しみって知ってるキミら??」
「肉食ってりゃ幸せなのよ、ここの人たちは」
その時、ハオが目を輝かせて走ってきた。
「見て見て! 燻製屋が十軒連なってるヨ!」
「それ全部同じ味じゃねーの?」
「全部違うネ! 一本目は松の香り、二本目はナラの香り、三本目は……」
「もうやめて、胃袋が寒気してきた」
バルトロメオがうんざり顔で頭を抱える。
ガイウスは苦笑しながら、通りの向こうに並ぶ看板を見上げた。
どの店にも、淡紫の蝶の紋章が刻まれている。
「……アルキード人とソルーナ人の夫婦をよく見る理由、分かった気がする」
バルトロメオがパンフレットを手に、ため息をついた。
「……アルキード人とソルーナ人って、なんで結婚うまくいくんだろうな」
ハオがソーセージをかじりながら首を傾げる。
「相性良いネ? 一見、紅茶とビールぐらい違うのに」
ルッツは即答した。
「むしろそれが良いの。アルキード人は“お茶の時間さえ守れれば生きていける”って人種」
「食事は……“まぁ食えればいい”くらい」
「え、マジで?」
「マジ。ガイウスなんてお菓子は全部うまいって言うのに、夕飯の味は覚えてないタイプよ」
「ほっとけ」
カップを傾けながら、ガイウスは渋い顔で返す。
ルッツは続ける。
「で、ソルーナ人は毎晩ソーセージとじゃがいもで気にしないんだけど、燻製には命賭けてる」
「うわ……方向性真逆の執念……」とバルトロメオ。
「でもどっちも“こだわりの一杯”があれば幸せなのヨ」ハオが笑う。
「アルキードは紅茶で、ソルーナはビール?」
「正解ネ!」
一瞬の沈黙のあと、ガイウスがぼそっと言った。
「……つまり、夫婦喧嘩しても“紅茶片手にソーセージ焼いて仲直り”するわけか」
「そういうこと!」
胃袋が外交の要だったとはね……」
「平和の秘訣はカロリー」
霧の町ソルーナ、静かな森の片隅で、笑い声と肉の焼ける音が響いていた。
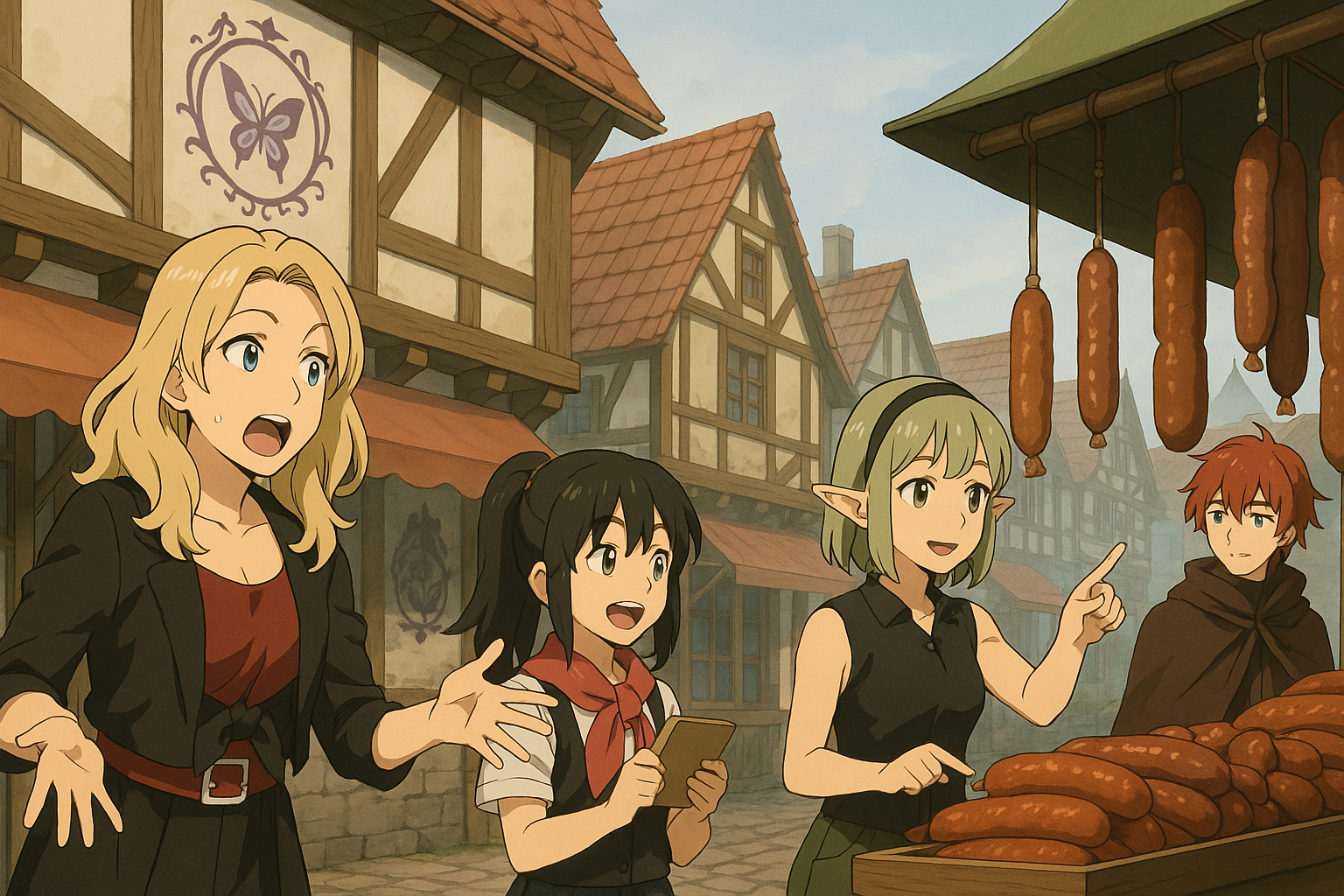
ソルーナの燻製通りは、朝から香りが濃い。
肉を吊るした屋台の軒先から、煙とスパイスの匂いが絡みつくように流れてくる。
ガイウスは腕を組み、無言でそれを眺めていたが、やがてぽつりと口を開く。
「なぁ俺ら、ちょっと遠出するんだけど」
「火を通さずに食えるソーセージってある?あと日持ちするのがいい」
屋台の店主は、腰に手を当ててにやりと笑った。
「それならサラミはいかが?ほら、試食」
ガイウスは無言でひときれ受け取り、かじる。
その瞬間、彼の表情がふっと和らぐ。
「うん……」
鋭い目つきも、戦場帰りの空気もどこへやら。
今そこにいるのは――完全に“おやつを食うシェパード”だった。
ヴィヌスがよく「シェパード!」と呼んでいた理由が、今になってようやく分かる。
ハオが横で、頬を緩めながら言った。
「なんか、わんこって言われてる理由わかった気するヨ……」
ガイウスは気づかないふりをして、もう一切れ齧る。
サラミの脂が舌の上で溶け、鼻を抜ける煙の香りが心地よい。
その穏やかな横顔が、妙に人間くさい。
「……あ、それより、唐辛子に合うソーセージは何?」
「スパイシー系だね?ならこれはどうかな」
店主が差し出した赤みの強いソーセージを見て、ハオの瞳が輝いた。
「これ!この香り!絶対炒めてもうまいヤツ!!」
ルッツとバルトロメオは、呆れたように顔を見合わせる。
「結局いつも料理の話になるんだな」
「この子、絶対旅の目的“食材集め”でしょ」
それでも、笑い声が響く。
霧に包まれた町で、どこまでも人間らしい音がした。
戦いの前に、こんな穏やかな時間があることが、奇跡のように思えた。
ハオは買ったばかりのスパイシーソーセージを包んでもらうと、
その場にしゃがみ込み、手帳を開いた。
革表紙のノートには、びっしりと小さな文字が並んでいる。
「フーロン基準辛味指数:7……ソルーナ式スモーク香辛指数:9」
「辛味の研究ノート」に、さらさらと新しい記録が加えられていく。
旅のメモというより、もはや食の学問書である。
バルトロメオが笑いながら、紙袋を抱えたガイウスを見やった。
「なぁ勇者さん、マスタードつけなくて平気?結構子ども舌でしょ?」
「……うるせぇ」
短く返しながらも、口の端がわずかに緩んでいる。
手元のサラミをひとかじり。
香辛料の粒が舌に弾ける音が、やけに心地よい。
ルッツはそんな二人を見て、呆れ半分、微笑み半分で肩をすくめた。
「まったく……この調子で本当に“聖域”まで辿り着けるのかしらね」
けれどその声には、どこか安堵が混じっている。
笑い声の混じる買い出し風景は、彼女にとって“帰ってきた町”そのものだった。
ソルーナ市場・お買い上げ表(勇者一行)
サラミ(試食後即購入)・ガイウス 「犬用ではありません」と店主メモ
スパイシーソーセージ(赤唐辛子ブレンド)・ハオ 「辛味指数9」研究対象
ジャガイモ10kg ルッツ・「煮込み・炒め・つぶし用」
ハーブミックス(消臭&保存用)・バルトロメオ 料理補佐兼おしゃれ目的
マスタード(小瓶)・店主おまけ。ガイウスの反応確認用
霧の町を離れる風が、鐘楼の鐘を鳴らした。
次の目的地――聖域ソルーナの森。
旅立ち前の腹ごしらえは、完璧だった。