ソルーナ郊外の丘は、煙と硝煙の匂いに包まれていた。
崩れた家々の影、焦げた煉瓦の街路、その向こうに――ゆっくりと迫る、黒鉄の車列。
魔王軍の戦車、自走砲、装甲兵が、粉塵を巻き上げながら進軍してくる。
その光景はまるで古い悪夢が再演されるかのようだった。
そして、その群れの中で、ただ一人。
黒と金の衣装を纏った女が、戦車の上に立っていた。
バルトロメオが息を呑む。
「うわぁ……これはまた、悪の女王って感じだね」
ハオは苦笑いを浮かべる。
「悪オーラ出過ぎてて潔いヨ……」
煙の向こうで、その女――ヴィヌスがゆっくりと振り返る。
金の縁取りが施された漆黒の衣、1年前と同じ色。
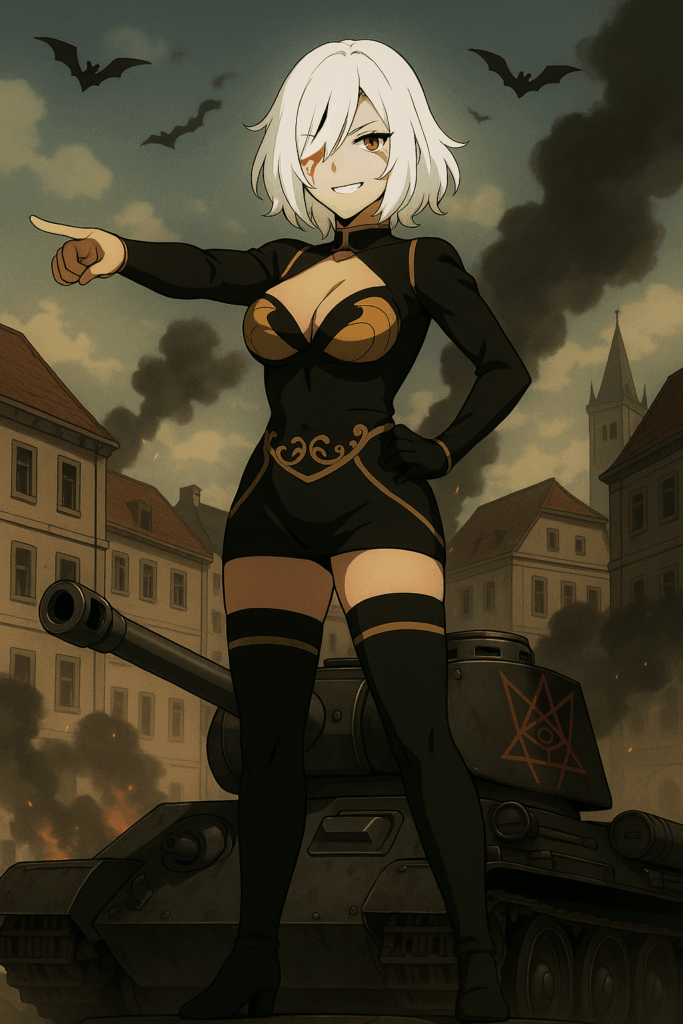
だが、今のそれは――まるで異形の礼装だった。
黒地に金糸の刺繍を走らせながらも、どこか“生き物”のように蠢いている。
胸元の黄金の意匠は翼のように開き、背中には紅い光脈が脈打っていた。
気品と悪意、神聖と穢れ――すべてが同居したその姿は、
美しくも悪趣味な、悪夢の舞台衣装だった。
ガイウスは言葉を失う。
彼の脳裏に、あの日のステージが浮かんだ。
“ヴィヌス”が、今は炎の中で同じポーズを取っている。
「……ヴィヌス、なのか……!?」
その問いに、女はゆっくりと指を伸ばし、
舞台の幕を上げるように空を指した。
「一年ぶりね、シェパード」
唇が笑みを描く。
その声音は、あの頃と同じ――だが、どこか艶を増していた。
「ちょっと色々あって。今、魔王軍側にいるの」
「でも……安心して。これは“台本じゃない”からね?」
彼女の赤い瞳が、まるで舞台灯のように揺れる。
ヴィヌスは、戦車の上で椅子をわりと当然のように使い、片脚を組んだまま笑っている。
足元には黒いベレー帽を頭に乗せた兵士が、サロンの椅子代わりにされている。
灰色の煙と火粉が背景で踊る中、彼女の笑い声だけが妙に軽やかに響いた。
「内容は簡単よ」
「どうせこの体じゃ聖域に入れないからね、じゃあ森ごと燃やしてやろうってわけ!!」
兵士が顔面蒼白で「あ、あのヴィヌス様…ヒールが頭に」と言いかけると。
ヴィヌスは指先でその声を遮るように振り向き、にやりとした。
「黙って♡」
兵士たちは震え、銃床を握り直す。
舞台と化した戦車の金属が、彼女を崇めるかのように鈍く光った。
ルッツの胸が高鳴る。目が爛々として、信じられないほどの嫌悪と恐れが混ざった顔で言う。
「なんかすごいドSなんだけど!?洗脳されてあぁなったとか?」
ガイウスは、その言葉に苦笑を含ませながら首を振る。
視線はヴィヌスの動きに釘付けだ。
「いや、ドSなのはあぁなる前からだ」
ルッツが「もともとかよ!!」とつっこむ余裕もあったが。
次の瞬間、ガイウスの声が冷えた。
「来るぞ!」
空気が変わった。笑い声が風に吸われる。
ヴィヌスの唇に浮いた嘲りがぴたりと止まり。
彼女自身が「戦い」を演じる俳優に収束していくのが見える。
ベレー帽の兵が合図を送り、機関銃の銃口が一斉に向けられた。
ガイウスの心臓は、もう怒りでも恐怖でもないところで鼓動していた。
バルドが教えた「断心閃」の芯が、腹の奥でじわりと温度を変える。
思考が研がれ、世界の音が厚手の布で覆われるように消えていく。
周囲の声は遠のき、空気の振動だけが残った。
鞘の金属音すら遠く、ただ自分の呼吸だけがはっきりと聞こえる。
世界は刃が通る直前の静けさに入り、時間が刃の先に集まる。
ガイウスは一歩踏み出した——動作は稲妻のように短く、だが静謐だった。
風が彼の髪を揺らし、瓦礫の埃が一瞬渦を巻く。
刃が抜ける瞬間、彼の内側で積もったすべての怒りも。
すべての後悔も、無駄な感情も、鋭く切り捨てられた。
世界が戻ってきたとき、刃は既にヴィヌスの前面を貫いていた。
だがそれは、肉をえぐるような獰猛な斬撃ではない。
音のない断絶――風景と時間を一瞬にして二つに割るような切り口だった。
ヴィヌスの衣の装飾が裂け、彼女の右腕の近くに浅い切り傷がつく。
火花が散り、血が一筋、彼女の淡い肌に線を描いた。
ヴィヌスは笑みを保とうとしていたが、その笑顔が一瞬、引きつる。
赤い瞳の光がほんの少しだけ揺れ、彼女の口から出たのは驚き。
あるいは初めて味わう「本気で傷つけられた」感覚だったのかもしれない。
「……ふふ、やるじゃない、シェパード」
彼女の声は、やや震えていた。
だが挑発は止めない。怒りと遊び心が混じった調子だ。
ガイウスの呼吸は早くも整い、剣を鞘に戻す。
彼は血の匂いと、切れ味の余韻を体の中で静かに受け止める。
「これで終わりだと思うなよ」
戦いは終わっていない。ヴィヌスは不敵に笑い、兵を鼓舞する。
勇者たちは歯を食いしばり、次の動きを決めるために身を低くした。
霧と火花の中で、二つの意志が改めて刃を交わそうとしていた。
鋼の衝突音が、ひときわ大きく響いた。
ヴィヌスの双剣が空を裂き、火花が雨のように飛び散る。
それを受け止めたガイウスの腕は、既にしびれていた。
鉄を噛むような感触が手のひらに残る。
呼吸のリズムが狂うたび、剣の軌道が微かに鈍る。
それでも後退するわけにはいかない。
ヴィヌスは口の端を上げ、冷たい声で笑った。
「どうしたの、シェパード? 音が遅いわよ?」
彼女の黒衣の下では、魔族製の呪詛装備が光を放っていた。
一つ一つが高位の魔術師の血を対価に作られた、正真正銘の禁装。
対して、ガイウスの装備は旅の途中で買い足した店売り品。
鎧は擦り切れ、ベルトも革が伸びている。剣すら研ぎが甘い。
同じ実力でも、装備の差が如実に出る。
ガイウスは壁際まで追い込まれ、背中が石壁にぶつかる音がした。
ヴィヌスが剣を構え、唇を歪ませる。
「どうしたの? 折角の“勇者様”が、そんなボロ布着てるからよ」
一方、瓦礫の裏手ではルッツたち三人も奮闘していた。
ヴィヌスが召喚した悪魔の群れが、黒い炎を纏いながら押し寄せる。
小悪魔ですら一体ずつが兵士並みの力を持ち、数は十を超えていた。
「どうにか、あの装備品を外せたらねぇ…!」
ルッツが悪魔の腕をかわしながら叫ぶ。
「でもどうやって!?」
「それが難しいんだヨネェ…!」
ハオが悪魔の顎を蹴り上げ、
バルトロメオが体を捻って魔法障壁を張る。
三人はただ、互いを守りながら時間を稼ぐしかなかった。
(くっそ~このままじゃジリ貧だ……!)
(何か手はないノ!?)
(せめて武器があれば……!!)
焦燥が胸を焦がす。
周囲には炎と煙、そして悪魔たちの笑い声。
一方のガイウスも、額に汗を浮かべながら歯を食いしばっていた。
「はぁ……はぁっ……!」
息が切れる。
ヴィヌスの剣が肩口を掠め、火花が散る。
「ねぇ、シェパード」
「アンタ、まだ気づかない? “現実”って、こういうことよ」
笑い声が、炎の中で鈴のように響く。
それは残酷さよりも、美しさを纏った音だった。
ヴィヌスは勝利を確信した。
剣を大きく振りかぶり、満面の笑みで刃を振るう。
その瞬間だけ、彼女は完全に油断していた。
「もらったああああぁぁ!!」
その隙を、ガイウスは見逃さない。
かつての彼なら、剣が折れた瞬間に棒立ちになっていただろう。
だが今は違う。むしろ、これを好機とばかりに口角を上げる。
「秘孔・命門!」
鋭く指が突き、ヴィヌスの動きが一瞬止まる。
「はうぅっ!?…う、な、何…したの…?」
「ヴィヌス、俺ね。今は武闘家やってるんだよね。だから今のお前の急所なんて簡単に突けるんだぜ?」
ガイウスは爽やかに笑う。
その表情は好青年そのものだが――いま、この状況で向けられたら、むしろ恐怖でしかない。
「さぁて、そろそろ効いてくるぜ…さっき突いた命門のツボが」
「はうぅぅ!?あああぁぁぁ!!」
ヴィヌスの体がビクリと跳ね、煙が上がる。
やがてそれは全身を覆い、彼女は絶叫する。
「ぐうううぅっ!あ、熱いぃ!!焼けちゃうううぅぅぅ!!!」
「おーすげー声出すじゃん、ヴィヌスちゃん」
「ふざけないでぇええぇぇぇ!!!」
ヴィヌスは怒りのまま炎を爆発させ、ガイウスを吹き飛ばした。
壁に叩きつけられた彼は、血を吐きながら崩れ落ちる。
ヴィヌスは、肩で息をしながら高笑いする。
「……ふう、ふぅ……ふ、ふふふ……あはははははっ!!
やった、やってやったわ!!ざまあみろよ!」
髪をかき上げるその顔は、まさに“悪の女王”。
いや、本来のヴィヌスだ。
勇者時代は抑えていた本性が、いま、悪魔として開花している。
「しょせんアンタは私の引き立て役がいいほうなのよぉ!!
二度と握れないぐらいぶっ壊してやるよ!」
その時、間に割って入る影――。
「待てぇ!!」
ヴィヌスが振り返る。
「あ゛ぁ!?ハーフエルフ風情がなんの用。今更遅いのよ!」
ルッツだ。
小さく足が震えていても、その瞳には決して折れない意志が宿っている。
彼女はガイウスの前に、しっかりと立ちはだかった。
「ここはあたしの故郷よ。森は大嫌いだけど……荒らすのは許さない!」
ルッツの叫びは震えていたが、その瞳は真っ直ぐだった。
「素直な子ね。大嫌いなんでしょ? じゃあ私が代わりに滅ぼしてあげるわ!」
ヴィヌスは楽しげに笑いながら剣を振る。
「エルフ共は聖剣の守護という名目で閉じこもって、外界と遮断してるだけ!
人間なんか見下してるに決まってるわ!! あんたの両親も追放したようにね!!」
「……違う」
「え?」
「父さんと母さんはいつも幸せそうだった。
少ししか一緒にいれなかったけど、いつもあたしを大切にしてくれた」
「嘘ね、どうせ演技してたんでしょう」
「そんなことないっ!」
「もういいわ、あんたから死になさいよ!!」
ヴィヌスの剣が振り上げられる。
もはや間に合わない距離。
ルッツは目を閉じ、ガイウスが血反吐まみれの口で何かを言おうとする――
その瞬間だった。
バルトロメオが不意に立ち上がる。
手にしていたのは、青く輝く瓶。
「おい、こんな時に何して――」
「演出って大事なんだよねぇ♪」
ウインクひとつ。
バルトロメオは瓶を高く掲げ、踊り出した。
ステップと共に、瓶の中身が霧のように広がっていく。
――聖水。
ミスト状になった聖水が神殿全体を包み、
人間にはほんのり涼しく感じる程度だが――。
「えぇ? う、嘘っ……私の装備が、あ!? ちょっとやめなさいーっ!!」
刃先が白煙を上げ、柄が溶け、鎧が崩れる。
手で抑えようとするが、その手からも煙が上がる。
悪魔たちも形を失い、煤になって消えていく。
そこに残されたのは――黒いランジェリー姿のヴィヌス。
「きゃああああああー!!」
通りの子供が指を差して叫んだ。
「ママ~あの人裸~!」
「こら~! 指さしちゃいけませ~ん!!」
ハオがその様子を見て小声でつぶやく。
「……エルフもやるんだ、あのやり取り」
その一言で、ガイウスが吹き出した。
「あっはっはっはっは!!! いやー傑作だったな!」
「おいキズ野郎、笑いすぎ……」
「いや~だってさあ、アイツ調子づいてた癖に下着で逃げてったんだぜ?
しかも途中でコケるしさぁ! あれでしばらく笑えるわ~!」
腹を抱えて笑うガイウス。
呆れながらも、ルッツも、ハオも、バルトロメオも、つられて笑った。
――こうして四人が揃って笑うのは、初めてかもしれない。
煙の残る空の下、その音がソルーナに静かに響いた。
戦火の煙が、まだ空を覆っていた。
ソルーナの煉瓦通りには、瓦礫の上で砕けたガラスが光を反射し、
焦げた匂いと鉄の味が入り混じっている。
ヴィヌスは、戦車の上から一瞥を投げると、
まるで舞台を降りる役者のように、一陣の黒煙とともに姿を消した。
――戦いは終わった。
だが、胸の中には何かが残る。
ガイウスは剣を鞘に戻し、静かに息を吐いた。
耳の奥で、まだ爆音の残響が鳴っている。
「おかしい……」
彼は、戦車の砲塔の上、ヴィヌスが立っていた場所を見上げる。
風が灰を巻き上げ、視界が揺らいだ。
「一年前のあいつに、あんなの……なかった」
脳裏に浮かぶのは、あの頃のヴィヌスの笑顔だ。
そこには、確かに“ヒビ”なんてなかった。
だが今の頬には、深紅の裂け目のような線が走っていた。
まるで“顔”そのものが拒絶しているかのように、
皮膚と何か別の存在が、分離しようとしていた。
「魔王軍の残党に“何か”されたのか……?」
呟きながらも、答えは出ない。
だがその“何か”が、呪いではないことだけは、直感で分かっていた。
ガイウスは拳を握りしめ、遠く、煙の向こうを見つめる。
「……あの顔、忘れられねぇな」
風が吹き抜ける。
その音だけが、戦場の名残を優しく撫でていった。