王都・晩餐会。
貴族たちの質問に答えるロディの頭の中は、常に必死の翻訳作業で埋まっていた。
納屋で怨言を吐く兄。
→ 「深く心身が傷ついていたため……うわ言のようなものを口にしていました」
鶏をシメて『安らぎ……』と呟く兄。
→ 「村に野生の魔物が入り込んだので、退治して心を落ち着けていたのです」
剣を引き摺りながら夕方の村を徘徊する兄。
→ 「歩行訓練です。村人に迷惑をかけぬよう、日没後にひっそり行っていました」
貴族たちは感動の面持ちで頷く。
「なるほど……勇者殿は故郷でも規律を忘れぬ方だったのだな」
「やはり英雄には深き覚悟がある……!」
ロディは額に汗を浮かべながらも、無理やり笑顔を作った。
内心は、ひとりツッコミが止まらない。
(我ながら俺、こんな嘘上手かったか?)
(これもう詐欺師なれるぞ……)
こうして晩餐会の夜は「勇者の美談」だらけで彩られていくのだった。
好奇心旺盛な貴族たちからようやく解放され、ロディは一人、霧の街を歩いていた。
ガス灯はまだ消えず、石畳に灯る光が頼りない影を落とす。
いよいよ、明日の朝。
勇者代理としての演説が待っている。
だがリハーサルの時間もなく、準備はぶっつけ本番。
手の中のカンペをぎゅっと握る。
紙は汗でしわくちゃになりかけていた。
「……とんでもねぇの背負ったわ……でも……」
小さく、しかし確かな声が漏れる。
「……俺、弟だからさ」
「兄ちゃんが壊れてまで守ったモン、全部台無しにするわけにいかねぇ」
その瞳は、もはや「少年」のそれではなかった。
聖痕を持たぬ勇者代理が、霧の街に凛と立つ。
その眼差しには狂犬と恐れられた兄にも引けを取らない。
強い覚悟の炎が灯っていた。
壇上に上がった少年は、まず深々と頭を下げた。
緊張で足が震えていたが、その声はよく通った。
「本日――勇者・ガイウス・アルドレッドの代理を務めさせていただきます。
弟の、ロディ・アルドレッドです。」
ロディが壇上に立ったとき、玉座の間の空気は冷たかった。
「ガイウス様、自分は無理だからって弟に押し付けるなんて……」
「聖痕もないただの少年に、何ができるのだ」
貴族たちは眉をひそめ、兵士たちでさえ腕を組んで渋い顔をしていた。
だが、ロディの言葉が静かに響き始めると、空気が少しずつ変わっていった。
「長きにわたる戦いの果てに、勇者の仲間たちはそれぞれの道を歩むことになりました。
そして兄は、その重さゆえに休養を命じられています。
英雄であっても、戦いの代償からは逃れられません。
心に深い傷を負うこと、それは罪ではなく、人の弱さであり、人の証でもあります。」
観衆がざわめく。
「罪ではなく、人の証……?」
「思ったより……重みがあるぞ」
やがて彼の声は、会場を包み込むように落ち着いて広がっていく。
「兄の剣は血を求めるためのものではありません。
人々を守るために振るわれ、そのために数多の命を背負ってきました。
もしその責任を忘れてしまえば、権威も栄光も意味を失うでしょう。」
「正義が声を失えば、民は苦しみ続けます。
その痛みを、私たちは決して忘れてはならない。
兄は断罪者ではありません。
戦いの光と影を、誰よりも深く知る者です。
だからこそ、その想いを私が伝えに来ました。」
「夜は必ず訪れます。
けれど夜の果てには、必ず朝が来る。
私たちはそのことを、今一度心に刻むべきです。」
子供を抱いた平民の母親が、思わず涙を拭った。
兵士の一人は、無意識に拳を握りしめる。
「朝は来る……確かに、俺たちはそうやって耐えてきた」
貴族たちも、互いに視線を交わし、次第に口を閉ざす。
「ただの少年かと思ったが……」
「いや、あの目を見ろ。兄と同じだ。あの覚悟……本物だ」
「今ここに宣言します。
正義は民のためにあるのであって、権威のためではありません。
私たちが憎むべきは人そのものではなく、過ちであり、弱さです。
それをただ断罪するのではなく、共に正していくことこそが希望へとつながるのです。」
「もしも明日を拒み、進むことを止めるなら――
その時こそ、私たちは剣を取り、未来を切り拓きます。
それが勇者の使命であり、兄から託された想いです。」
「私は聖痕を持ちません。
けれど、弟だからこそ分かるのです。
兄が壊れてまで守ろうとしたものを、決して無駄にはできないと。
だからこそ、この声を皆に届けます。」
「勇者ガイウスの意志は、ここに生きています。
どうかそのことを――覚えていてください。」
最後にロディが「兄が壊れてまで守ろうとしたものを無駄にしない」と語ったとき。
玉座の間を満たしたのは最初の冷ややかさではなく、確かな静寂と共感のざわめきだった。
その場にいた誰もが「勇者の血は、確かにここに生きている」
そう思わずにはいられなかった。
“聖痕を持たぬ少年”にすぎないはずの声が、不思議なほど観衆の耳に残った。
アルキード王国でのロディの勇者代理演説は、勇者史上。
かつてないほど地に足がついた現実的な内容となった。
理想や夢ではなく、これから民が直面する苦しみと課題。
そしてそれを支える決意。
王侯貴族すら言葉を失うほどの誠実さが、そこにあった。
演説が終わり、静寂が玉座の間を包んだ。
だがその沈黙は、決して冷たいものではなかった。
大臣は顎に手を当て、疑わしげな目でロディを見据える。
(会話すら危うい状態から……ここまで整ったスピーチが出来るはずない。
……おそらく代筆だ。誰かが裏で整えたに違いない)
そう解釈することでしか、この場の異様さを飲み込めなかった。
彼にとって“勇者は常に異端”であり、理解不能の存在であったからだ。
一方、玉座に座る国王は違った。
彼は目を伏せ沈黙し、静かに一枚の肖像画を見上げた。
初代国王――ザイ・アルキード。
その隣には、弟にして初代勇者-テラ・アルキードの肖像もある。
王は幼いころから幾度もこの肖像を眺めてきた。
王位を築いた兄と、剣を掲げた弟。
支え合いながら国を形作った二人の姿。
ラピア王宮。
現国王が玉座から目を逸らし、壁に掲げられた肖像を見上げる。
そこには初代国王ザイ・アルキードと、その弟にして初代勇者テラの姿があった。
ふと――確かに聞こえた気がした。
肖像の向こうから、低く渋い声が。
「テラ、なぜ魔王を逃がした?」
「お前ならば討てたはずだ」
声の主は兄王にして初代国王-ザイ・アルキード。
数秒の沈黙の中、テラ・アルキードは無言で立ち尽くしている。
その無言が、答えであるかのように。
やがて再び声が落ちる。
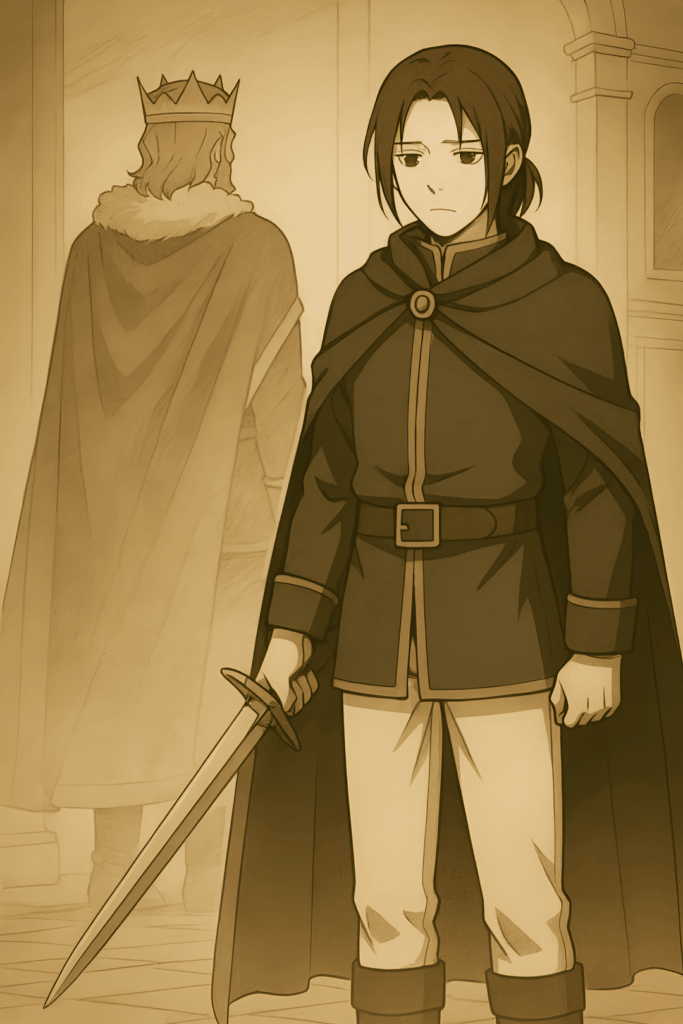
「……もうよい」
「お前は王家に生まれるには野心がなすぎる」
「どこにでも、好きなところへ行け」
現国王は、はっとして我に返る。
肖像の前には誰もいない。
けれど今の一瞬、初代王と初代勇者の対話を垣間見た気がしたのだった。
そして今――目の前に立つ赤髪の勇者ガイウスと、その弟ロディ。
「まるで……初代王家が戻ってきたようだ」
国王の胸に去来したのは、恐怖でも、疑念でもなく、錯覚に近い畏敬の念だった。
王は誰にも聞かれぬほどの声で呟く。
「勇者とは……やはり、王国の血脈とは別のところで巡り合うものなのだな」
こうして、王族すらも“アルドレッド兄弟”に、歴史の影を重ね始めるのであった。
一方その頃。
ガイウス・アルドレッドは王都の外れを歩いていた。
瞳を曇天に向けながら、彼はふと呟く。
「……ロディ、ちゃんと喋れてるかな」
しかし、その足は止まらない。
彼だけが感じ取ったのだ。
再び現れつつある、エクリプスの胎動を。
狂犬は再び旅に出る。
追放された勇者として。
そして、弟に“光”を託した兄として。