朝。
曇天、濡れたアスファルト、どこかぬるい空気。
街全体がしっとりと沈み、通りの色彩が一段階落ちて見えた。
(雨の日は配達も気が滅入るな……)
そう思ったその矢先、上司が差し出した伝票。
見た瞬間、タチバナの顔が引きつる。
「おいタチバナ、これ頼むな。宛先は“なかよしハイツ”だ」
「……また、あそこスか」
紙の端に滲んだインクが、じっとりと雨粒のように歪んでいた。
住所欄にはこう書かれている。
なかよしハイツ 333号室 ご宛名:ユピテル様
唯一の救いは「宅配BOX希望」の文字が記されていることだった。
これなら、住人に直接会うリスクはない──はずだ。
(……宅配BOXなら、きっと大丈夫。きっと……)
そう自分に言い聞かせ、レインコートのフードを深くかぶる。
ぬるい雨が、アスファルトの上で音もなく跳ねた。
こうして、タチバナの試練は再び始まった。
なかよしハイツのエントランスを抜け、
タチバナは再び、濡れた階段を一段ずつ上がっていく。
建物全体が静まり返っていた。
外の雨音が、薄いコンクリの壁を通して“ざぁ”という低い唸りに変わる。
その途中──ふと、共有スペースの隅に置かれた長椅子が目に入った。
何かがそこに、横たわっている。
(……誰か、いる?)
目を凝らすと、それは人のようであり、人でないようにも見えた。
座布団を枕に、黒いフードの少女が眠っている。
髪は闇のように艶やかで、息は浅く静か。
そう、かつてエレベーター前でしゃがみ込み、
片目だけでタチバナの魂を射抜いた──あの「黒猫」だ。

(よかった……今回は寝てる……)
恐る恐る視線を逸らしながら、足を忍ばせる。
彼女はタチバナの気配にわずかに寝返りを打つ。
拒絶はない。だが興味もない。
ただ、自分の世界の夢を見ているような静けさ。
(……大きい音を立てたら、確実に終わる)
喉を鳴らすことすら恐れ、一段、また一段と足音を殺して階段を登っていく。
──のちに知ることになる。
あの朝「唯一の癒し」は、たぶんこの光景だけだった。
ユピテルの部屋へ向かう途中、薄暗い廊下の先に“誰か”の気配があった。
雨の音に混ざって、コツ、コツ、と一定のテンポで鳴る靴音。
……いや、これは靴じゃない。
誰かが、足でリズムを取っている音だ。
(……?)
視線の先。
廊下の中央、赤いスカーフを首に巻いた少年が立っていた。
黒髪は雨に濡れてボサボサ、浅黒い肌に浮かぶ筋肉のライン。
遠くに見る分には、
どこにでもいそうな活発な中東系の少年……のように“見えた”。
「なンだよ!今日はウラとゲーセン行く約束だったのに!!」
ぶつぶつと不機嫌に文句を言いながら、
彼は壁を蹴り、リズムを取るように片足でトントンと鳴らす。
表情は明るい。声も元気。
だがどこか、音のテンポがズレていた。
そして、唐突にこちらへ顔を向けた。
「んあ? 兄ちゃんなんだ、配達?」
近づいてきた瞬間、タチバナの心臓が一拍止まる。
その目が、普通じゃなかった。
瞳が──まるで渦を巻くように、同心円状に揺らいでいる。
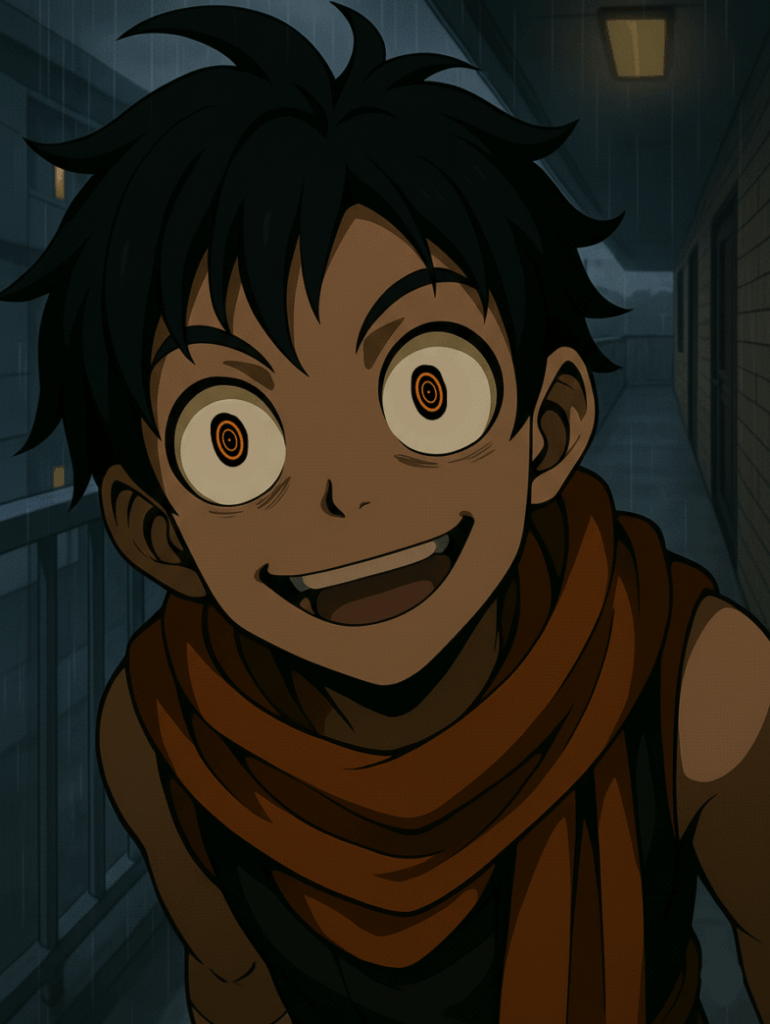
焦点が合わない。
こちらを見ているはずなのに、その視線が“奥の何か”を覗いている。
(……やばい。これ、絶対目ぇ合わせたらダメなやつ)
少年はニヤリと笑い、首をかしげながら一歩、また一歩と近づく。
足音だけがやけに重く響いた。
「ウラ、寝坊したのかな〜?兄ちゃん見なかった?緑の髪でチビなの」
「い、いや……知らない……」
「そっかぁ〜。あ、でも兄ちゃんも遊ぶ?」
「遠慮します!!!」
返事より早く、踵を返して逃げる。
背中越しにまだ、あの同心円の目が追ってくる気配がした。
サタヌスをどうにか撒き、タチバナはほとんど駆け足で廊下を進んでいた。
階段を曲がるたびに、雨の音が近くなったり遠くなったりする。
まるでこの団地そのものが呼吸しているみたいだ。
だが──ある地点を踏んだ瞬間、足裏が“ヌチャッ”と滑った。
「……うわ、濡れてる……?」
床全体が異常に湿っていた。
雨漏りどころの騒ぎじゃない。
まるで誰かがバケツ一杯の水をぶちまけたように、床が光っている。
壁にも、足跡のような水の痕跡が点々と続いている。
(……おかしい。窓もないのに……)
照明の青白い蛍光灯が、水たまりに反射してゆらゆらと揺れる。
視界の端には──魚のウロコのような、きらりと光る何か。
一歩進むごとに、靴底が“ピチャッ、ピチャッ”と鳴る。
冷たいのに、なぜか熱がこもる。
それは“生温かい”水だった。
(……誰か、通った……?)
誰もいない。だが、通った。
その感覚だけは確かに残っている。
静寂の中──ふと、奥のドアの向こうから声が聞こえた。
女性の怒鳴り声だ。
怒っている。激しく、何かを責め立てるように。
「ふざけないでッ! 雨の日なんて聞いてないわよ!!」
……そして、間を置いて、穏やかな男性の声。
聞き覚えのない落ち着いたトーン。
どこか知的で、感情が希薄な声だった。
「雨に怒っても仕方ない。それにほら……カエルも愛嬌あるじゃないか」
その一言のあと、室内が一瞬静まり返る。
そしてまた「ギャアアア!!!」という絶叫。
(……部屋の中の人、さっき“ギャアアア!!”って叫んでなかった?)
少し笑いそうになったが、すぐ我に返る。
壁の向こうでは、いまだに雨と悲鳴が混ざっていた。
その音を背に、タチバナは足早にその場を離れた。
水たまりを蹴る音が、まるで何かに“ついて来られている”ように。
一定の間隔で追いかけてくる。
雨の廊下を抜けた先、
突き当たりの壁に取り付けられた宅配BOXが見えた。
無機質な金属の扉がずらりと並び、そこだけが団地の中でやけに“新しい”。
「……よし、ここで終わりだ」
宛先は──ユピテル様。
前回、唯一直接の接触を避けられた相手。
それだけに、胸の奥で安堵が滲んだ。
(本人が出てこないのが唯一の救い……)
端末を操作しようと、液晶画面を軽くタップする。
だが次の瞬間、文字がぐにゃりと歪んだ。
「登 録 者 :ユピ テ ル」
「あ そ び ま し ょ う」
「斬りますね。」
液晶が明滅し、まるで意志を持ったかのように文字を組み替えていく。
カタカタと電子音が鳴るたびに、画面の中で雷マークが点滅する。
「……これ、仕様じゃないよな……?」
慎重に小包を入れる。
そのとき──扉が閉まる音が、妙に反響した。
それは、まるで剣を抜く時の金属音。
(……今の音、気のせいだよな?)
背筋に冷たい汗が流れた。
荷物を入れ終え、逃げるように踵を返したその瞬間。
隣室のドアの向こうから、笑い声が聞こえた。
「怖がってる……可愛い……」
「フフフフ……フフフフフフフ……」
その声は、静かで艶やかで、凍るように冷たい。
思わずタチバナは足を止め、ドアを見た。
中からは光一つ漏れてこない。
ただ、笑いだけが続いている。
(やめろこえぇから!!)
声は次第に遠ざかり、雨の音と混ざって消えた。
ドアの向こうに“誰か”がいるのは確かだが、
その存在を確かめる勇気は、もうどこにもなかった。
タチバナは最後まで気を引き締めていた。
この団地を出るまで、気を抜くわけにはいかない。
理由はひとつ。
前回ここで、最恐の存在と鉢合わせたからだ。
(……今日は大丈夫。いない。絶対いない……)
エントランスのガラス越しに、外の雨が見える。
しとしとと降り続ける朝の雨。
だが、その静けさが逆に神経をすり減らしていく。
玄関前の自動ドアの反射に、自分の姿しか映っていないことを確認し。
ようやく足を動かした、その時だった。
「配達員さん、雨止まないみたいだよ」
背後から、穏やかな声がした。
どこか懐かしいようで、けれど決定的に違う響き。
「……俺と遊ぼう?」
ぞくり、と背筋が凍る。
振り向くまでもなく、気配でわかった。
“何か”が、すぐ背後に立っている。
ゆっくりと振り返る。
黒いコートをまとった長身の青年が立っていた。
赤い瞳が、まっすぐタチバナを見下ろしている。
瞳孔は──ターゲットマークのように収束していた。
笑っている。だがその笑顔は、人間のものではない。
唇の動きと、声のリズムがまったく合っていない。
(……ガイウス、さん……?)
声は似ている。音色も、言葉の癖も。
だがどこかが違う。微妙な音程のズレ。
まるで“別の誰か”が、録音を再生して喋っているような。
遠く、大家の部屋の方角から別の声が聞こえた。
「坊っちゃん、今日何する〜?」
(……ガイウスさんは、向こうにいる……)
(じゃあ、今ここにいる“これ”は──)
その瞬間、直感した。
これは“ガイウス”ではない。
青年──いや、“ガイウスのような何か”が、そっと肩に手を置いた。
ギリ、と骨が軋む音がした。
「あ。配達員さん……まだ人間じゃん」
赤い瞳が愉快そうに細められる。
「死なないヤツ以外と遊んじゃダメなんだった」
笑い声が、喉ではなく、空気そのものから響いた。
「またね」
その言葉と同時に、ふっと圧が消えた。
タチバナが恐る恐る振り返ると、
そこにはもう誰もいなかった。
ただ、雨音だけが残っていた。
そして足元には──赤いマークのような跡が濡れた床に残っていた。
雨の日の配達を終えた翌朝、タチバナは社内の共有端末を開き。
そっと一文を追加した。
《配達ルート注意事項:更新版》
・渦巻き目の少年 → 距離感バグ(視線)
・濡れてるだけの廊下 → 通ると精神が濡れる(霊圧)
・宅配BOX → 脱構築(機械に意志)
・見えない声 → 油断が死因(存在証明の矛盾)
・虹目に似た“それ” → ガイウスではない(ラスボス)
みんな優しい。ただし“こっちのルール”で生きてない。
エンターキーを押した瞬間、タチバナは椅子の背にもたれ、深く息をついた。
「……あの、アバドンの配達員って……全員あぁいうの経験してるんですか?」
隣のデスクで書類をまとめていた先輩が、顔だけこちらに向ける。
目の下に深いクマ。
手には、冷えたコーヒー缶。
しばらく沈黙が続き──先輩は意味深にニヤリと笑った。
「一皮むけたな。記念に海境屋の干物をやろう、うまいぞ」
差し出された包み紙には、見慣れたウロコ模様。
封の隙間から、かすかに潮の匂いと……血のにおいがした。
【怖いぞ、なかよしハイツ —完—】