「うーむ…魔王どもの残党は大陸に逃げたて言うしな、港に行くか…」
ここはアルキード王国より西の地にある港町。
其処で一人の青年が頭を抱えていた。
名はガイウス。
アルキード王国から追い出され旅の最中であるクズ、もとい勇者である。
「おいおいどうしたァ兄ちゃんよォ?」
そんな彼に話しかける者がいた、いかにもガラの悪いチンピラといった風体だ。
「……あぁン?」
「ヒィッ!?な、なんだよ怖い顔するなよぉ!
向こうでケンカが起きてるんだよぉ!兄ちゃん強そうだから止めてくれよ~」
「チッ……仕方ねぇなぁ、あとで酒奢れよな」
そうして彼は案内されるがまま現場に向かうと、確かにケンカが起きていた。
船乗りは気性が荒い者が多いのでこういうのは珍しくない、なんだか今回は少し違う。
「何よこのー!大陸に行くなら乗せなさいって言っただけじゃないのよー!」
「ダメだ!耳尖ってるじゃねぇか、魔族だろてめー!魔族は乗せねぇ主義なんだぁ」
「誰が魔族だ!ハーフエルフよ!!良いから乗せろコノヤロー!」
どうやら船に乗せてほしいハーフエルフと拒否する船員のやり取りらしい。
この手のトラブルはよく見る光景だ、別に珍しいことじゃない。
大抵の場合種族差別が原因で起きるのだ。
こういった諍いはどこでも起きているのだ。
(さてどうすっかな……とりあえず仲裁に入るか)
正直言って面倒臭いのだが仕方ない。
このまま放っておくと殴り合いにまで発展しかねないからな。
ガイウスはすっと「まぁまぁ落ち着いて」と間に入る、猫かぶり全開の笑顔で。
「まぁまぁまぁお嬢さん落ち着きなさいな。大陸に俺も行くところで」
「でもこいつ!耳が尖ってるやつは乗せないって言うのよ!」
「うーーーん困ったねぇ……あ、船長さん。俺と……そうだ、腕相撲しません?」
「え?別にいいけど……なんで?」
「負けたら彼女を乗せてあげてください、大丈夫加減しますんで♪」
そういって彼は審判役の船員と向かい合うように座る。
そして彼が合図をすると試合が始まった、結果は当然彼の圧勝だった。
だが力の差を見せつけるためにわざと手加減してやってるので。
しばらく硬直していたが顔を赤くしていたのを見て、一気に倒す!
「うおおおっ!?」
「はい俺の勝ち~!というわけでお嬢さんどうぞお乗り下さいませ」
「えっ……いいの?」
「いいっていいって、さぁ乗った乗った」
こうして彼女は無事(?)乗船できたのだった。
(うーん……あのおっさん弱すぎだな、ちょっとムキになりすぎたか……?)
そう思いながら船内を歩く、今は甲板をあのハーフエルフと歩いていた。
ローブを着ていたので分からなかったがまだ幼いらしい、10代くらいに見える。
まあハーフエルフだから、実際は自分よりも長生きなんだろうけど。
「私はルッツ、ハーフエルフよ。ちょっと前森を家出してきたとこ」
(家出?じゃ俺と同じで帰れねぇ人間か)
まさか自分と同じ境遇の人間がいるとは思わなかった。
だがこれはチャンスかもしれない、 ここでこいつを利用し。
上手いことやれば自分の株も上がるかもしれないからだ。
「へぇそりゃ災難だったな。ま、せっかくだし仲良くしようぜ」
「うんよろしく!」
そう言って握手をする二人、だがこの時の二人は知らなかった……。
この先も何かとアクが強い「居場所」を失った人々が集うことになろうとは。
地平線-どんどん遠ざかる故郷。
小さくなっていくアルビオン島を目に焼き付けつつ。
ガイウスはふと思い出したように口を開いた。
「メルクリウスのやつ、言ってたな」
「聖剣を守る森は真っ黒で、木々がすぐに生え替わるから、地図が絶対に作れない。
聖教の作った聖域じゃない、“ホンモノ”なんだって」
ソルーナ大森林。
大陸の北に広がるその森は、昼なお薄暗く、木々の影が折り重なる。
樹皮は煤を塗ったように黒く、切り倒しても翌日には別の芽が生えている。
根は大地を割り、絡み合い、迷い込む者を足元から捕らえた。
霧は濃く、方角を狂わせる。
陽が差し込むことは稀で、鳥の声も途絶える。
その異様さゆえ、地図を描こうとした者は誰一人成功していない。
人々は恐れを込めて「聖剣を守る森」と呼ぶが。
それは聖教が信仰のために築いた聖域でない、原初の結界。
ルッツは黙ってその言葉を聞いていた。
故郷を嫌って飛び出してきた少女の目に、あの森の闇は今も焼き付いている。
ルッツは甲板に肘をかけ、海風に髪をなびかせながら言った。
「そ。あの森、偏屈でね。エルフ以外を絶対入れたがらないの」
「だからその分、一度嫌われると帰れないって言っていいとこ」
ガイウスはしばらく黙っていた。
隣に立つ少女の横顔を盗み見て、何も言わずに視線を海へ戻す。
甲板の向こうではカモメが通る声で鳴き、白い翼が空を切っていった。
ルッツはわざと明るく、吐き捨てるように続けた。
「むしろせいせいしたわ、あんなクソッタレな森」
「ほとぼり冷めるまで帰るもんか」
その言葉には強がりと、ほんの少しの寂しさが滲んでいた。
ガイウスはただ無言で、同じ海を見つめ続けていた。
「で、エルフがなんでアルビオン島にいたんだ?」
「点と点が結びつかねぇんだが」
「アンタ勇者でしょ?ならエクスカリバー見たでしょ」
初対面でそう言い放つ彼女の言葉には、理由があった。
「あれ、エルフが代々守ってきた聖剣だから。
昔から、あの島とエルフは縁深いんだよ」
アルキード王国の在る島-アルビオン島は勇者伝説の発祥地であり、聖剣が眠る地でもある。
ルッツの一族は代々そこで“森の民”として剣を守護してきた。
だが、ルッツは祖父と大喧嘩し、家を飛び出した。
「どうせなら一度くらい、伝説の剣が眠る島をこの目で見てやる」と思い。
自然と足はアルビオン島へと向かっていた。
気晴らしのつもりで訪れたはずの島。
だが――そこで彼女は思わぬ問題に巻き込まれる。
耳が尖っているせいで、港の人間たちに魔族と間違われ。
その場で揉め事を起こしてしまったのだ。
そして、そこに居合わせたのが“追放勇者”ガイウスだった。
英雄譚の残り香と、エルフの伝承。
二人の出会いは、皮肉にも聖剣伝説の島から始まった。
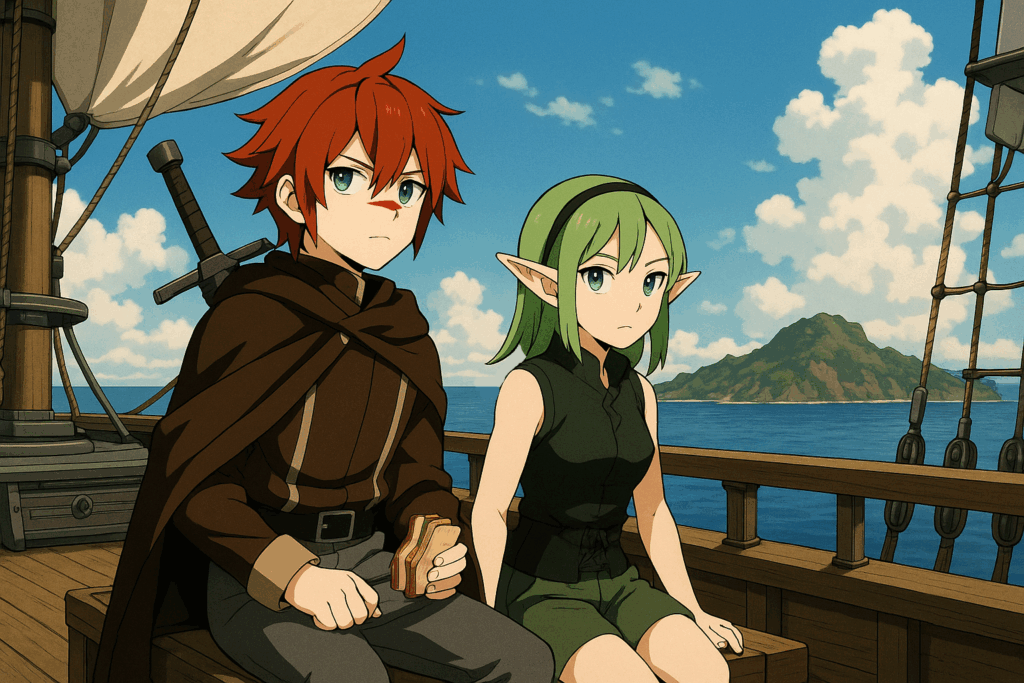
ルッツはじっとガイウスを見つめ、眉をひそめた。
「ねぇ、勇者なのにエクスカリバー持ってないの?」
問いかけに、ガイウスの肩が微かに揺れる。
普段の“狂犬”の鋭さは影を潜め、珍しくしどろもどろになった。
「いや……あれは、王様に返した……」
「だがまさか、ガチモンの聖剣とは知らずに、その……」
ガイウスは声を落とし、気まずそうに続ける。
「引き摺ってた」
ルッツは一瞬沈黙し、それから噴き出すように笑った。
「多分エクスカリバーも、勇者に引き摺られるとは思ってなかったと思うよ」
ガイウスは苦笑し、わずかに頷く。
「……だな」
甲板の向こうでカモメが数羽、青い空へと舞い上がっていった。
ガイウスとルッツは甲板を後にし、船室へ向かう。
通路を歩きながら、ふと周囲を見回して違和感を覚えた。
「……前に乗ったときより、随分変わったな」
甲板員が手で回していた滑車や舵輪が、歯車に置き換えられている。
帆を畳む作業も、鉄製のウィンチが勝手に動いていた。
廊下の壁には魔導ランプが並び、微かに蒸気の匂いが漂っている。
ルッツは目を丸くした。
「一年前は、もっと古臭い船だったのに……」
ガイウスは短く頷き、磨かれた鉄のレールを指先でなぞった。
「産業革命ってやつだな。……世界は勝手に進んでいく」
二人の背後で蒸気の音が吐き出され、船は確かに“新しい時代”を切り裂いて進んでいた。
ガイウスは廊下の鉄製レールを眺めながら、肩をすくめた。
「こりゃ、勇者って概念もそのうち化石扱いかもな」
ルッツは隣で歩きながら、口元を歪めて答える。
「いやー、どうだろ? メキア商会のおっさん達が言ってたよ。
“マナスチームがどうとか”……新しい動力だか何だか知らないけど?
時代は進んでも、人は簡単に変わらないんじゃない?」
彼女は少しだけ真剣な目をして続ける。
「だってさ、どんなに機械が増えたって……。
“ヒーローになんとかして貰おう”って願望は消えないと思うよ」
ガイウスは一瞬黙り、やがて苦笑を浮かべた。
「……そうかもな」
自分の役割は終わったはずなのに。
もう魔王はいないのに。
ガイウスはため息混じりに呟いた。
「自立しろよな……人間」