「灰の目さんとは今もやりとりしてルノ?」
唐突なハオの問いに、ガイウスは眉をひそめた。
宿場のベンチ。膝の上では猫がまるまって、尻尾だけが気怠げに揺れている。
「あぁ、バイトとして描いてたまに送ってる」
「これが報酬良くてな。魔物退治より安定して稼げる」
言いながら、どこか気まずそうに視線を逸らした。
描くこと自体は嫌いじゃない。ただ、“あのギルド”に評価されるのが腹立たしいだけだ。
それは、勇者時代の悪ふざけから始まった因縁だった。
当時、メルクリウスが“匿名”で送った一枚のスケッチが、
ソラル中央推理ギルド「灰の目」に認められたのがきっかけ。
その後、勇者ブランドが失墜し、民衆の信仰が薄れた頃から——
「真実を暴く者=探偵」への需要が急速に高まった。
魔王の再来も、勇者の堕落も、人々にとってはもう伝説ではなく“現実の謎”だったのだ。
それに乗じて、灰の目は一気に台頭。
貴族でも、軍でも、教会でもない、“事実”を商う組織として名を広げた。
皮肉にも、その台頭を後押ししたのは、他でもない——ガイウスの絵だった。
「報酬目当てのバイトだから!」
彼は何度もそう言い訳している。
だが、灰の目の報告書にはこう記されている。
『ガイウス・アルドレッド氏の描画は、視覚的記録を超え、
六将の残滓・魔力痕跡・地形構造まで忠実に再現する。
これは記憶術や魔法学をも凌駕する“再現視覚”の一種と推定される。』
——特異体質。
本人の意識とは無関係に、見たものの“真実”を描き出す目。
だからこそ、彼のスケッチには魔力の流れまで浮かび上がってしまう。
灰の目は、その力を利用しようとした。
しかし同時に、彼の独立性を尊重し、“バイト契約”の体裁を保っている。
表向きはイラストレーター、裏では国家を越える情報協力者。
つまり、ガイウスが六将を追うための合法的な出入り許可や潜入ルートを確保する、
いわば政治と軍を出し抜く“灰の仲介屋”でもある。
それは彼にとって、最大の皮肉であり、最も頼れる繋がりでもあった。
一年前の悪ふざけが、今では戦場の裏を支える力になっている。
あのとき笑って送ったスケッチが、今は世界を動かしている。
——が。
「勇者ガイウス殿」
宿の入り口に立つ男の声が響く。
灰の目の使者。漆黒のコートに灰色の徽章。
目は静かに笑っていた。
「正式に“灰筆師候補”として登録させて頂きたい」
ガイウスの表情が、秒で崩壊した。
「いやだぁぁぁああ!! 俺は描きたくて描いてるんじゃねぇ!!」
ベンチから立ち上がり、全力で拒否。
まるで小学生の職業体験を断るかの勢いである。
ハオは頬をゆるませた。
「ネコもヨロコんでるヨ〜」
「裏切るな猫ォ!!」
膝の上の猫が、ちょうどその瞬間、ゴロゴロと喉を鳴らした。
その音が、まるで賛同の拍手のように聞こえた。
……それでも、彼は描き続ける。
報酬目当てのバイトと言いながら、誰よりも正確に“真実”を捉える線を引く。
描けば描くほど、世界の歪みが見えてしまう。
それを止めることは、もはや誰にもできない。
だからこそ、人々は彼をこう呼ぶ。
“灰筆師ガイウス”
——真実を描く男。
そして、描きたくもない現実を、誰よりもうまく描けてしまう男。
猫は再び丸くなり、陽だまりの上で寝息を立てた。
ガイウスはその背を見つめ、苦笑しながらスケッチブックを開く。
「……報酬、上がるといいんだがな」
ペンが走る。
その線は、世界の真実を、またひとつ暴いていく。
軒先に干された布が風に揺れ、唐辛子と油の匂いが混じる昼下がり。
ホアリンの通りはいつも通り賑やかで、炒め油の音と笑い声が途切れない。
その人波を抜ける途中、ガイウスは小さく手を振る影を見た。
「あっ! 勇者さんだ!」
声が弾んだ。聞き覚えのある声。
振り向いた先に立っていたのは、懐かしい少女——いや、もう“娘”と呼ぶべき年頃だった。
黒髪に紅い紐を編み込み、目元にはうっすらと化粧の跡。
あのときロビーで無邪気に「わたしを描いて!」と叫んでいた少女とは違う。
あどけなさの中に、少し背伸びした都会の風を纏っていた。
「……お前、リーシャンか?」
「うん! 一年前より、背伸びたでしょ?」
笑顔は変わらない。けれど、その奥にある目の輝きは確かに強くなっていた。
十二歳の「素朴な可愛さ」から、十三歳の「夢を追う少女」へ。
人は一年で、こんなにも変わるものかとガイウスは思った。
「宿屋、手伝いは続けてんのか?」
「もちろん。継ぐ予定は……夢が破れたとき、かな?」
冗談めかして笑うその口調の奥に、決意があった。
「今はね、踊り子ギルドで修行中。お客さんの前に立つの、楽しくて」
ガイウスが答えようとした瞬間、背後からひょいと顔を出す男がいた。
「なるほど、わかるよ。昔の僕みたいな顔だね」
陽気な声。
バルトロメオがいつの間にか合流していた。
紅の外套を軽く翻し、相変わらずの芝居がかった笑みを浮かべる。
「そういう子はね、成功するよ。カンだけどね」
軽口に混じる真実の響き。彼は“夢を追って踊り続けた者”の顔をしていた。
リーシャンは頬を少し赤らめて、照れたように笑った。
「ありがとう、“踊り子の先輩”」
その言葉に、バルトロメオは肩をすくめて満足げに去っていった。
リーシャンの部屋に通されると、壁に一枚の絵が飾られていた。
それはメルクリウスが描いた、あの“事件10秒前”の似顔絵だった。
照明の下で見ると、妙に完成度が高い。
街灯の影、シルクのスカート、あの不穏なトランクケース。
全てが丁寧に額縁に収まり、まるで小さな祭壇のように飾られていた。
「……まだ取ってあったのか」
ガイウスの声に、リーシャンは嬉しそうに頷いた。
「うん。“いつか本当に事件を起こせるくらい有名になりたい”って思えるんだ」
「……やめろ、物騒な夢にすんな!」
呆れたように言いながらも、彼の口元は僅かに緩んでいた。
あのとき、無邪気に“描いて”と頼んできた少女が、今は夢を語って笑っている。
その笑顔が、自分の描いた過去の線よりも、ずっと“生きている”ように見えた。
窓の外では夜風が揺れ、遠くで誰かが笛を吹いていた。
ガイウスは壁の絵を一度見上げ、それから視線を落とした。
——あの時の線が、今も誰かの背中を押している。
それだけで、少し報われた気がした。
「……まぁ、踊り子の夢。応援してるよ」
「ほんと? じゃあ今度、ステージ見に来てね!」
その言葉に、ガイウスは困ったように笑いながら頷いた。
そして小さく、誰にも聞こえない声でつぶやいた。
「……事件じゃなくて、舞台で会えるなら、そっちの方がいい」
その夜、ホアリンの街の灯は静かに瞬き、
“絵を描く勇者”と“夢を描く少女”の再会を、やさしく照らしていた。
「にしてもあの絵、神官が描いたって信じられないわ」
ルッツがカップを置きながら呟いた。
「推理小説だったじゃん。完全に」
「ああ、俺も気になって聞いたんだよ」
ガイウスは肩をすくめる。
「ガキの頃、大人向けの推理小説ばっか読んでて、挿絵を模写してたんだとさ」
——聖教本部・大聖堂の片隅。
祈りと光に包まれた白い石壁の中で、一人の少年が黙々とペンを走らせていた。
名を、マーキュリー。後のメルクリウス・ゾルクォーデである。
彼は幼くして書写と聖歌を完璧に習得し、“神童”と呼ばれた。
だが、その眼はあまりにも鋭すぎた。
誰も気づかない歪みを見抜き、神の絵にさえ“嘘”を見出してしまう。
七歳のある日。
彼は授業中に宗教画を前に立ち上がり、無造作に紙を引き裂いた。
あまりの行為に司祭たちは息を呑む。
しかし少年の言葉は、もっと衝撃的だった。
「……この聖母像、構図がクソだ」
「っ……神に対してその口を──!」
「いやマジで。光源が逆。あと、この手。死体の手だろ」
司祭たちは青ざめた。
少年の分析は正しかった。
絵の作者が、実際の遺体をモデルにしていた事実を、誰よりも先に見抜いたのだ。
その日から、マーキュリーは“神童”ではなく“魔眼の子”と呼ばれるようになった。
孤立した少年の世界を変えたのは、一冊の本だった。
地下書庫で司祭見習いが落とした埃まみれの小説。
表紙は破れ、題名だけが残っていた——《葬られた午後の誓約》。
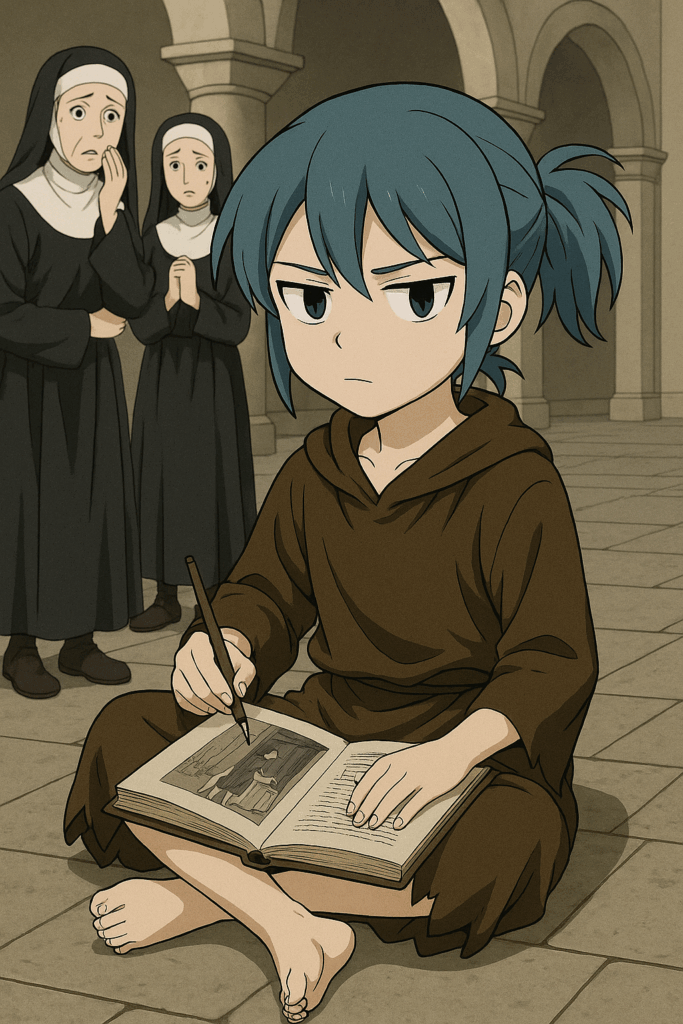
血のような赤インク。曇った鏡。殺された神父。
少年はページをめくるごとに、胸が熱くなるのを感じた。
神の沈黙よりも、真実を掘り起こす人間の叫びが、何倍も“生きている”と思った。
マーキュリーは本を閉じ、呟いた。
「俺はね、上から見下ろすだけの“神”より……」
「泥を這って真実を見つける探偵のほうを信用してる」
「こいつら、命賭けてんだよ」
その瞬間、少年の瞳に宿ったのは“神の光”ではなく、“探偵のまなざし”だった。
信仰の天才は、皮肉にも“疑う才能”に目覚めてしまったのだ。
「……出発点、そこ!?」
バルトロメオがコーヒーを吹いた。
「神童、完全にサスペンスに育てられてんじゃん!」
「まぁ、あいつらしいだろ」
ガイウスは苦笑しながら立ち上がる。
窓の外、ホアリンの街は夕陽に染まり、石畳が赤く光っていた。
軒先では、猫が寝そべっている。
あの時描いた猫かどうかは、もう分からない。
けれど、丸まった背中も、閉じた瞼も、何も変わっていなかった。
ガイウスはしばらくその姿を眺め、ふっと息を漏らした。
「……この街、やっぱり絵になるな」
風が通り、紙がめくれた。
そこに新しい線が描かれていく。
描けば描くほど、世界が少しだけ鮮明になる気がした。
彼はペンを走らせながら、ゆっくりと笑った。
神でも探偵でもなく、ただ“描く者”として。
その線が、また誰かの夢を動かすことを——
彼は、まだ知らない。