騒動の中心、診察室。
あまりに広まりすぎた“ロケットパンチ説”に、
当の本人・リベリオは、今日も涼しい顔でこう言った。
「私が……ロケットパンチを撃てると?」
「撃てません」
──とんでもねぇ大嘘である。
「嘘つけええええええ!!」
先にブチギレたのはイグニスだった。
健康診断で正気を削られた分の怒りをフルチャージ。
「お前のレントゲン、完全にロボだったぞ!?肘んとこスライド式だったじゃん!!」
ノランも叫ぶ。
「腹黒のくせにレントゲンかっこいいの狡いぞ!!!」
怒りの理由が理不尽すぎる。
リベリオは微笑を崩さぬまま、静かに紅茶をすする。
その“胡散臭さMAXの一口”に、
室内の空気がさらに重くなった。
突如、診察室のドアが吹き飛んだ。
「誰が吹き飛ばせって言ったああああああああああ!!!」
イグニスが叫ぶより早く、貴族然とした姿が現れる。
「……クヴァル君。ノックはしてくださいね」
リベリオは微笑を保ったまま、瓦礫の山を見つめる。
「俺の蹴破る音がノックだ」
クヴァル、理不尽ここに極まれり。
その背後で、ひょこっ、と顔を覗かせる狼耳。
「……いじめないでね……」
声の主はアリエッティ。
ぐるぐる巻きの毛布を引きずりながら、小動物モード全開でぴこぴこ耳が揺れる。
クヴァルの笑い声が、部屋の空気をほんの一瞬だけ引き締めた。
「じゃあ訊くが署長よ……」
視線はまっすぐリベリオに向いている。どこか挑発じみた目つきだ。
「この中で一番“分離射出”って単語似合うの、誰だと思う?」
答えを待つまでもなく、リベリオの口角がすっと上がる。
「……ノランですかね?」
その瞬間、ノランのツインテが逆立った気がした。
「なんでだよ!!!!」
声は思いっきり裏返り、周囲に響く。
リベリオは肩をすくめて、紅茶のカップを軽く持ち直す。
「いやぁ。ほら、戦闘機とかに乗せたら」
「開始3秒で撃ち落されて、“分離射出”ボタンだけは迷いなく押していそうじゃないですか」
真顔でそんなことを言うものだから、一同しばらく呆然とする。
ノランは盛大にむくれながら、スマホをいじる手を止めて見せる。
「え、いや、さすがに3秒は盛りすぎ!もっと粘るし!」
「しかも撃ち落されてからイジェクトするタイプじゃないから!!」
それでもリベリオは動じない。
「ご安心を、ノランさん。着地後の『即自撮り生配信』までワンセットで想定済みです」
完璧なまでに用意された腹黒スマイル。
「分離射出系配信者…なんかバズりそうで嫌だな…」
クヴァルは「むしろ生きて帰ってきそうだから怖い」と半笑い。
ノランは苦笑いしながら「帰ってくるに決まってるだろ!サムネ用に!」と答える。
牢内はまたしても変な笑いに包まれるのだった。
「……まったく、君たちも物好きですね」
囚人たちのロケットパンチ連呼に。
リベリオは紅茶を啜りながら、心底呆れたように笑った。
「大体ロケットパンチなんて……ふっ」
「あんな実用性もへったくれもない兵器、サイボーグに付けるわけないでしょう?」
理路整然とした物言い。
語彙も仕草も全てエリート。
「戦闘の最中に腕を飛ばすなんて、正気の沙汰じゃありませんよ?」
だが言葉の裏にある記憶を、彼自身も時折ふと思い出すことがある。
──昔、まだ“人造人間”として設計され始めたばかりの頃。
【記憶映像・回想モード ON】
白く光る実験室の奥、整備台に座る少年・リベリオ。通称「ショタリオ」。
目の前には軍帽を被った、眠たげな中年技術者。
レイバー・ククルス准将。サイボーグ開発の最高責任者。
「Code:Rebellion。今から最終調整を行う」
「……何か希望はあるか」
その問いに、少年は少しだけ考え――
「……ロケットパンチをつけてください」
静まり返るラボ、沈黙するレイバー。
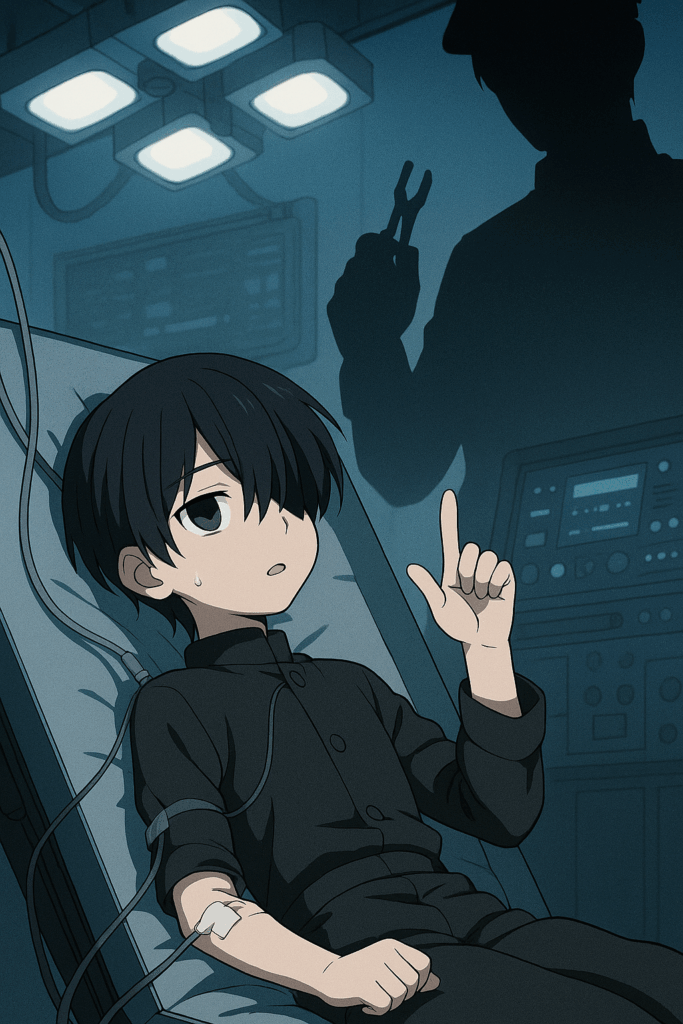
「……………いいぞ」
「やった」
ショタ時代唯一のワガママがロケットパンチだったという事実。
それを誰よりも知っているのは、もちろんリベリオ本人である。
なのに、今の発言。
「戦闘中に腕を飛ばすなんて、狂気の沙汰ですよ」
本人が言った。しかも要求した。しかも即採用された。
室内にいた全員が、同時に思った。
「まじでこいつ……」
それでもなお、リベリオは笑っていた。
紅茶のカップをくるりと回しながら。
「……さて、そんな都市伝説より」
「今夜の献立は、どうしましょうかね?」
事の発端は、ノランの一言だった。
「じゃあ私たちの中じゃ、署長は撃てる設定でいくからな!!」
言い切った。
決定事項になった。
事実より“設定”が優先されるのが、次元牢という魔窟である。
「……そんなに見たいんです?」
「そうやって騒ぐとですね、紅茶が不味くなるんですよ」
署長はそっとティーカップを置き、静かに立ち上がった。
「では、退室願えますかね?」
そのまま、右肘に左手を添え――構えた。
明らかに“撃つポーズ”を取った。
全員、硬直。
「撃てるじゃん!!?? マジで撃てるじゃん!!!!」
イグニス、パニック。だがテンション爆上がり。
「こえぇぇぇけどかっけぇぇぇ!!!」
「うわわわ!まじで撃つ顔だよあれ~~!にげよう~~~っ!!!」
アリエッティ、耳も尻尾もフルバタ。もはや毛玉。
「やべぇ撮り忘れた!!でも骨数本逝くよりマシだあああああっ!!」
ノラン、まさかの撤退判断。奇跡の理性。
「退却ゥゥーーー!!」
クヴァル、貴族のくせに速すぎる逃走宣言。
床が揺れるほどの全力退避。
その場に残されたのは、構えたままのリベリオただ一人。
「……おやおや」
肘から手を離し、微笑む。
「ほんの少し、“肘を触っただけ”で……あんなに怯えるとは」
そして静かに呟いた。
「いいネタを見つけましたよ」
その微笑は“撃たずに精神を砕く”究極のドS型兵器の完成を意味していた。
この日、“ロケットパンチ署長”の異名は、完全に定着したのである。
\ドンガラガッシャーーーン!!/
ドアが跳ね飛ぶ勢いで開かれた次元牢食堂。
「撃つぞアレ!絶対撃つぞアレ!!」
ノランが絶叫しながら飛び込む。
「肘だった!肘からいくぞあれ!!」
イグニス、再確認のテンパり。
「耳に悪い!あんな音は耳に悪いっ!!」
クヴァル、耳を押さえて叫ぶ貴族。
「お茶会じゃなくて処刑会だよぉぉ……!!!」
アリエッティ、すでに半泣き。尻尾がすごい勢いで床掃除中。
四人、椅子ごと倒れ込むように逃げ込む。
しかし、その先にいたのは――
スイーツタワーを囲んで超☆平常運転中の二人組。
アヴィドは口いっぱいにスコーンを頬張っており、
その向かいには、紅茶をすするクアザールが優雅に座っていた。
アヴィドの笑顔は“柔らかそう”なのに、どうしようもなく温度がなかった。
「どしたん? 話、聞こうか」
その一言が、食堂の空気をキンと凍らせる。
“元ネタ”の面影は皆無、返答に困るレベル。
不自然な静寂の中、ノランがスマホを握りしめながら、吐き捨てるように呟く。
「アヴィー……下心とかじゃなくて、もっとヤバい意味にしか聞こえないんだけど」
続くイグニスも、少し顔を引きつらせたまま同意する。
「……“ヤリ目”じゃなくて“殺り目”だな」
誰も笑わない。むしろ、本気で引き気味だ。
だがアヴィドは悪びれもせず、いつもの半目で「否定はしないよ~」とへらり。
その“無害な顔”が、逆に誰よりも危険だった。
アリエッティは恐怖で固まり、声にならない悲鳴を上げて耳を震わせている。
「ぴぇぇぇ……」
すでに言語を失い、椅子ごと机の下に隠れそうな勢いだ。
スイーツの香り漂う食堂が、一瞬で修羅場の気配に包まれる。
たかが「話聞こうか」、されど「話聞こうか」──
この牢獄、優しさの定義が根本的におかしい。
そこへ、平然とクアザールの声。
「話の流れが、ちょっと見えませんが……」
「とりあえず、落ち着きましょう?ほら、スコーンありますよ」
笑顔。完璧な英国紳士スマイル。
だが、ノランたちは――そのスコーンが「破裂音にしか見えない」
「まってこれ…もしかしてクアザールさんもロケットパンチ肯定派…?」
「この空間、まともなのアヴィドだけ説あるわ……」
「それはそれで末期じゃない?」
「しょくどうこわい……しょくどうなのに……おかしこわい……」
次元牢は今日も地獄のまま、美味しそうな香りが漂っていた。